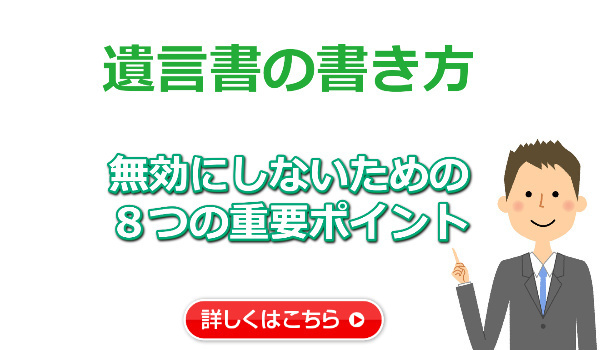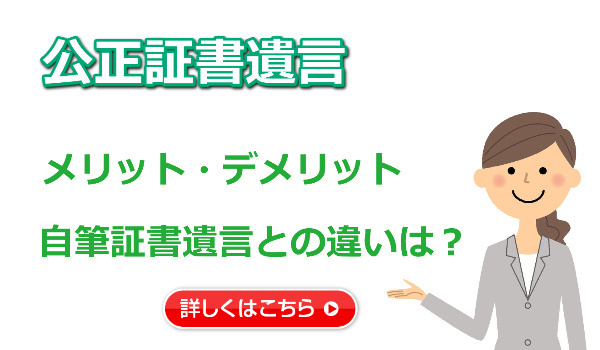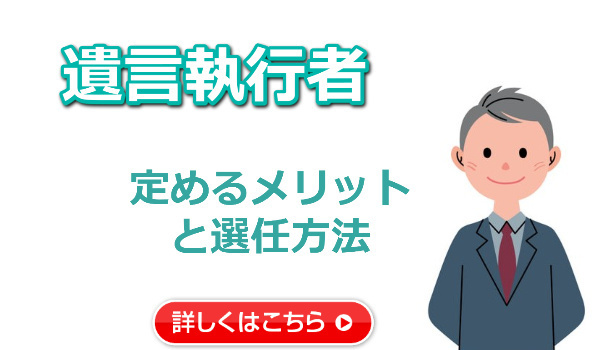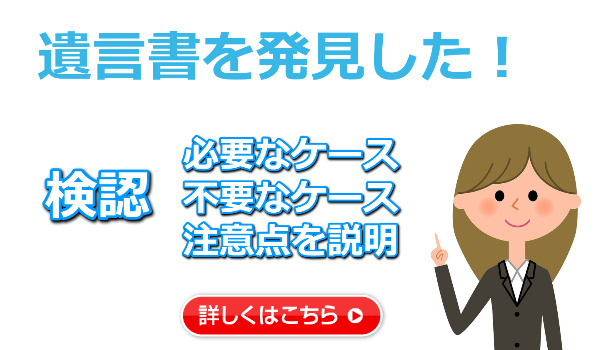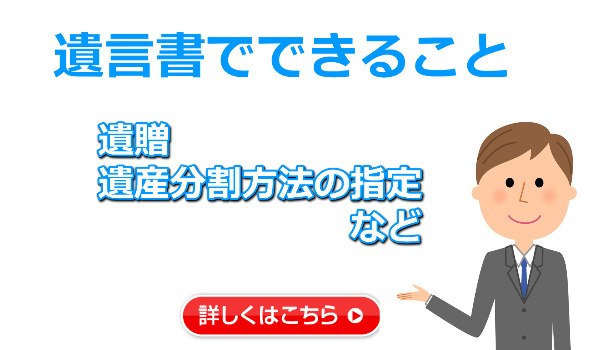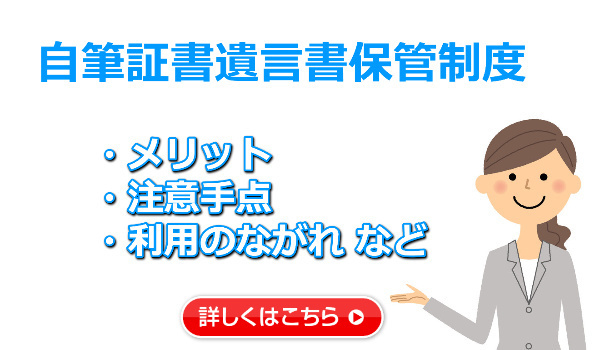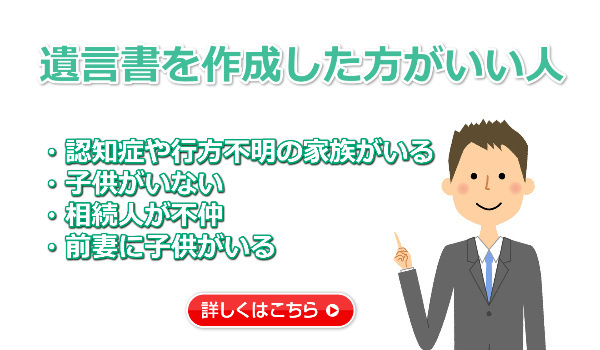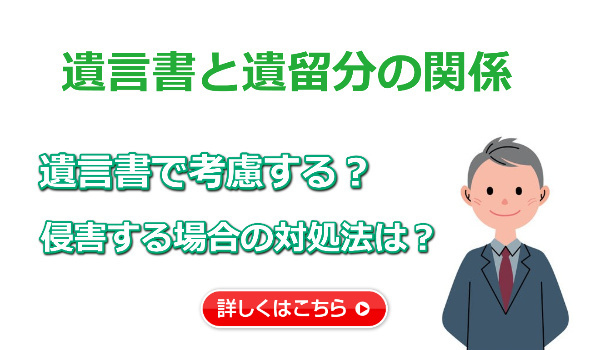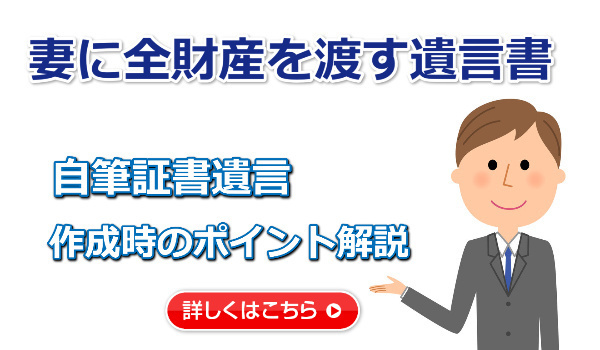相続・遺言に関する手続の総合案内(合同会社つなぐ(FP)×司法書士法人黒川事務所×行政書士黒川事務所の運営サイト)
公正証書遺言の証人になれない人や依頼するときの費用を紹介
遺言書の中でも、作成するときに証人による立会が必要なものを「公正証書遺言書」と呼びます。
自筆証書遺言書と比べて、遺言書の原本が公証人役場で保管されるため、紛失・隠匿・偽造のおそれがないのがメリットです。
公正証書遺言の証人は、誰でもなれるわけではありません。
民法第974条では、証人になれない人(欠格者)を定めているため、公正証書遺言を作成する前に確認しておきましょう。
本記事では、公正証書遺言の証人になるための条件や、証人を依頼するときの費用をわかりやすく解説します。
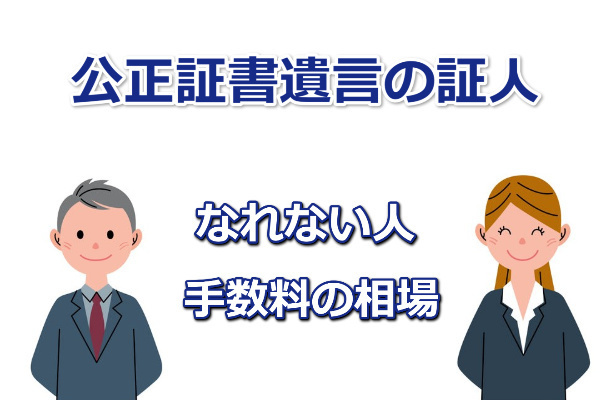
公正証書遺言の証人とは?
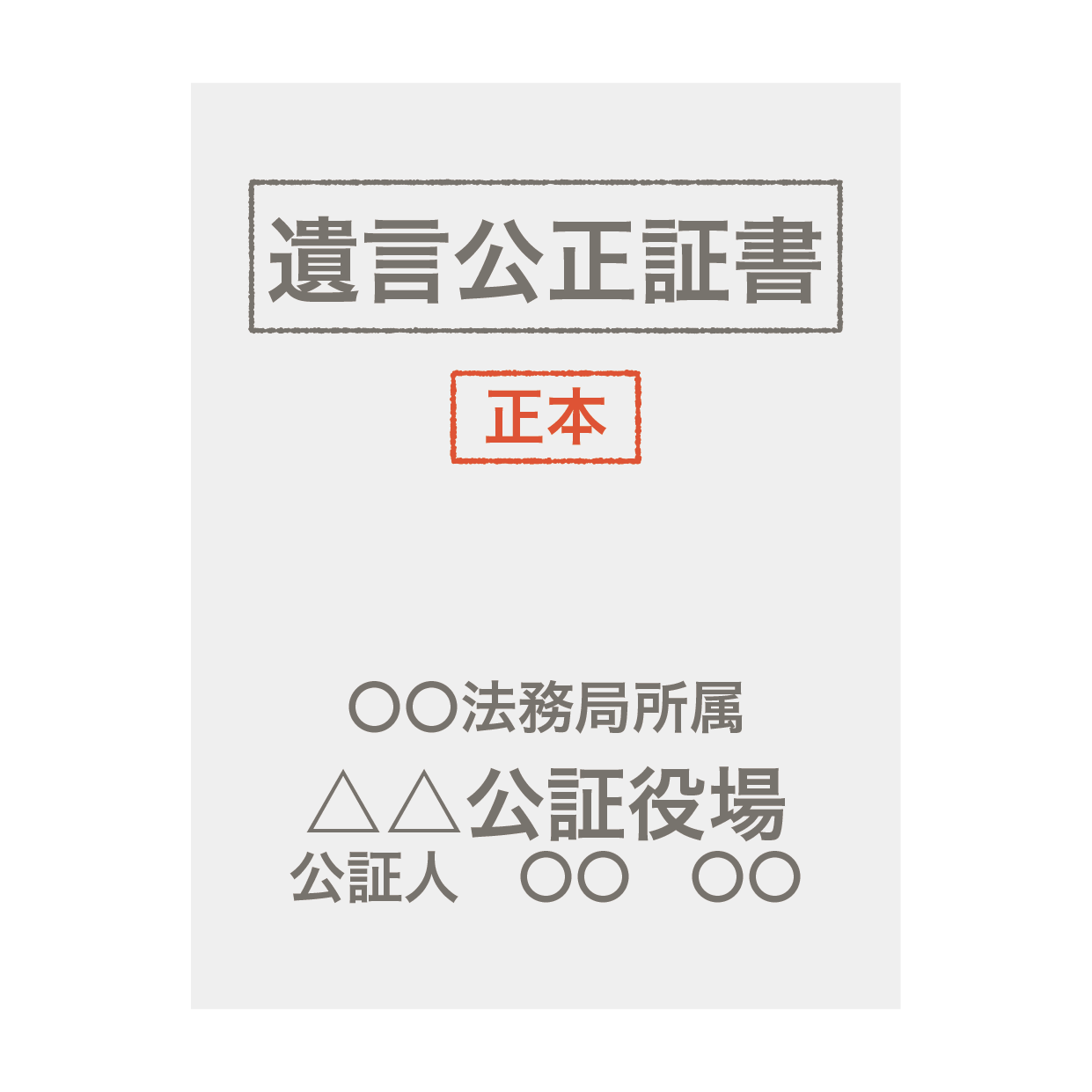
公正証書遺言とは?遺言書の作成方法は複数ある
法的な効力を持つ遺言書は、遺言の全文を自署する自筆証書遺言書、公証人役場で作成する公正証書遺言書、遺言書を秘密裏に作成する秘密証書遺言の3種類あります。
相続手続きで主に利用されるのは、自筆証書遺言書と公正証書遺言書です。
それぞれのメリット・デメリットは以下の表のとおりです。
| 項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
|---|---|---|
| 作成方法 | 遺言者が、日付、氏名、財産の分割内容等全文を自書し、押印して作成。 | 遺言者が、原則として、証人2人以上とともに公証人役場に出かけ、公証人に遺言内容を口述し、公証人が筆記して作成。 |
| メリット |
|
|
| デメリット |
|
|
公正証書遺言は証人が2人必要
公正証書遺言を作成する場合、民法第969条の規定により、2名の証人を用意する必要があります。
民法(第九百六十九条)
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
公正証書遺言の証人になれない人
民法第974条では、公正証書遺言の証人になれない人(欠格者)の条件を3つ挙げています。
民法(第九百七十四条)
次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
未成年者
被相続人の配偶者や直系血族など
公証人の配偶者や4親等内の親族など
公正証書遺言の証人を頼むときの費用

公正証書遺言の証人に対して報酬の支払いが必要な場合があります。
たとえば、公証人役場で証人を紹介してもらう場合や、弁護士や司法書士などの専門家に依頼する場合です。
公正証書遺言の証人を依頼するときの報酬額の目安は以下の表のとおりです。
| パターン | 報酬額の目安 |
|---|---|
| 弁護士や司法書士などの専門家に依頼する場合 | 1人当たり1万円程度 |
| 利害関係のない知人に依頼する場合 | 1人当たり5,000円~1万円 |
知人に依頼する場合は、報酬を支払う必要はありませんが、公証人役場に出かける手間などを考慮し、1人当たり5,000円~1万円のお礼を渡すことが一般的です。
公正証書遺言を作成する場合の手数料
公正証書遺言を作成する場合、公証人手数料令により、公証人に所定の手数料を支払う必要があります。
| 遺産の価格 | 手数料の金額 |
|---|---|
| 100万円以下のもの | 5,000円 |
| 100万円を超え200万円以下のもの | 7,000円 |
| 200万円を超え500万円以下のもの | 1万1,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下のもの | 1万7,000円 |
| 1,000万円を超え3,000万円以下のもの | 2万3,000円 |
| 3,000万円を超え5,000万円以下のもの | 2万9,000円 |
| 5,000万円を超え1億円以下のもの | 4万3,000円 |
| 1億円を超え3億円以下のもの | 4万3,000円に超過額5,000万円までごとに1万3,000円を加算した額 |
| 3億円を超え10億円以下のもの | 9万5,000円に超過額5,000万円までごとに1万1,000円を加算した額 |
| 10億円を超えるもの | 24万9,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額 |
なお、遺言で2名以上に遺贈する場合は、各相続人・各受遺者ごとに、「相続させ」または「遺贈する」財産の価額により目的の価額を算出し、それぞれの公証人手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。
さらに、「遺言加算」として、1億円までは1万1000円が加算されます。
【まとめ】公正証書遺言の証人になれないケースや手数料について知っておこう
公正証書遺言は、作成するときに2名の証人が必要な遺言書です。民法には、公正証書遺言の証人になれない欠格要件が定められています。未成年者、被相続人の配偶者や直系血族、公証人の配偶者や4親等内の親族は証人にはなれないため、それ以外の人を選びましょう。
公正証書遺言の作成には、法律で定められた公証人手数料のほか、証人を依頼した人への報酬の支払いが必要な場合もあります。