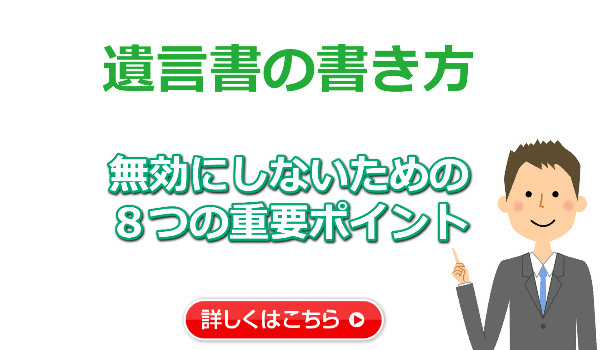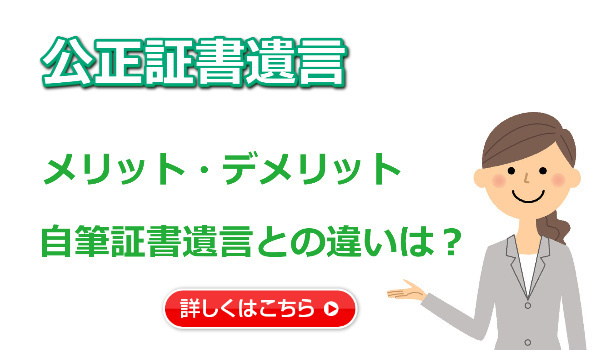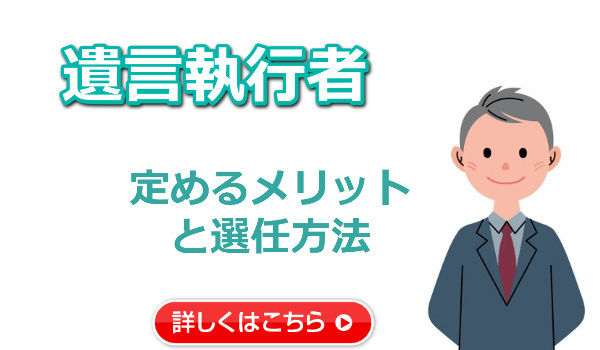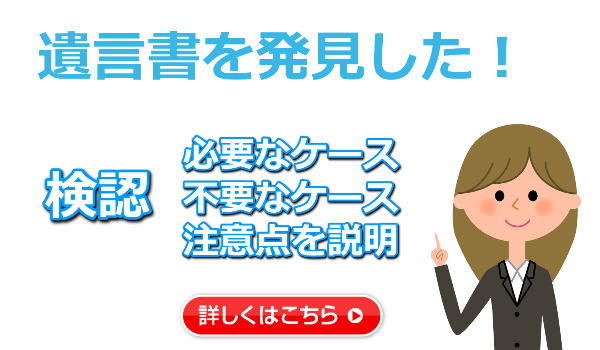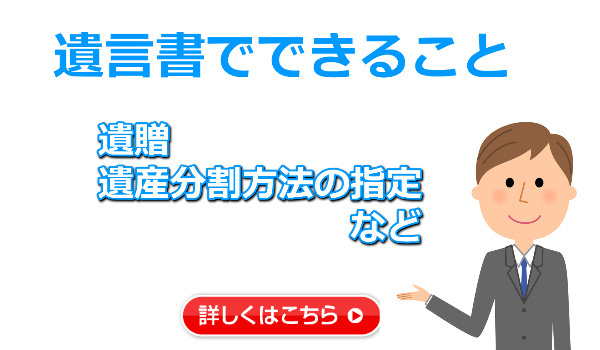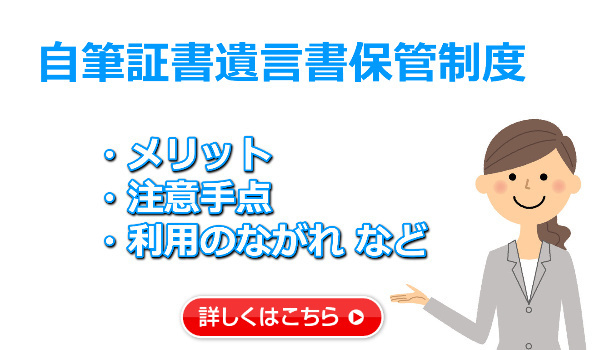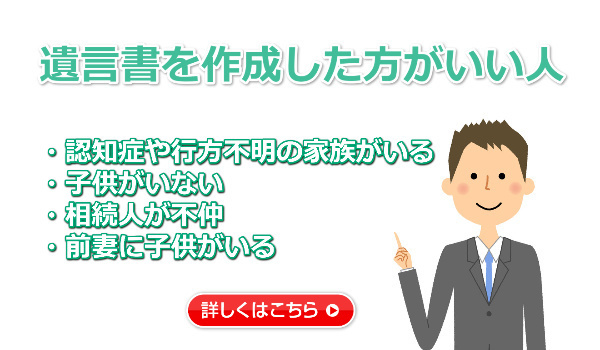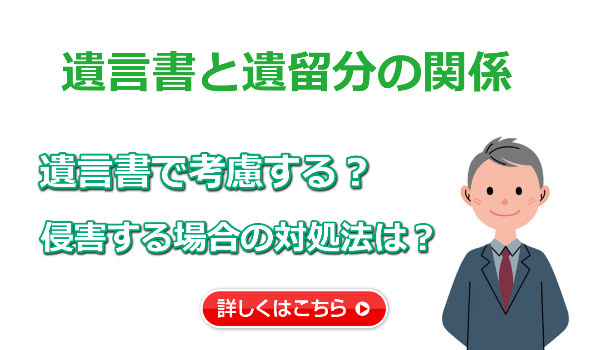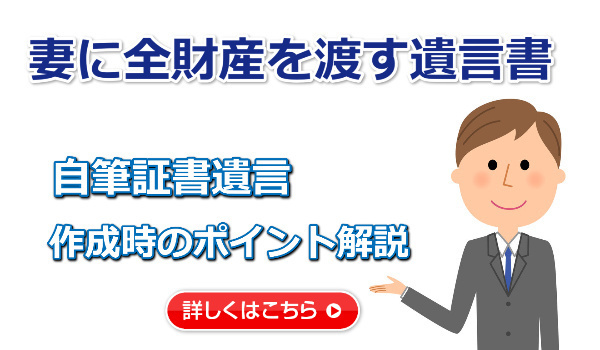相続・遺言に関する手続の総合案内(合同会社つなぐ(FP)×司法書士法人黒川事務所×行政書士黒川事務所の運営サイト)
公正証書遺言の必要書類や集め方・費用について
公正証書遺言を作成するには、いくつもの必要書類を集めなければなりません。
事前にどういった資料が必要か知っておけばスムーズに作成手続きを進められるでしょう。
今回は公正証書遺言の必要書類や集め方、書類収集にかかる費用をお伝えします。
これから公正証書遺言の作成を検討されている方は、参考にしてみてください。
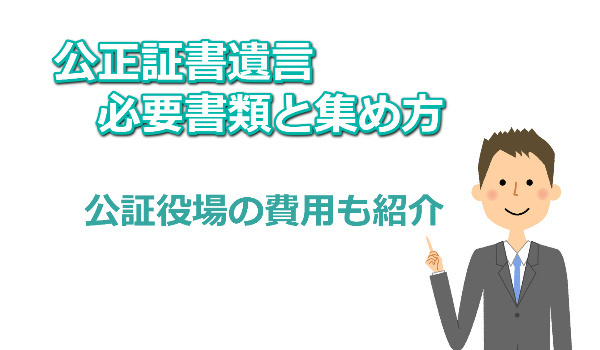
公正証書遺言の必要書類
公正証書遺言とは
公正証書遺言は公務員の一種である公証人に作成してもらうタイプの遺言書です。
自分で作成する自筆証書遺言より無効になりにくく、原本が公証役場で保管されるので紛失リスクもありません。文字を書けない状態でも遺言書を作成できます。死後に相続人が家庭裁判所で検認を受ける必要もないのも、メリットとなるでしょう。
当事務所でも、遺言書を作成する際には基本的に公正証書遺言をおすすめしています。
公正証書遺言の必要書類と入手先一覧
公正証書遺言を作成する際の必要書類と入手先を一覧にて示します。
| 書類の名称 | 取得できる場所 |
|---|---|
| 本人確認書類(印鑑証明書、運転免許証、マイナンバーカードなど) | 自分で保管している、あるいは役所など |
| 遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本(全部事項証明書) | 本籍地のある市区町村役場 |
| 受贈者の住民票 | 受贈者が居住している市区町村役場 |
| 法人へ寄付する場合には法人の資格証明書 | 法務局 |
| 不動産の登記事項証明書と固定資産評価証明書 | 登記事項証明書は法務局、固定資産評価証明書は不動産が所在する市区町村の役場 |
| 証人を用意する場合、証人の住所や職業、氏名や生年月日がわかる資料 | 本人確認資料の写しやメモなど |
| 遺言執行者がいる場合、その人の住所や職業、氏名や生年月日がわかる資料 | 本人確認資料の写しやメモなど |
| 代理人に依頼する場合には印鑑登録証明書 | 住民登録と印鑑登録している市区町村の役場 |
| 代理人に依頼する場合には代理人の本人確認書類 | 代理人に依頼する |
本人確認書類について
本人確認書類としては、以下の組み合わせの「いずれか」が必要です。
- 印鑑証明書と実印(住民登録と印鑑登録している役場で取得)
- 運転免許証と認印(自分で保管している)
- マイナンバーカードと認印(自分で保管しているか、役場へ申請して取得する)
- 住民基本台帳カード(写真付き)と認印(役場へ申請して取得する)
- パスポート、身体障害者手帳又は在留カードと認印(自分で保管している)
預貯金がある場合には預金通帳(金融機関名、支店名、口座番号がわかるもの)、株式がある場合には銘柄や数量がわかるものを用意しましょう。
公証役場によっても必要書類の具体的な内容が異なるケースもあります。財産や遺言内容により、上記以外の資料が必要となる可能性もあるので、詳しくは事前に公証人へ確認しましょう。
公正証書遺言の必要書類取得にかかる手数料
| 書類の名称 | 手数料 | 取得先 |
|---|---|---|
| 印鑑登録証明書 | 300円 | 住民登録と印鑑登録している市区町村役場 |
| 戸籍謄本(全部事項証明書) | 450円 | 本籍地のある市区町村役場 |
| 住民票 | 250~300円 | 住民登録している市区町村役場 |
| 不動産の全部事項証明書 法人の資格証明書 | 600円 | 法務局 |
| 固定資産評価証明書 | 350~450円程度(市区町村によって異なる) | 不動産が所在する市区町村役場 |
| 預貯金の明細 | 無料~数百円程度 | 取引先の金融機関 |
| 株式の明細 | 無料が多い | 証券会社 |
合計しても、数百円~数千円以内におさまるケースが多いでしょう。
ただし公正証書遺言を作成する手数料は別途かかります。
金額は以下のとおりとなっていて、遺産の価額によって変動します。
公正証書遺言を作成する手数料
| 目的の価額 | 手数料 |
|---|---|
| 100万円以下 | 5000円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
| 200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
| 500万円を超え1000万円以下 | 170000円 |
| 1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
| 3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
| 5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
| 1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に対し、5000万円までごとに1万3000円を加算 |
| 3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に対し、5000万円までごとに1万1000円を加算した額 |
| 10億円を超える場合 | 24万9000円に対し、5000万円までごとに8000円を加算した額 |
遺言内容にもよりますが、数万円程度はかかるケースが多いでしょう。
また公証人から証人を紹介してもらったり公証人に出張してきてもらったりすると、さらに数万円の費用が発生します。
公正証書遺言の作成は司法書士へ依頼できる
公正証書遺言ではたくさんの必要書類を集めなければならず、公証人とのやり取りもしなければならないので手間がかかります。
司法書士に手続きを依頼すると、手間を省けてスムーズに遺言書を作成できるメリットがあります。
以下で司法書士にどういったことを依頼できるのか、ご紹介します。
遺言内容を相談できる
公正証書遺言を作成する際には、事前に遺言内容を自分で決めておかねばなりません。
公証役場では遺言内容についての相談には応じてくれないので注意が必要です。
ただ現実的に「どのような遺言内容が最善なのか」を素人の方が判断するのは難しいでしょう。自己判断で遺言書を作成すると、遺留分を侵害してトラブルになってしまう可能性もあります。
司法書士であれば、遺言者の希望や遺産内容をみて、総合的にどういった遺言内容が適しているか判断できます。トラブルを防いで遺言者も相続人も納得できる遺言書を作成しやすくなると大きなメリットとなるでしょう。
スムーズに遺言書を作成
公正証書遺言を作成するにはたくさんの書類が必要です。
手間取る方も多いのですが、必要書類が揃わないと遺言書を作成できないので、書類集めに難航するといつまでも遺言書が出来上がりません。
司法書士に任せれば、書類集めや公証人とのやり取りなどの対応を任せられるので、遺言者にかかる労力が軽減されます。
専門家の関与によってスムーズに遺言書を作成できることも大きなメリットとなるでしょう。
証人の費用を節約できる
公正証書遺言を作成するには2人の証人が必要です。また証人には一定の資格が必要で、資格のない人に証人を依頼すると、公正証書遺言が無効になってしまいます。心当たりのない場合には公証人に紹介をお願いできますが、その分費用がかかってしまうのもデメリットです。
司法書士に遺言書作成を依頼すると証人も引き受けてもらえるのが一般的なので、証人を探す手間や費用を抑えられるメリットがあります。
遺言執行者となり遺言を確実に実行できる
公正証書遺言の内容を確実に実行するには、遺言執行者をつけておくようおすすめします。
遺言執行者とは、不動産の相続登記や預貯金払い戻しなどの具体的な遺言内容を実現する役割を果たす人です。
司法書士に公正証書遺言の作成を依頼すると、遺言執行者への就任も依頼できます。これにより、遺言内容が確実に実現されやすくなるのはメリットといえるでしょう。
法人組織になっている事務所を選ぶ
司法書士などの専門家へ遺言執行者を依頼するときには「法人」組織を選ぶようおすすめします。個人の場合、その方が亡くなったり事務所を廃業したりすると、遺言執行してもらいにくくなるためです。
法人であれば、専門家個人に何かあっても法人が活動している限り、対応してもらえます。
黒川事務所は司法書士法人として営業していますので、ご安心してご依頼いただけるでしょう。
公正証書遺言を作成する際には、安全かつスムーズに進めるためにも専門家に相談しましょう。
当法人では遺言や相続対策に非常に力を入れており、必要書類や費用、作成手順、遺言内容などについて親身になってアドバイスさせていただきます。
東京や横浜、大阪にオフィスがあり多地域にてご相談を承りますので、お気軽にご相談ください。
監修者:黒川聡史

保有資格と所属団体
- 司法書士:東京司法書士会所属:登録番号4230号
- 行政書士:東京都行政書士会所属:登録番号第19082582号
- FP(FP技能士1級:日本FP協会CFP®)
経歴
昭和51年生まれ。平成13年司法書士と行政書士の資格取得後、都内司法書士事務所で勤務。平成19年に独立開業し、平成30年に法人化し司法書士法人黒川事務所となる。また、ファイナンシャルプランニング技能士1級及びCFP®を取得しFPとしても活動している(合同会社つなぐ)。