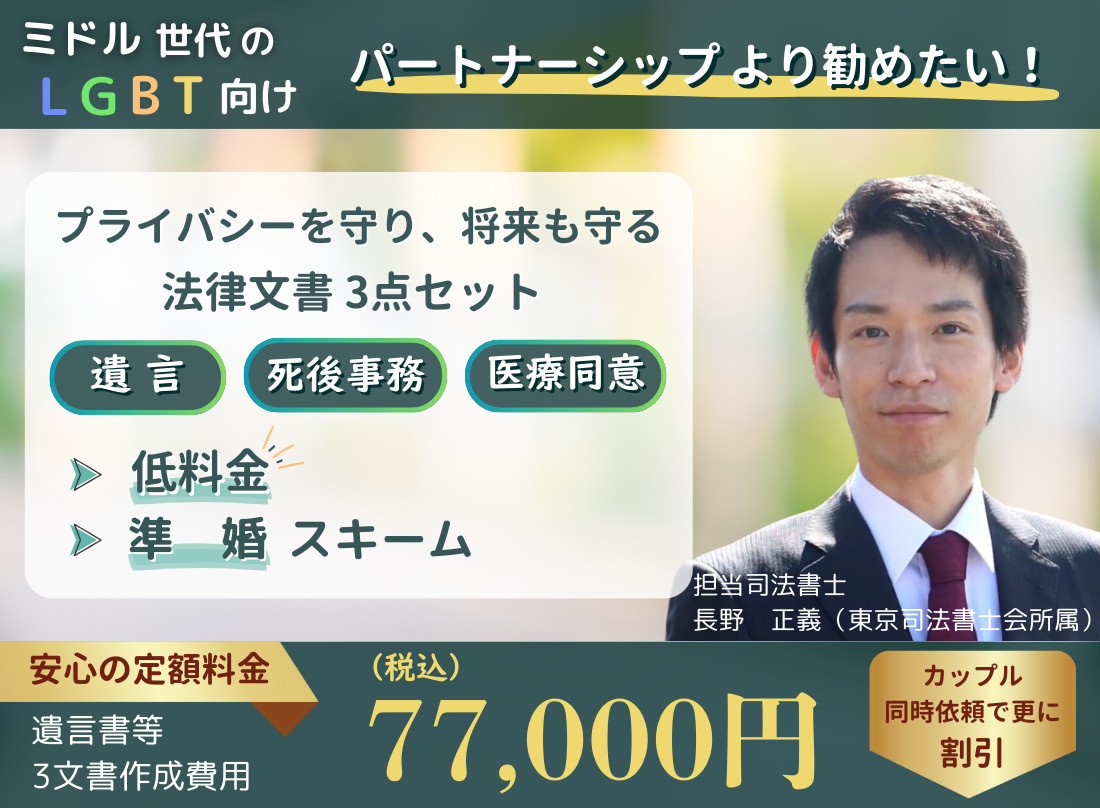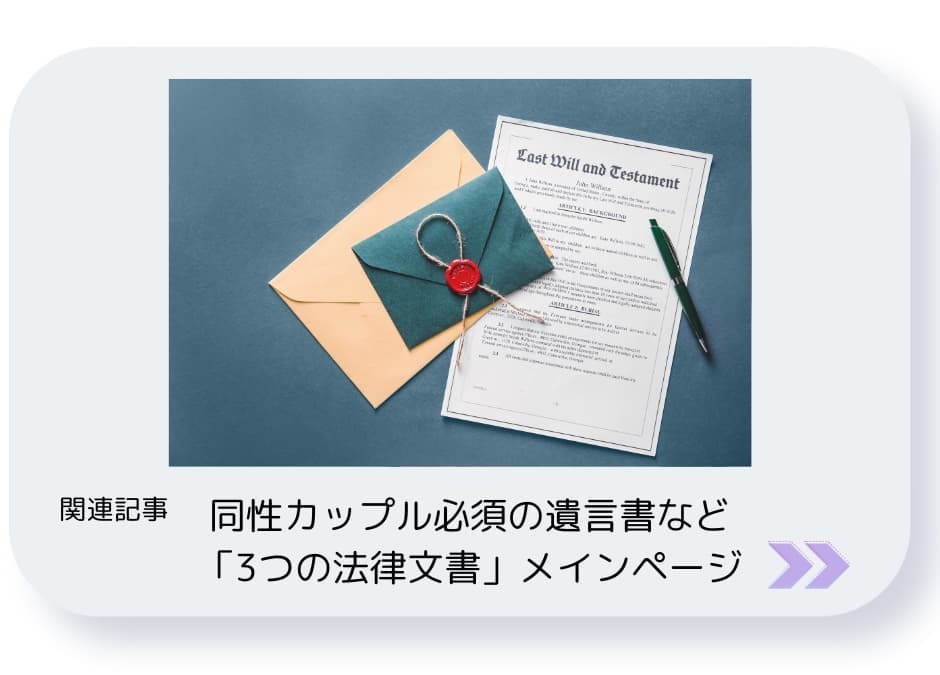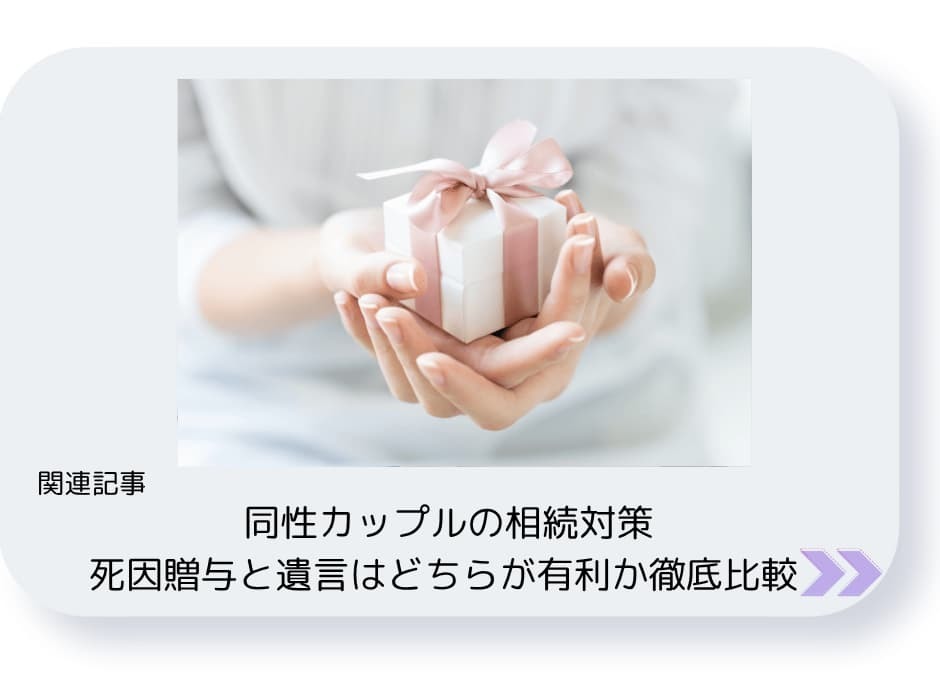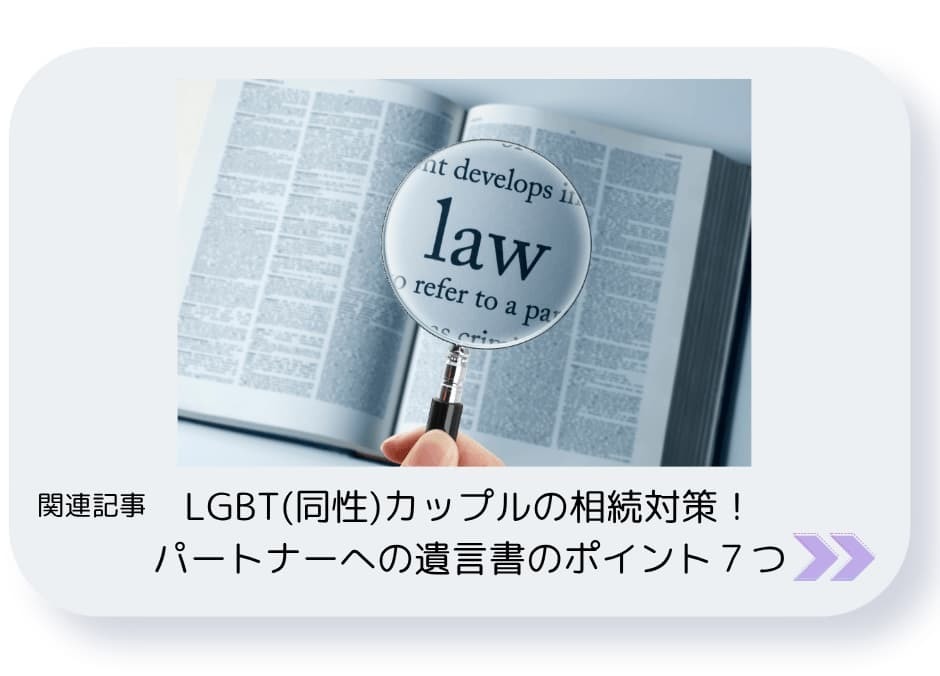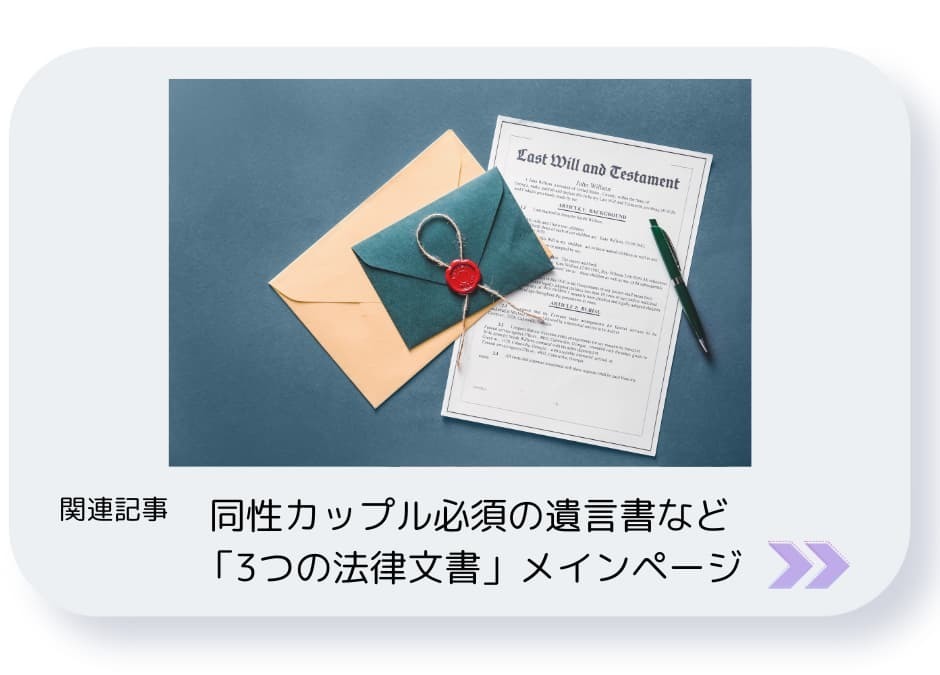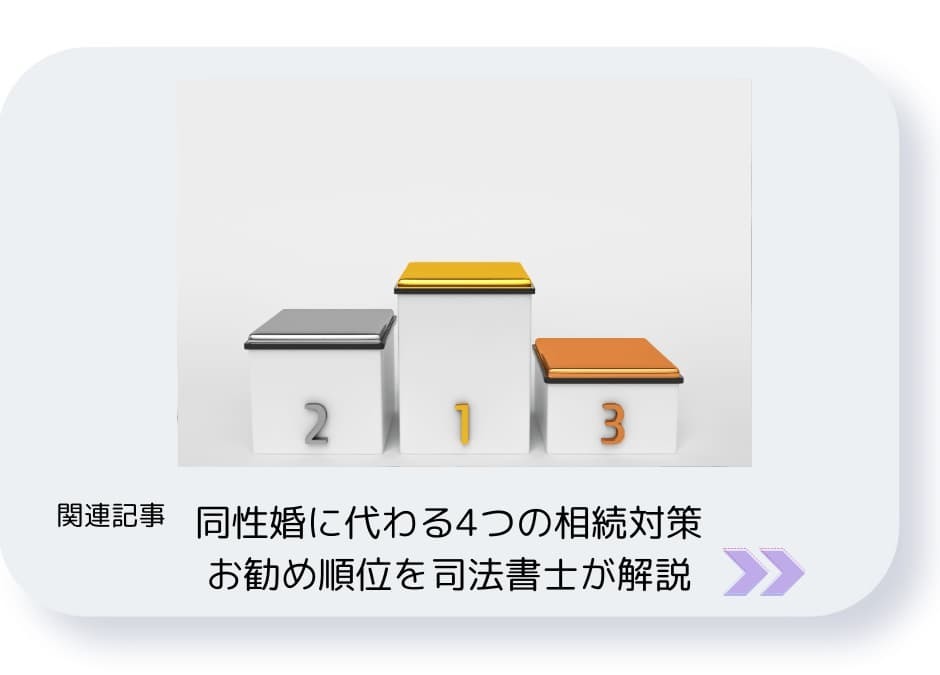相続・遺言に関する手続の総合案内(合同会社つなぐ(FP)×司法書士法人黒川事務所×行政書士黒川事務所の運営サイト)
同性パートナーへの遺言は公正証書にしないのも選択肢!リスクや費用で分析
「公正証書の方が安全なのは分かるけど、費用も抑えたい」
遺言書を実際に作るのか決める際に、まず気になるのが費用だと思います。
当事務所では、レズビアンやゲイなど、ミドル世代のLGBTの方向けに遺言書など「3つの法律文書」をお勧めしています。
しかし、ミドル世代の方であれば、死亡や重病というリスクは高齢の方よりも低いため、低い発生確率に応じて費用も抑えたいと考えるのは当然だと思います。
今回は、遺言書をどの方式で作成すべきなのかについて解説します。作成の方式によって、費用やリスクヘッジの面で大きな差が出てくるためです。
表を多用して、どのサイトよりも詳しく分かりやすい内容を目指していますので、遺言書の作成を検討中の方はぜひご参考にされてください。

目 次
遺言書は主に2種類
ほとんどの遺言書は、下記の2種類のどちらかで作成されます。
遺言書の種類
| 意義 | 遺言書の保管場所 | |
|---|---|---|
| 公正証書遺言 | 公証役場という役所で、公証人という法律専門職に作成してもらう遺言 | 公証役場 |
| 自筆証書遺言 | 公証人の関与なく自分で作成する遺言 | 制限なし(法務局保管制度あり) |
少し前までの法律専門職の間では、遺言書は公正証書一択というのに近い程度でお勧めするのが一般的でした。
しかし、公正証書にしないという選択肢も、令和2年に法務局保管制度が施行されたことにより、十分検討に値するようになりました。
リスク:比較表で見えてくる自筆証書遺言の危うさ
-この章の目次-
2-1.【比較表】紛争リスク
2-2.偽造を疑われない
2-3.作成時の認知症を疑われない
2-4.形式に問題がない
2-5.内容に問題がない
2-6.紛失や改ざん等の恐れがない
2-7.生前は関係者に知られない
2-8.死後すぐ発見される
2-9.死後すぐ権利保全(登記)可能
2-10.リスクのまとめ
【比較表】紛争リスク
| 公正証書 | 自筆証書 | 自筆証書法務局 保管 | |
|---|---|---|---|
| 紛争要素 | 安全性 | ||
| 偽造を疑われない | ○ | △ | ○ |
| 作成時の認知症を疑われない | ○ | △ | △ |
| 形式に問題がない | ○ | △ | ○ |
| 内容に問題がない | ○ | △ | △ |
| 紛失や破棄・改ざんの恐れがない | ○ | △ | ○ |
| 生前は関係者に知られない | △ | △ | ○ |
| 死後すぐに発見される | △ | △ | ○ |
| 死後すぐに権利保全(登記)できる | ○ | △ | ○ |
偽造を疑われない
作成時の認知症を疑われない
形式に問題がない
内容に問題がない
公正証書遺言の場合、公証人という法律専門職が作成に関与するため、遺言の内容についてもアドバイスをしてくれます。
公証人の本分は遺言者の言うことを公正証書に落とし込むということにあるので、内容についてどこまで踏み込んでアドバイスをしてくれるかは人によってかなり温度差があるようです。
とはいえ少なくとも、無効に陥りかねないような問題がある場合は適切なアドバイスをしてくれます。

紛失や破棄・改ざんの恐れがない
生前は関係者に知られない
公正証書遺言の場合、遺言書の原本は公証役場に保管され、生前は遺言者本人しか検索や閲覧をすることはできません。
ただし、死後に公正証書遺言の存在に気付かれないまま相続人に相続財産を処分されるリスクを考慮すると、 一部の親族や受遺者(遺言書で贈与を受ける人)には 遺言をのこした旨を伝えておく等の対策が必要になります。
伝えておく相手方としては、遺言者と同居しているなど、遺言者の死亡の事実をすぐに把握できる人が望ましいでしょう。
自筆証書遺言で法務局に保管しない場合も、同様の対策が必要になります。

死後すぐに発見される
自筆証書遺言で法務局保管の場合、保管申請の際に通知先を指定して希望すれば、死後に法務局から遺言保管の事実を通知してもらうことが可能です。これを「指定者通知」といいます。
この通知先には、家族や相続人に限らず、誰でも指定可能で、最大3名まで登録できます(令和5年10月施行の制度改正以降)。
法務局において遺言保管の部署と戸籍の部署は連携していて、死亡届(届出期限は死後1週間)の受付直後に指定者通知が行われるため、死後速やかに遺言の存在を関係者に知らせることが可能になっています。
これに対し、公正証書遺言は死亡に際して自動的に関係者に通知する仕組みにはなっていません。
公証役場で全国の公正証書遺言を検索するシステムはありますが、死後に関係者からの検索申請を待つものであるため、検索されずに遺言書は存在しないものとして相続人に相続財産を処分されるリスクがあります。
自筆証書遺言で法務局に保管しない場合は、通知制度も検索システムもないため、よりそのリスクは高まります。
死後すぐに権利保全(登記)できる
この部分はやや専門的な話になります。不動産をお持ちでない(当面買う予定もない)方は、読み飛ばすことをお勧めします。
まず前提として、不動産の遺贈(遺言書で行う贈与)を受けた人は、法務局に遺贈の登記申請(遺贈による不動産名義変更の申請)をできるだけ早く行う方が安全です。
というのも、もし法定相続人が先に一定の登記申請(法定相続の登記申請と第三者への売却の登記申請)を済ませてしまうと、本来遺贈を受けるはずであった人はその不動産を取得できなくなってしまうからです。
民法で、そのような早い者勝ちのルールになっています(民法177条)。
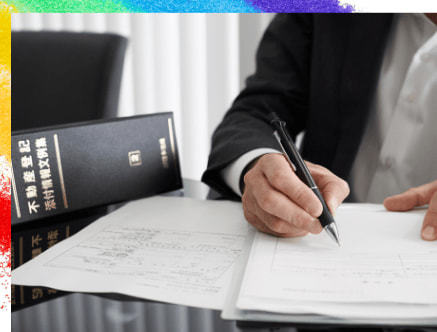
自筆証書遺言で法務局に保管しない場合、遺贈の登記申請までに時間がかかってしまいます。遺贈の登記申請の前に裁判所で「検認」という手続が必要とされているためです(民法1004条)。
検認の手続とは、相続人と裁判官の立会の下で遺言書の状態を確認・記録する手続であり、1〜3か月程かかります。
そのため、検認の申立準備や手続中に、法定相続人に登記申請の先を越されて、遺贈が実現できなくなるリスクがあるのです。
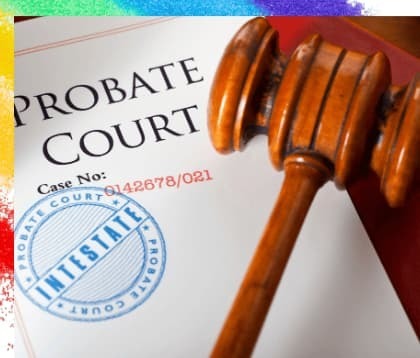
自筆証書遺言で法務局保管の場合、検認の手続は不要です。
そのため、法務局に保管しない場合よりは遺贈の登記申請をかなり早めることができますが、公正証書遺言よりは多少時間がかかります。
遺贈の登記申請に必要な遺言書謄本を法務局の保管部署から取得するのに多少時間がかかるためです(保管部署への提出書類として、遺言者の出生から死亡までの一連の戸籍等が必要で、その分量は多く、揃えるのに時間を要します)。
その反面、公正証書遺言は検認が不要ですし、遺贈の登記申請に必要な遺言書謄本も既に自宅にあるか、なくても比較的簡単に再発行請求をすることができます。
以上をまとめると、遺贈を法定相続人に覆されないようにするには遺贈の登記申請を急ぐべきで、そのスピードは公正証書遺言>法務局に保管した自筆証書遺言>>>法務局に保管しない自筆証書遺言という順になります。
なお、生前から登記を具備できる相続対策として、遺言ではなく死因贈与という方法もあります。詳しくは以下の記事をご覧ください。
リスクのまとめ
費用:公正証書は保管制度よりかなり高い
-この章の目次-
3-1.【比較表】費用
3-2.公正証書遺言の実費
3-2-1.公証役場手数料
3-2-2.証人費用
3-3.自筆証書遺言の実費
3-4.弁護士や司法書士への報酬
3-5.当事務所でのトータルの費用
【比較表】費用
| 公正証書 | 自筆証書 法務局保管 | |
|---|---|---|
| 実費 (公証役場・法務局) | 3万円以上 | 3,900円 |
| 証人費用 | 0~2万円 | 0円 |
| 報酬 (士業事務所) | 10~20万円 | 5~15万円 |
上記の表はかなり大雑把な目安です。詳細は下記で詳しく解説していきます。
公証役場の手数料は、遺贈する財産の金額によって大きく変わってきます。遺贈先の人数によっても多少変わります。
大まかな目安を把握していただくために、遺贈先が一人の場合の手数料額を表にしました。
遺贈先の人数が増える程、表の金額よりも少しずつ増えていきますが、平均的な経済力の40代の方がする遺言であれば、公証役場の手数料は5万〜8万円が多数といえます。
公証役場手数料の料金表
| 遺贈する財産額 | 手数料(概算) |
|---|---|
| 100万円以下 | 35,000円 |
| 1,000万円以下 | 50,000円 |
| 3,000万円以下 | 55,000円 |
| 5,000万円以下 | 65,000円 |
| 1億円以下 | 80,000円 |
なお、上記の表は、遺言書の正本謄本の発行手数料も含めた金額です。
また、「祭祀承継者」を定める前提での金額です。祭祀承継者については下記の記事で詳しく解説しているので、よければご覧ください。
証人費用
自筆証書遺言の実費
弁護士や司法書士への報酬
報酬は自由化されていますので事務所ごとに大きな開きがありますが、通常の遺言であれば10万〜20万円程度に設定している事務所が多い印象です。
また、自筆証書遺言よりも公正証書遺言の方が報酬を高く設定している事務所が多数です。
弁護士、司法書士、行政書士の報酬の相場については下記の記事でも解説していますので、よければご覧ください。
当事務所でのトータルの費用
当事務所のLGBTの方向け法律文書作成サービスでは、公正証書遺言も自筆証書遺言も同一の66,000円(税込)でお受けしています。
また、公正証書遺言で証人を事務所側で手配する場合にも、追加費用が発生することはありません。
そのため、実費も含めた当事務所でのトータルの費用は下記になります。
この表の中で公正証書遺言の実費は、平均的な経済力の40代の方を想定した概算額ですので、あくまで目安に留めていただければと思います。
当事務所での遺言料金表
| 公正証書 | 自筆証書 法務局保管 | |
|---|---|---|
| 実費 (公証役場・法務局) | 50,000円~80,000円 | 3,900円 |
| 証人費用 | 0円 (手配無料) | 0円 |
| 報酬 (司法書士) | 66,000円 (税込) | 66,000円 (税込) |
| 合計 | 110,000円~140,000円 | 69,900円 |
※他に各種証明書(戸籍等)の取得実費が数百円〜数千円かかります。
【注】 上記の料金は、20~50代のLGBTの方限定の低料金サービスでの金額になります。
当事務所のLGBTの方向け法律文書作成サービスについては、下記がメインページになりますので、ご覧いただければ幸いです。
手間:公正証書は資料集めが少し面倒
【比較表】手間
| 公正証書 | 自筆証書 法務局保管 | |
|---|---|---|
| 資料提出 | 沢山あり | 住民票のみ |
| 手書き | 不要 | 必要 |
| 出頭 (公証役場・法務局) | 原則必要※ | 必要 |
公正証書遺言の手間
公正証書遺言の場合は、遺贈する財産の金額が分かる資料を提出する必要があります。
例えば、不動産の課税明細書ないし固定資産評価証明書や、有価証券の取引報告書などです。
また、財産の承継先を特定する資料も必要になります。
例えば、遺産の一部を法定相続人に承継させる場合には、その法定相続人と遺言者との続柄が分かる戸籍謄本が必要になります。受遺者が親族以外の場合には、受遺者の住所が分かる資料(住民票、受遺者に届いた手紙等)も必要です。
遺言書の文案をメール等で公証人と詰めた場合でも、最後に本人が公証役場に出向いて公証人と面談をする必要があります(ただし、出張費を払えば自宅や入院先の病院まで出張してくれます)。面談の所要時間は30分前後です。
自筆証書遺言の手間
保管制度利用の手間
士業事務所に依頼した場合の手間
士業事務所に作成補助を依頼すると、上記の手間をかなり軽減させることができます。
公正証書遺言の場合、公証人との事前の打ち合わせは全て代行してくれます。また、必要書類の面でも、その大部分を代わりに収集してくれます。
最小限の手間で、公的な公証人と民間の士業事務所の、法律専門職同士が話し合った上での最適解を示してくれます。
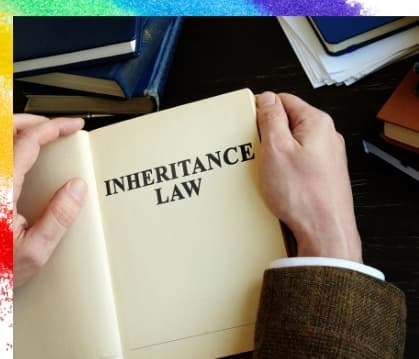
まとめ
遺言内容の実現には公正証書遺言が一番安全ですが、一般的なケースで実費が6~7万円程度かかることと、必要書類収集に若干手間がかかります。
ミドル世代の方などは、自筆証書遺言も検討に値する選択肢といえます。その場合は法務局に保管しましょう。実費は3,900円のみですし、提出書類も住民票のみで簡便です。
保管部署の担当官は内容をチェックできないので、弁護士や司法書士に作成のサポートを依頼されることをお勧めします。
そして最後にお伝えしたいのは、どんな形でも遺言書を全く作らないよりはベターだということです。
同性カップルの方や事実婚の方は、法定相続やパートナーシップ登録(宣誓)などの制度では死後に大事な人を経済的に守れませんので、高齢でなくても遺言書作成は大変重要です。
今回の記事が皆様の遺言書着手の一助になれば幸いです。
本サービスの担当・執筆者

長野 正義(ながの まさよし)
保有資格
- 司法書士(東京司法書士会所属/登録番号:第8353号)
- 個人情報保護士
- 知的財産管理技能士(二級)
経歴等
昭和57年 東京都文京区 生まれ
平成16年 中央大学 法学部法律学科 卒業
平成22年 司法書士試験 合格
平成23年 簡易裁判所の訴訟代理権試験 合格
一般企業の法務部、大手の司法書士法人等を経て、現職。
メッセージ
裁判所への書類や企業間契約書など、法律文書の作成を専門として15年程の実務経験があります。定型文中心の行政申請業務が主流の司法書士業界では珍しい経歴かもしれません。
現在は特に、同性カップルの法的課題に対する支援に注力しており、遺言書や医療同意委任契約など、法的効力や実務上の実効性を重視したサポートを行っています。
「一人の人生の大事な局面に関わる責任」を重く受け止め、依頼者の思いに応える成果を提供できるよう、今後も研鑽を続けて参ります。
好きな言葉
・至誠一貫 ・第一義
趣味
・茶道(裏千家/許状:行之行台子)