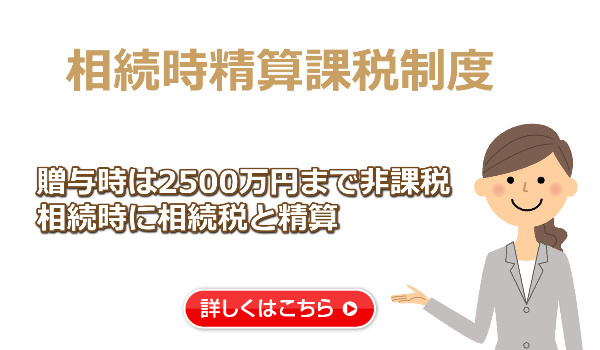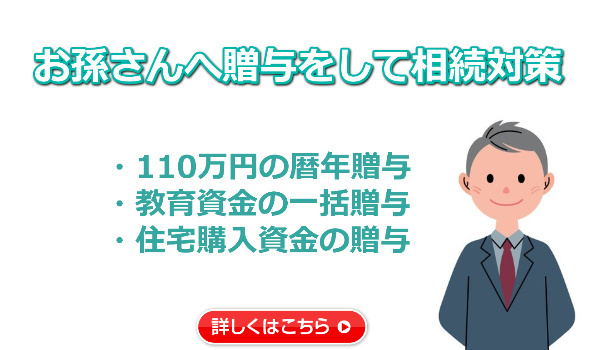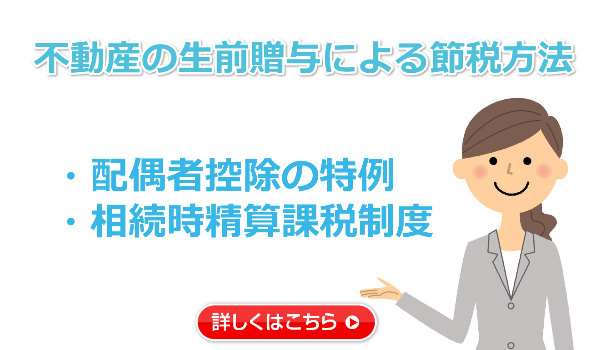相続・遺言に関する手続の総合案内(合同会社つなぐ(FP)×司法書士法人黒川事務所×行政書士黒川事務所の運営サイト)
生前贈与を活用した相続税対策5選
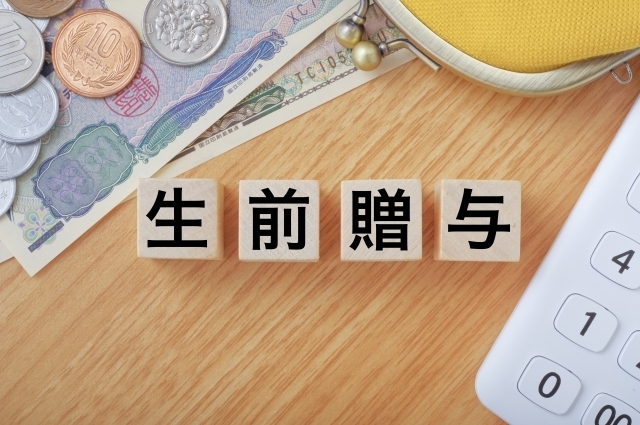
相続税対策には生前贈与が有効です。
贈与税にはさまざまな控除の制度がもうけられているので、上手に使って生前贈与しておくと遺産が減り、相続税を節税できます。
今回はFPの資格を持つ司法書士が生前贈与を利用した効果的な相続税対策方法をお伝えします。
贈与税控除制度については、状況に応じて適切な方法を選択する必要がありますので、関心がありましたらお気軽にご相談ください。
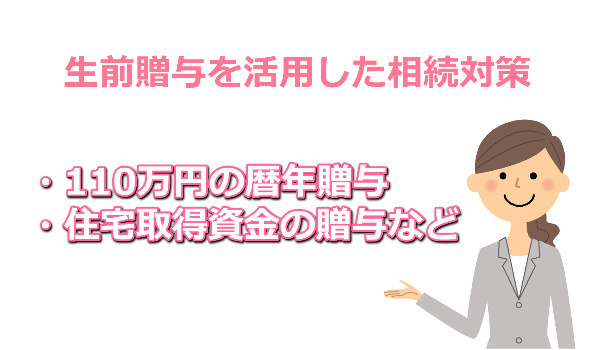
相続税対策で利用できる贈与税の控除制度一覧
相続税対策として利用しやすい贈与税の控除制度には、以下のようなものがあります。
1.暦年贈与
暦年贈与は、贈与税の「基礎控除枠」を利用した節税方法です。
贈与税には年間110万円までの基礎控除枠があり、1人に対し毎年110万円以下の贈与であれば贈与税がかかりません。贈与財産は何であってもかまいません。
預金や株式、不動産などを贈与できます。
年間110万円は「受贈者」についてカウントされるので、数人に110万円ずつ贈与するなら贈与税は発生しません。
これを利用して、毎年110万円ずつ贈与し続けるのが暦年贈与です。
たとえば3人の子どもと2人の孫へ毎年110万円ずつ贈与すると、毎年合計550万円ずつ無税で受け継がせることが可能となります。
暦年贈与の注意点
暦年贈与する際には、以下の点に注意が必要です。
「連年贈与とみなされるリスク」
暦年贈与するには「毎年1回」贈与契約を締結し、その都度贈与しなければなりません。
そうではなく当初にまとまった贈与契約を締結し、その後毎年110万円ずつ支払うと「当初に合計金額の贈与契約を締結し、その後分割払いしている」とみなされて110万円を超える部分に贈与税がかかる可能性があります。
このように「単なる分割払いの贈与」を「定期贈与」「連年贈与」といいます。
連年贈与とみなされないように、贈与契約書は毎年作成しましょう。
「相続発生7年前までの生前贈与を相続財産に加算」
以前は、相続人が取得した「相続発生3年前までの生前贈与を相続財産に加算する」ルールでした。
それが改正されて「7年前」まで相続財産に加算されることになりました。
ただし、相続発生4年前~7年前の贈与については贈与額の合計から100万円を控除できる。
これにより高齢の方の駆け込みでの贈与に影響が出ます。
2.教育資金の一括贈与
親や祖父母が子どもや孫へ教育資金を一括で贈与する場合、最大1,500万円までが非課税となります。
贈与されたお金は入学金、毎年の学費などだけではなく、塾代やスポーツ教室などの費用に使ってもかまいません(塾代などの場合、控除額は500万円が限度です)。これを教育資金の一括贈与の特例といいます。
教育資金として控除対象になる費用の例
- 各種学校の入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、入学・入園試験の検定料
- 学用品の購入費、修学旅行費や学校給食費
- 塾や水泳教室などの費用、月謝、施設使用料など
- 英会話スクール、幼児教室などの費用
- 水泳教室、野球やサッカークラブ、ピアノ、絵画、書道教室などの費用
- 習い事をするために必要な道具の購入費用
- 通学定期券代、留学のための渡航費
教育資金一括贈与を利用する際には、受贈者である子どもや孫名義の信託銀行口座を作成し、そこへ贈与金を入金する必要があります。
教育資金一括贈与の注意点
3.結婚子育て資金の一括贈与
親や祖父母が子どもや孫へ結婚子育て資金を贈与すると、最大1,000万円までの控除を受けられます。これを結婚子育て資金の一括贈与特例といいます。
結婚資金については300万円、子育て資金については1000万円が限度です。
結婚子育て費用の例
結婚資金の例
- 挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用(ただし婚姻日の1年前以後に支払われるもの)
- 家賃や敷金等の新居費用、転居費用
子育て費用の例
- 不妊治療・妊婦健診に要する費用
- 分べん費、産後ケアに要する費用
- 子どもの医療費、幼稚園・保育所等の保育料、ベビーシッター代
結婚子育て資金の一括贈与を利用する際にも受贈者名義の信託銀行口座を作り、そこへ贈与金を振り込む必要があります。
結婚子育て資金贈与の注意点
4.住宅取得資金贈与の特例
親や祖父母が20歳以上の子どもや孫へ住宅取得資金を贈与する場合、一定金額が控除されます。
具体的な控除額は住宅の性能によって異なります。
省エネや耐震性のある性能の高い住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円が限度です。
なお住宅(土地、建物、マンションなど)の取得資金であれば、「購入」する場合も「新築」費用であってもかまいません。
住宅取得資金贈与特例の注意点
5.配偶者への居住用不動産贈与
20年以上連れ添った夫婦間で居住用不動産を贈与する際には、贈与税の配偶者控除が適用されます。具体的には2,000万円までの贈与額を控除してもらえます。
配偶者控除の場合、不動産そのものだけではなく新たな住宅の購入費用や建築費用の贈与にも適用できます。
相続税対策だけではなく死後の配偶者の住居確保にも役立つので、状況に応じて利用しましょう。
相続税対策で生前贈与する際の注意点
相続税対策で生前贈与する場合、以下の点にご注意ください。
今後は死亡前7年間の贈与には相続税がかかる
生前贈与すると基本的には「贈与税」の課税対象となるので、贈与税の控除や軽減制度を適用すると税額を減らしやすくなります。
しかし死亡前7年間の贈与には「相続税」が課税されてしまいます(相続発生4年前~7年前の贈与については贈与額の合計から100万円を控除できる)。
贈与を行うなら、贈与者が元気なうちに行っておくべきといえるでしょう。
税制改正や期限に要注意
贈与税を含め、税制は毎年改正されます。
贈与税の控除制度を適用して相続税を節税したいなら、税制改正の動きを把握して「そのときに有効な制度」を活用する必要があります。
相続税の節税制度にはさまざまなものがあり、それぞれ適用できる要件や控除額も異なります。頻繁に税制改正されるので、自分たちだけで調べきるのは難しいでしょう。
黒川事務所ではFPの資格を持った司法書士が、お金のお悩みについても専門的な知識をもって対応しております。生前贈与だけではなく保険を使った有効な相続対策のスキームもご紹介できます。
相続税対策や不動産の相続、遺産分割など相続関係の不安やご要望がありましたら、ぜひとも一度ご相談ください。
監修者:黒川聡史

保有資格と所属団体
- 司法書士:東京司法書士会所属:登録番号4230号
- 行政書士:東京都行政書士会所属:登録番号第19082582号
- FP(FP技能士1級:日本FP協会CFP®)
経歴
昭和51年生まれ。平成13年司法書士と行政書士の資格取得後、都内司法書士事務所で勤務。平成19年に独立開業し、平成30年に法人化し司法書士法人黒川事務所となる。また、ファイナンシャルプランニング技能士1級及びCFP®を取得しFPとしても活動している(合同会社つなぐ)。