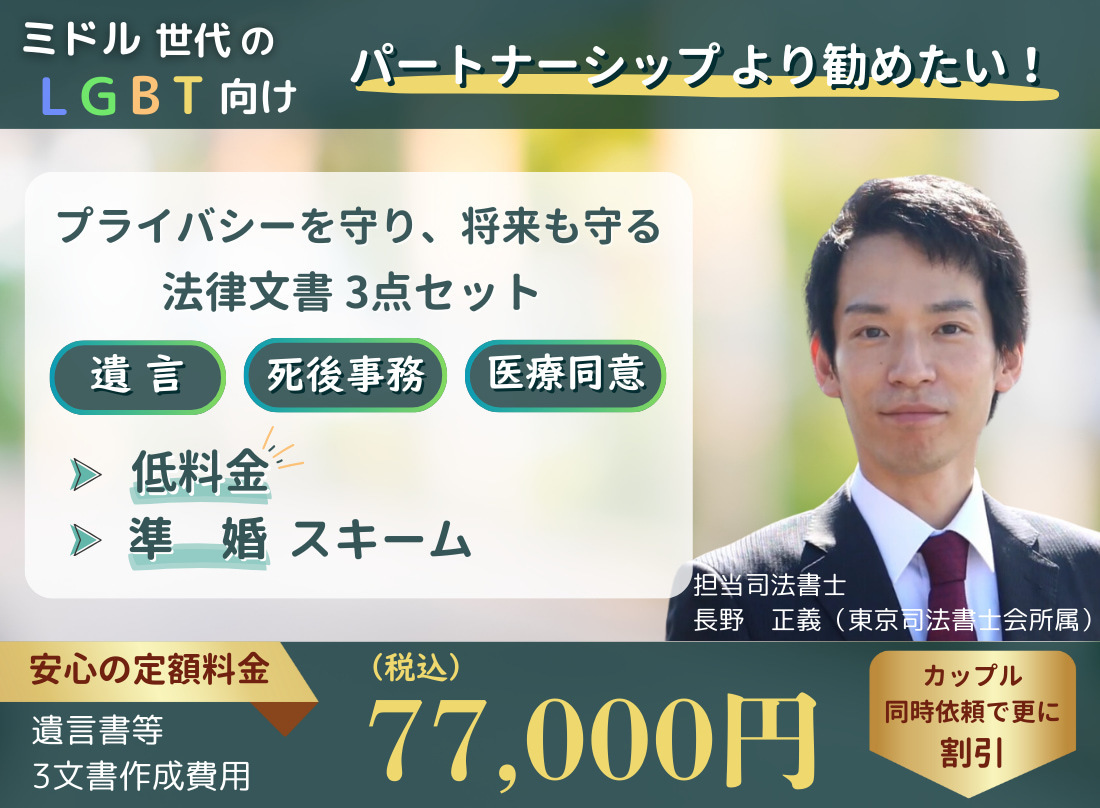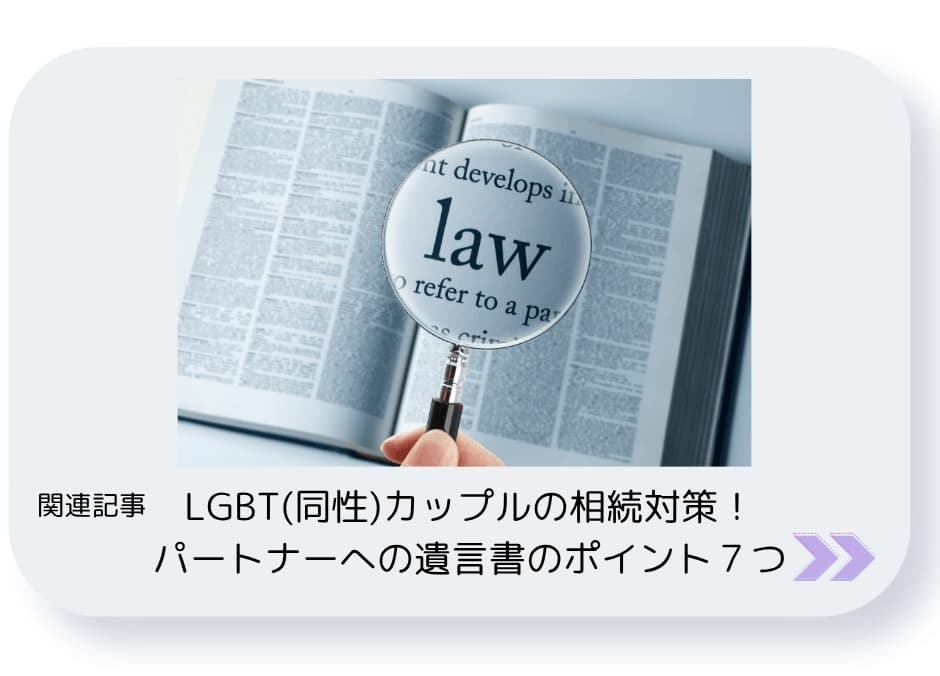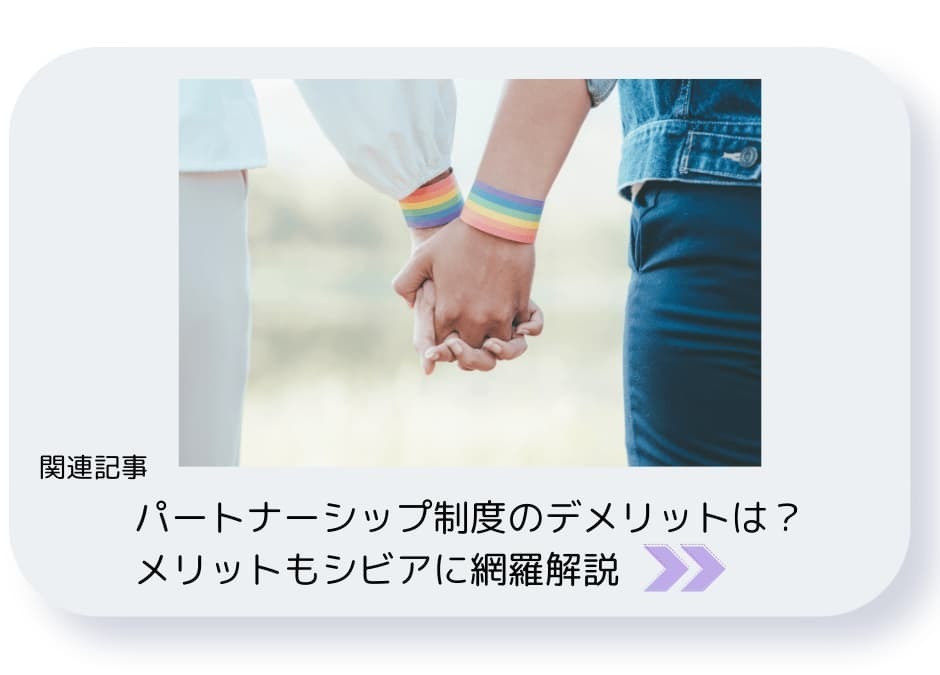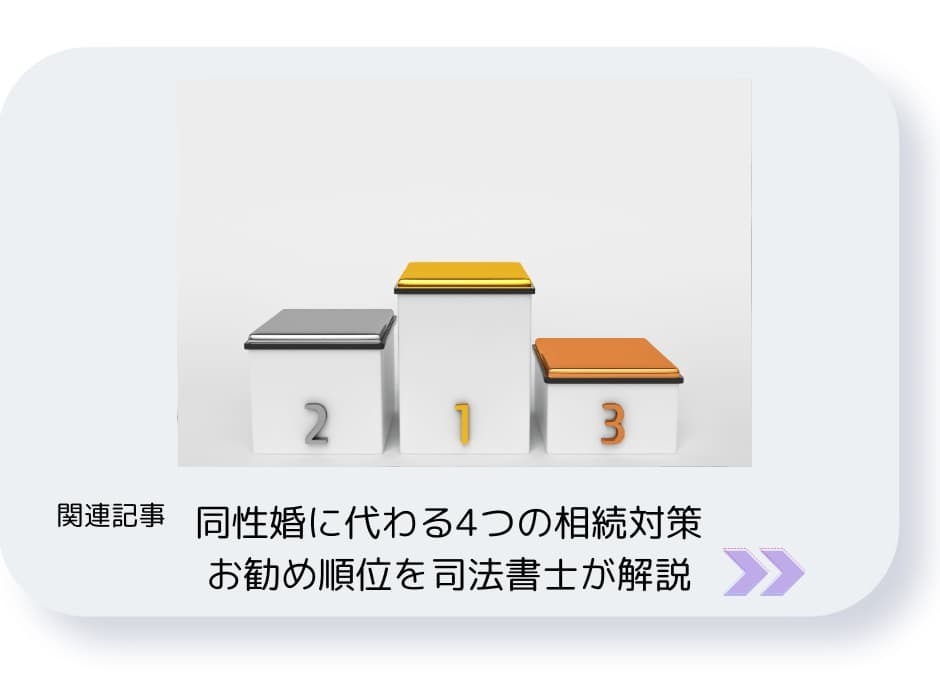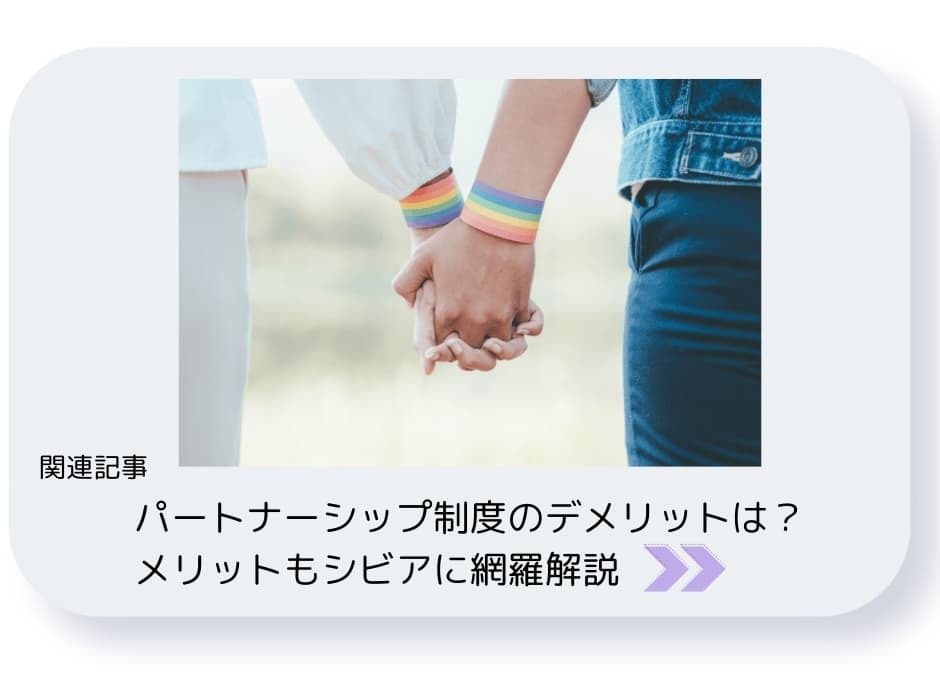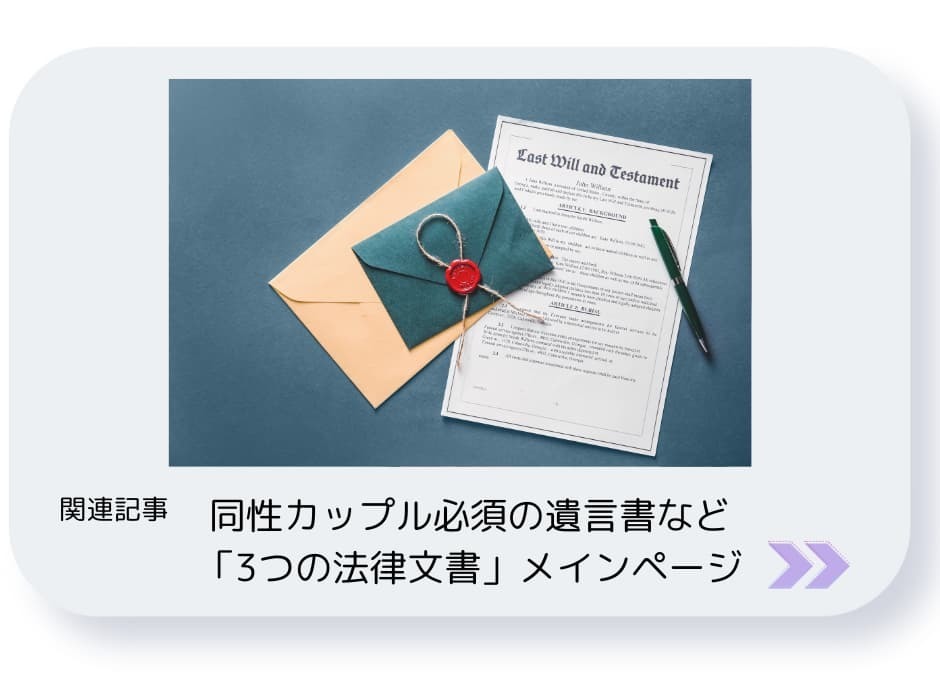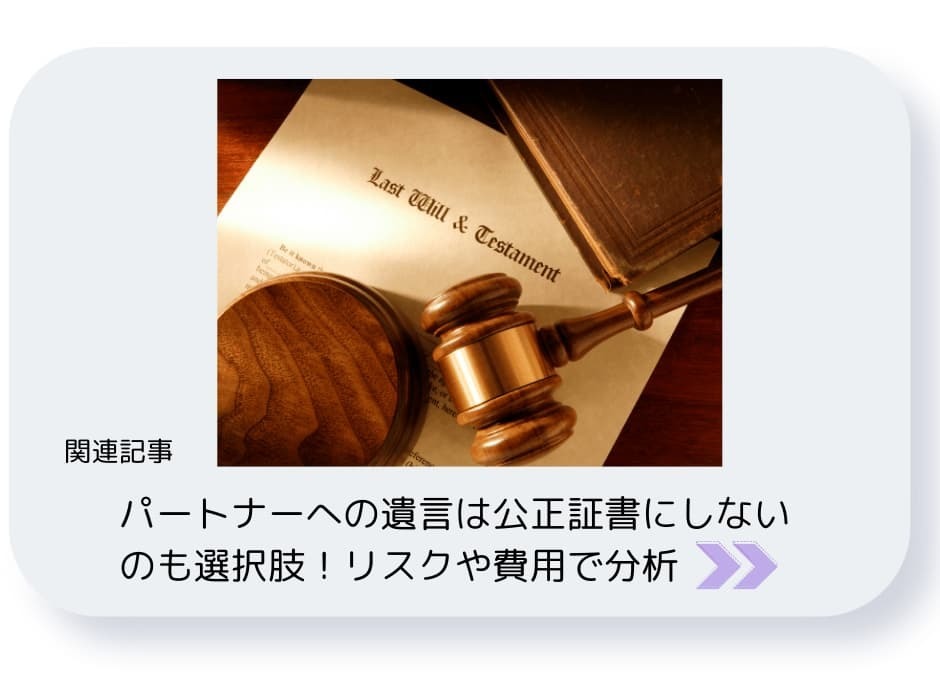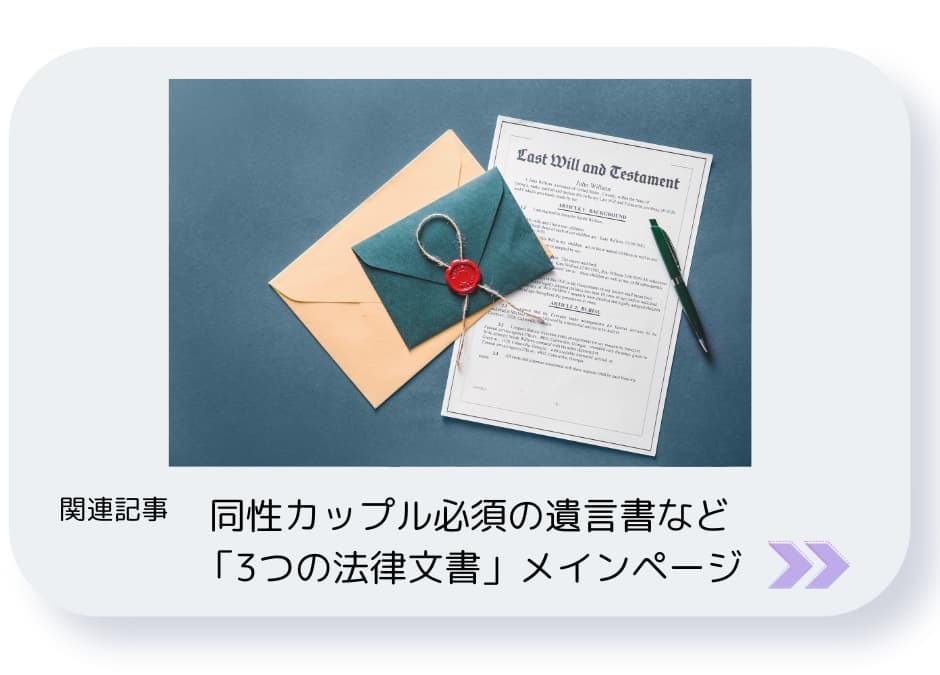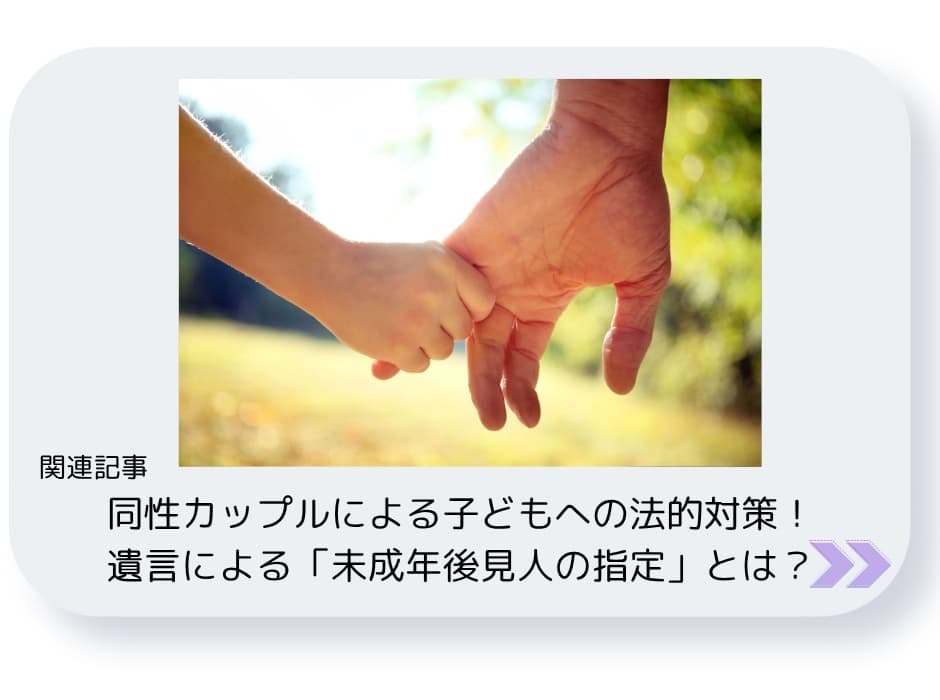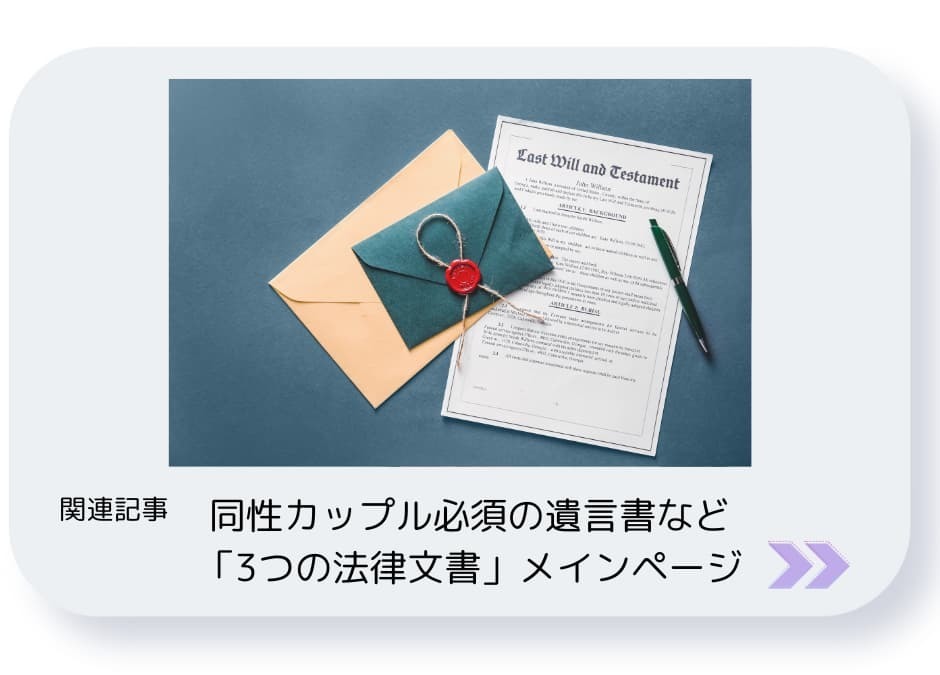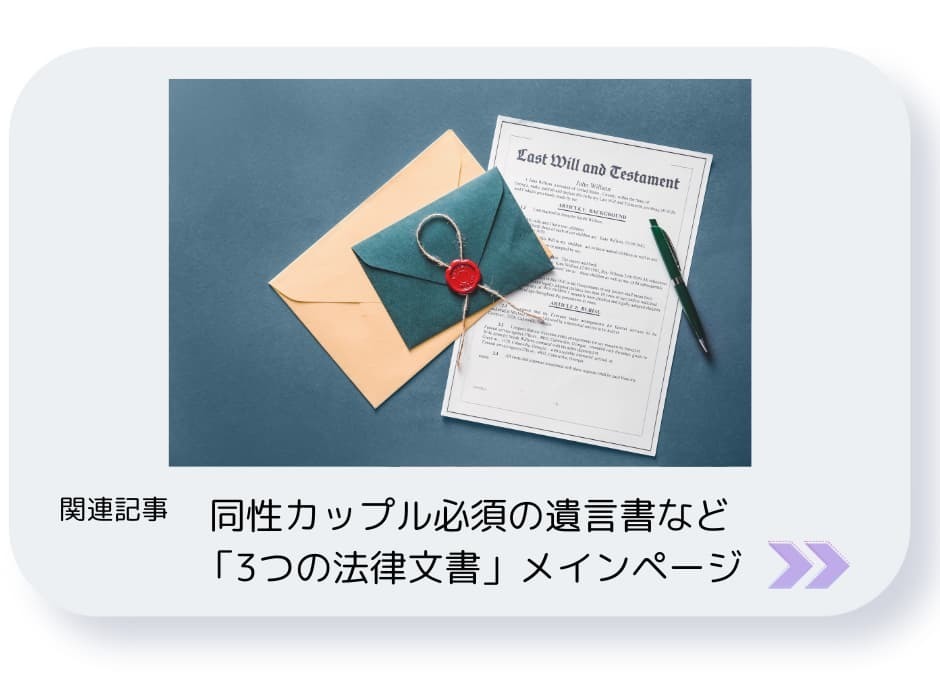相続・遺言に関する手続の総合案内(合同会社つなぐ(FP)×司法書士法人黒川事務所×行政書士黒川事務所の運営サイト)
同性カップルの養子縁組のメリットデメリットは?パートナーシップや遺言とも比較!
最終更新日:2025年7月26日
「子どものいるレズビアンのカップルが養子縁組をしたという話を聞いたけど、パートナーシップと何が違うんだろう」
レズビアンやゲイなど同性カップルの方にとって、養子縁組は結婚に近い法的効力を生じさせる有力な選択肢といえます。
他方で、最近はパートナーシップ制度も注目を集めていますし、同性カップルの方に特にお勧めな相続対策である遺言書などの別の選択肢も存在します。
今回は、養子縁組のメリットとデメリットについて、パートナーシップ制度、遺言書との比較を交えながら詳しく解説していきたいと思います。
同性婚が認められない現在の日本において、同性カップルの方がお二人の幸せのために最適な選択肢を選ぶ一助となれば幸いです。

養子縁組とは?同性カップルも利用可能?
養子縁組の意義
同性カップルの養子縁組の可否
同性カップルの方も利用することが可能です。
実際に、同性婚が認められない日本において、結婚類似の強い効力を生じさせることができる代替手段として、これまでよく活用されてきました。
(ただし、その有効性に若干の疑義があることには注意が必要です。この点は、養子縁組のデメリットの箇所(養子縁組は無効のリスクがある)で解説します。)
養子縁組の要件・手続・費用
同性カップルの双方が20歳以上であり、認知症を患っていなければ、住所地か本籍地の市役所への届け出のみで可能です(裁判所での手続等は不要です)。
縁組届には証人2名の署名が必要ですが、証人は成人であれば誰でもよく、親族である必要はありません。
縁組届の書式は以下のようなものになります。
費用はかかりません。令和6年3月1日以降に届け出をする場合は、添付書類として戸籍謄本を提出する必要も原則なくなりましたので、その面でも費用はかかりません。
他の選択肢(パートナーシップ制度・遺言書)の意義
パートナーシップ制度の意義
パートナーシップ制度は、自治体(市区町村役場)においてパートナーとしての登録や宣誓を行うことで、法律上の夫婦と同等の関係にあることを役所が認める制度です。
国の法律に基づく制度ではないので、導入していない自治体もありますが、現在では日本全国多くの自治体が導入しています。
あくまで法的な効力はありませんが、住宅ローンのペアローンや公営住宅への共同入居など、夫婦同様のサービスを受けやすくなるというメリットがあります。
養子縁組のメリット
養子縁組の遺産相続でのメリット
養親子は相続人になれる
相続制度において、養子は実子(血の繋がった子ども)と全く同様に取り扱われます。そのため、養子縁組をすれば、ほとんどのケースでカップルが相互に遺産の法定相続人になることができます。
例外的に相続人になれないケース
養子となったパートナーが亡くなった場合に、そのパートナーに子ども(養親から見れば孫)がいるときだけは、養親は相続人になることができません。民法が定める相続順位において、養親は養子の子どもに劣後するためです(民法889条・887条)。
このケースでは、養子縁組と併せて遺言書の活用も積極的に検討しましょう。
養親子は相続税も減税
遺産の総額が3000万円以上の場合は、相続税が課される可能性があります。
養子縁組であれば、下記のとおり相続税について親子間に適用される多くの減税措置を受けることができます。
養子縁組による節税一覧表
| 制度名 | 制度の概要 | 養子縁組による節税効果 |
|---|---|---|
| 相続税の基礎控除 | 遺産が「3000万+(600万×法定相続人の数)」までは課税されない | 縁組により法定相続人の数が増えて基礎控除が増額することがある |
| 小規模宅地の特例 | 相続税の計算で、宅地の評価額を最大80%減額できる。遺産の大部分は土地が占めることが多いため減税効果大 | 縁組をした同性カップルがその持ち家(マンション含む)で同居している場合、多くのケースでこの特例を受けられる |
| 相続税の2割加算 | 「親子と配偶者」以外に課される相続税は2割増額される | 縁組により親子となるためこの増税を回避可能 |
| 不動産登録免許税 | 遺産承継に伴う登記申請(不動産の名義変更)での法務局手数料が、本来は不動産評価額の20/1000かかる | 縁組により相続人への登記となり、不動産評価額の4/1000という低率で済む |
| 生命保険非課税枠 | 受取人が相続人の場合、生命保険金に課される相続税の非課税枠(法定相続人の数×500万)が適用される | 縁組により相続人になるため非課税枠の適用可能 |

遺言書との比較:相続(遺贈)
遺言書は、意義の箇所で解説したように、養子縁組よりも柔軟に、本人の意思で遺産を誰にでも自由な分量で承継させることが可能です。
ただし、遺言書にも限界はあり、一部の親族は遺留分という制度で守られています。
遺留分とは、分かりやすく言うと「一部の法定相続人に最低限認められた、遺産の一部請求権」のことであり、遺言書でも奪うことはできません。
例えば、遺言書で「パートナーに全財産を遺贈する」と書いておいても、一部の親族はパートナーに遺留分の請求をすることで、最大で遺産の評価総額の半分に相当する金銭を取り立てることができてしまいます。
遺留分の詳細については、下記の記事で詳しく解説しているので、よければ参考にされてください。
パートナーシップ制度との比較:相続
養子縁組の苗字へのメリット
養子縁組は苗字も戸籍も同じになる
養子縁組をすると、カップルのうち先に生まれた方が養親になります。
年長者を養子にすることは民法で禁止されているため(民法793条)、どちらが親になるかを選ぶことはできません。
その結果、年少のパートナーは、養親の苗字に変更になり、養親の戸籍に子どもとして入ることになります。
養子縁組は結婚と類似点も多いですが、結婚はどちらの苗字を名乗るか→どちらの戸籍に入るかを自由に選ぶことができるので、この面では異なります。
とはいえ、入籍して同じ苗字を名乗れるのは、結婚に近い幸福感の源泉になりうるでしょう。
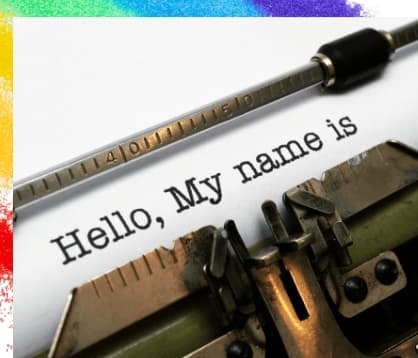
パートナーシップ制度との比較:苗字
養子縁組の住民票続柄へのメリット
養子縁組は続柄も変わる
養子縁組の場合は、法的に親子になるので、住民票の続柄についても「父」「母」ないし「子」と表記されます。
パートナーシップ制度との比較:住民票続柄
パートナーシップ制度に登録すると、一部の自治体では世帯主との続柄を「妻(未届)」又は「夫(未届)」と表記することが可能になります。
この表記は男女の事実婚における表記と同一のものです。
このような取組みを開始した自治体はまだ少数ですが、最近になって東京都世田谷区や中野区でも表記可能になるなど、徐々に広がりを見せています。
>>世田谷区公式サイト「パートナーシップ宣誓等を行った方の住民票の続柄変更に関する手続」
ご興味があれば、お住まいの自治体に表記可能か確認してみましょう。
養子縁組の扶養面へのメリット
養子縁組は扶養認定が可能になる
養子縁組の場合、同性カップルは法的には親子になりますので、どちらかの収入がかなり低いときは、所得税や住民税の扶養減税を受けたり、社会保険の扶養に入ることが可能になります。
パートナーシップ制度との比較:扶養面
養子縁組の各種サービスへのメリット
養子縁組は親子として各種サービスを受けられる
養子縁組をすれば親子になれますので、当然に民間企業や行政機関において家族としてのサービスを受けることが可能になります。
一例としては生命保険が挙げられます。一部の保険会社では生命保険の受取人は親族に限定されていますが、養子縁組をすればパートナーも親族になるので受取人に指定することが可能になります。
その他、住宅ローンの親子リレーローンやクレジットカードの家族カード、携帯電話の家族割なども利用可能になります。
パートナーシップ制度との比較:各種サービス面
パートナーシップ制度においても、そもそもこの制度が「夫婦間に提供される各種サービスを同性カップルも受けやすくする」という目的のものですので、民間ないし行政上のサービスを受けやすくなります。
例えば、パートナーへの生命保険の契約や、住宅のペアローン、公営住宅での共同入居などが可能ないし容易になることがあります。
パートナーシップ制度により利用可能なサービスについては、以下の記事で詳しく解説しているので、よければご覧ください。
養子縁組のデメリット
養子縁組の遺産相続でのデメリット
遺産分割協議が必要になるリスク
上記で解説したように相続上のメリットが大きい養子縁組ですが、その反面で同性カップルが養子縁組をする場合にはリスクも存在します。それは、他に法定相続人がいる場合です。
比較的多いケースとしては、養子が養親より先に亡くなった場合に、その養子の実親(血の繋がったお父様かお母様)がご健在のケースです。
養子縁組をしても、実親との法的な親子関係は継続します。そのため、養親と実親の両方が相続人となってしまいます。

このような共同相続の場合、「遺産分割協議」が必要になりますが、これが厄介です。
遺産分割協議とは、相続財産のうち、誰がどの財産を具体的に相続するかを決める話し合いです。例えば、相続人aが不動産を、相続人bが金融資産を、という具合で決めていきます。
この協議は相続人全員で行う必要がありますので、養親となったパートナーは養子の実親と、全部の遺産を相続できないという面で対立する中で話し合いをしなければならなくなってしまいます。
本来は遺産全部を相続できたはずのご両親との話合いですから、ご両親とパートナーとの面識が乏しい場合には、協議が紛糾するのは想像に難しくないでしょう。

遺産分割協議を避けるためには、養子縁組をした同性カップルも遺言書を書くことが有効です。
遺言書で養親に遺産の全部を与える旨(全部包括遺贈)を定めておけば、遺産分割協議は不要になります。
さらに、養子縁組と遺言書を組み合わせると、詳細は割愛しますが、遺言書でも奪えないご両親の遺留分を減らすこともできます。
養子縁組と遺言書を組み合わせる手法は、生前贈与以外では、現行法で一番多くの財産を同性パートナーに承継させることができる相続対策と言えるでしょう。
養子縁組の配偶者的効力でのデメリット
養子縁組に配偶者としての権利義務はない
養子縁組はあくまで法的に親子関係を築くものですので、配偶者としての法的保護を受けることはできません。
例えば、「貞操義務(浮気をしない義務)」はありません。そのため、万一浮気をされてしまっても、パートナーやその浮気相手に慰謝料を請求することはできません。
また、「財産分与」の権利もありません。結婚した夫婦が離婚する場合であれば、結婚中に築いた財産の原則半分の分与を請求できるので、その差は大きいですね。
同性カップルの貞操義務や財産分与については、下記の記事のデメリットの箇所で詳しく解説していますので、よければご覧ください。
養子縁組の同性婚へのデメリット
養子縁組は将来の同性婚が危ぶまれる
人によっては「今は同性パートナーと養子縁組をしておいて、もし将来的に同性婚を認める法改正がされたら、離縁(養子縁組の解消)をして結婚しよう」と考えている方もおられるかもしれませんが、その考え方は危険です。
なぜなら、離縁をした後であっても、過去に養親と養子の関係にあった者同士での結婚は、民法で禁止されているためです(民法736条)。
この民法の禁止規定は、親子秩序の維持が目的とされています。結婚観については近年大きく変動していることは間違いないと思いますが、親子観の変動はより緩やかでしょうから、同性婚の法改正と併せてこの禁止規定も変更されるかは不透明です。

そのため特に若いカップルの場合は、遺言書やパートナーシップ制度など他の制度で備えるにとどめて、養子縁組は急がない方がお勧めです。
同性カップルが将来のリスクなく採れる「法律婚に代わる実効的な備え」として、当事務所では遺言書など「3つの法律文書」をお勧めしていますので、詳しくは下記のページもご覧いただければ幸いです。
なお、養子縁組をしているとパートナーシップ制度についても、自治体によっては養親子を含めて近い親族間での利用を禁止しているため、利用できなくなる可能性があります。
養親子間でのパートナーシップ登録の可否
例えば、パートナーシップ制度を牽引する下記の自治体でも、以下のように可否が分かれています(2025年7月現在)。
▶ 渋谷区(登録不可)
パートナーシップ証明を申請できる人として「近親者でないこと」があり、ここでいう近親者には「養親子等の間」も含まれるものとされているため、同性パートナー間の縁組による親子は登録することができません。
>>渋谷区公式サイト「渋谷区パートナーシップ証明発行の手引き」
▶ 東京都(登録可)
対象者の要件として「直系血族(親子など)の関係にないこと」はありますが、パートナー関係に基づく養子縁組の場合は除外される旨が明示されており、パートナー間の縁組による親子は登録可能とされています。
上記の同性婚へのデメリットを回避する方法として、別の養子縁組の形態(兄弟姉妹型)も存在します。しかし、利用しづらい方法になりますので、詳しくは記事末尾のQ&Aで解説します。
養子縁組の有効性の面でのデメリット
養子縁組は無効のリスクがある
養子縁組は、本来は親子関係を築くのが目的ですので、同性カップルが夫婦同等の関係を築く意思で行なった縁組は無効になるリスクがあります。
特に遺産が多額の場合、養親子に財産を奪われた親族が無効を主張してくる可能性があり、実際に裁判で争われた事例も存在します。
過去の裁判例では以下のように判示して、同性カップルの縁組を有効と認めたものが存在します。
東京高等裁判所判決 平成31年4月10日
養子縁組の扶養や相続等に係る法的効果や、同居して生活するとか、精神的に支え合うとかなどといった社会的な効果の中核的な部分を享受しようとして養子縁組をする場合については、取りも直さず、養子縁組の法的効果や社会的な効果を享受しようとしているといえるのであるから (中略)
同性愛関係を継続したいという動機・目的が併存しているからといって、縁組意思を否定するのは相当ではない
しかし、この判決はあくまで、その裁判の対象になった同性カップルの細々とした背景事情を汲み取って下されたものなので、同性カップルの養子縁組を全て有効と認めたものではないことには注意が必要です。
特に、上記の裁判例は性交渉を継続していないカップルの事例という特徴があり、性交渉を継続中の場合には養子縁組の成立について否定的な見解の判例も存在します(最判昭和46年10月22日)。
そのためパートナーの親族と疎遠の場合は、今後も縁組の有効性が争われて訴えられるリスクについて、一定の覚悟はしておかなければなりません。
養子縁組の秘密保持の面でのデメリット
養子縁組はカミングアウト前提
性的指向という繊細な個人情報について、なるべく秘密を守った上で法的対策を講じておきたいと考える方も少なくないと思います。
この点、養子縁組は、名前も戸籍も変わるので、完全にオープンな方向きと言えるかと思います。
パートナーシップ制度との比較:秘密保持の面
パートナーシップ制度は、基本的に公表や第三者の閲覧を前提とした制度ではなく、公務員には秘密保持義務があるため、制度登録それ自体で親族等にバレるリスクは低くなります。
しかし、パートナーシップ制度の目的は、民間や行政において夫婦同様の各種サービスを受けることにあり、そのためには各サービスの窓口に登録証の提示が必要になるので、パートナーシップ制度を活用すればするほど秘密保持にも限界が出てくるといえるでしょう。
遺言書との比較:秘密保持の面
遺言書であれば秘密を守った上で相続対策が可能です。
遺言書の作成を誰にも伝えていない場合、その存在が埋もれて遺産分割をされてしまうリスクも存在しますが、法務局保管制度や公正証書遺言を用いれば、そのリスクも減らすことが可能です。
法務局保管制度や公正証書については下記の記事で詳しく紹介しているので、よければご覧ください。
養子縁組と親権・子育て
養子縁組は親権者が養親だけになってしまう
遺言書で未成年後見人を指定できる
養子縁組のよくあるQ&A
-この章の目次-
6-2.在留資格で養子縁組は有効ですか?
病院での看護で養子縁組は有効ですか?
有効です。法的に親となり、最も親等の近い親族となるので、医療の面会や手術等への同意について病院からの十分な協力を期待できます。
この点は、パートナーシップ制度においても公営病院等で一定の協力は期待できます。
以上の2つの制度を利用した場合でも、別に医療に関する契約を締結しておくことはなお有効ということができます。
医療に関する独立の医療同意委任契約を締結したり、パートナーシップ「契約」(準婚姻契約)の一条項として医療同意を規定しておきましょう。
病院は本人の意思を最優先に扱うため、これらの契約において自らの意思の代弁者としてパートナーを指定しておくことで、病院からのより一層の協力が期待できます。
医療同意委任契約については下記の記事で詳しく解説しているので、よければご覧ください。
在留資格で養子縁組は有効ですか?
同性婚を見据えた養子縁組の方法はありませんか?
同性カップル同士が養子縁組をする場合、上記のように将来的に同性婚ができなくなるリスクがあります。
そのようなリスクを回避するために、同性カップル(AさんとBさん)の一方(Aさん)が他方の親(Bさんの親)と養子縁組をするという方法も一応存在します(この方法を「兄弟姉妹型」と呼ぶことにします)。
この場合、Bさんの親から見て、Bさんは実子、Aさんは養子であり、AさんとBさんは法的に兄弟姉妹という身分での親族になれます。
実子と養子との間での結婚は現行法でも禁止されていないので(民法734条但書)、将来的に同性婚が法制化された際にはAさんとBさんは結婚が可能です。
しかし、この方法の利用は、下記のデメリットや困難が伴います。
兄弟姉妹型の養子縁組の相続問題
亡くなった方の遺産をその兄弟姉妹が相続できるのは、亡くなった方に子供がおらず、直系尊属(両親や祖父母)の全員が既に亡くなっている場合に限られます(兄弟姉妹は第3順位の法定相続人であるため)。
つまり、兄弟姉妹型の養子縁組では、同性カップルの一方が亡くなった場合、その親(養親も実親も含みます)がご健在なら、同性カップルの他方は一切相続することはできません。
兄弟姉妹型の場合には、同性パートナーに遺産を承継させるという大変重要な目的が果たせなくなるリスクが少なくないことを理解する必要があります。
兄弟姉妹型の養子縁組の実現困難性
兄弟姉妹型の養子縁組の場合、養親となる予定の、同性カップルの一方の親の協力が当然必要になりますが、これは容易なことではありません。
例えば相続面に焦点を当てると、養子になるということは、養親の第一順位の法定相続人の一人になるということを意味します。
恋愛面では「貴方が好きになったのなら私は尊重する」と言ってくれる親であっても、自分が亡くなった際の直接の財産承継先となることまで認めてくれるとは限りません。
また、もしその親に別の実子(同性カップル以外の子供)がいる場合はさらに難易度が上がります。
というのもその実子は、養子という存在により、親が亡くなったときの相続分(遺産の分け前)が大きく減ることになるので、養子縁組に反対する可能性は相当程度に高いでしょう。
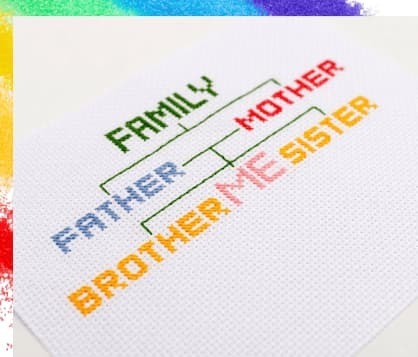
養子縁組を解消(離縁)する際の手続や注意点は?
パートナーとの関係が万一破綻してしまった場合は、速やかに養子縁組を解消することをお勧めします。そのままにしておくと、関係が切れていても、法的には親子のままとなり、お互いに相続権や扶養義務が残り続けてしまうためです。
相手が離縁に同意してくれている場合は、市区町村の役所に2人で離縁届を提出するだけで解消が可能です。しかし、相手が反対する場合には、家庭裁判所で調停や訴訟の手続を経なければなりません。
夫婦が別れるときに合意できないと、他の訴訟類型と比べて長期の裁判に発展することが少なくないように、養親子でも親族関係という強い法的関係を一度築いた以上、合意がないと解消するのは相当な苦労が伴います。
このように、養子縁組は解消時に法的トラブルに発展するリスクもあるため、縁組を検討する段階でこそ、二人で慎重に話し合うことが大切です。
養子縁組を解消するときは遺言書も変えるべきですか?
この記事の随所で解説しているように、養子縁組をしていても、併せて遺言書の用意もしておくことで万全の法的対策が可能になります。
しかし、それだけのつながりを築いたカップルでも、残念ながら関係が破綻してしまうことはあります。そうした場合には、離縁手続と併せて、遺言書の見直しも検討することをお勧めします。
遺言書には「撤回擬制」というものが民法で定められており、遺言内容に反するような一定の行為があれば遺言は自動的に効力を失います(民法1023条2項)。例えば、遺言書で誰かに与えると記載した財産を生前に別人に売却してしまうと、その遺言の部分は無効になります。
しかし、離婚や離縁など、配偶者や養子への遺言に至った前提の身分関係の解消がこの撤回擬制に当たるのかは黒に近いグレーです。古い判例ではこれを認めたものがありますが(最判昭56.11.13)、学説的には否定的な見解も有力です。
まとめ
養子縁組は、遺産相続や苗字の変更、扶養の認定という面で結婚類似の強い効力を生じさせることが可能です。
実際に一昔前にはよく利用されていました。
しかし、養子と養親が離縁後も結婚できないリスク等を考えると、特に若い同性カップルの方に養子縁組という手法はあまりお勧めできません。
昨今の同性婚訴訟の情勢からすれば、そう遠くない将来に同性婚が認められるか、そうでなくても同性婚類似の国家的制度が創設されることが現実味を帯びてきているためです。

他方で、遺言書は常に有意義な選択肢と言えます。
遺言書は同性婚が認められるか否かに関わらず、パートナーに遺産分割不要の財産承継を可能にさせるためには必須だからです。
また、各制度は単独ではなく組み合わせて用意しておくと、制度のすき間を埋めて同性婚に近づけることができるため、更に効果的といえます。
そのため当事務所では、養子縁組ではなく、秘密保持を重視される方には遺言書+医療同意委任契約+死後事務委任契約の「3つの法律文書」を、比較的オープンな方には遺言書+パートナーシップ制度の活用をお勧めしています。
本サービスの担当・執筆者

長野 正義(ながの まさよし)
保有資格
- 司法書士(東京司法書士会所属/登録番号:第8353号)
- 個人情報保護士
- 知的財産管理技能士(二級)
経歴等
昭和57年 東京都文京区 生まれ
平成16年 中央大学 法学部法律学科 卒業
平成22年 司法書士試験 合格
平成23年 簡易裁判所の訴訟代理権試験 合格
一般企業の法務部、大手の司法書士法人等を経て、現職。
メッセージ
裁判所への書類や企業間契約書など、法律文書の作成を専門として15年程の実務経験があります。定型文中心の行政申請業務が主流の司法書士業界では珍しい経歴かもしれません。
現在は特に、同性カップルの法的課題に対する支援に注力しており、遺言書や医療同意委任契約など、法的効力や実務上の実効性を重視したサポートを行っています。
「一人の人生の大事な局面に関わる責任」を重く受け止め、依頼者の思いに応える成果を提供できるよう、今後も研鑽を続けて参ります。
好きな言葉
・至誠一貫 ・第一義
趣味
茶道(裏千家/許状:行之行台子)