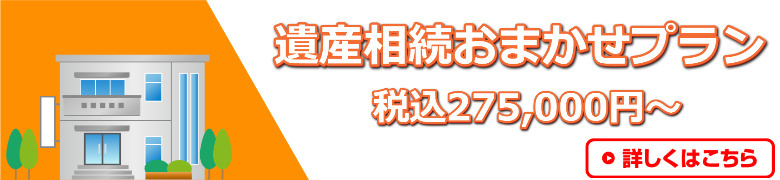相続・遺言に関する手続の総合案内(合同会社つなぐ(FP)×司法書士法人黒川事務所×行政書士黒川事務所の運営サイト)
銀行口座(預貯金)を相続した場合の手続きのご案内
ほとんどの方にとって必要となる相続手続きが預貯金の相続手続きです。
被相続人名義の預貯金は、被相続人が亡くなったことを金融機関が把握すると口座が凍結されます。
これは、一部の相続人により勝手に預貯金を引き出すことを防止するためです。
凍結を解除するためには、「誰が相続するか」を決めて、書類をそろえて銀行に提出する必要があります。
預貯金の相続手続きの必要書類

預貯金の相続手続きに必要な書類は下記のとおりです。窓口で手続きする方の身分証明書や被相続人の通帳やキャッシュカードもあれば準備しましょう。
- 金融機関所定の払い戻し請求書(金融機関備え付け)
- 被相続人の戸籍(除籍・改製原戸籍)の謄本(出生から死亡までつながるものが全て)
- 被相続人の預貯金通帳と届出印
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
次に、下記ケースでは下記書類が追加で必要となります
【遺産分割協議後のケース】
・遺産分割協議書(相続人全員の実印での押印)
【家庭裁判所による調停・審判をした後のケース】
・家庭裁判所の調停調書謄本又は審判書謄本(家庭裁判所から発行して貰えます)
【遺言書に基づいて行うケース】
・遺言書(自筆証書遺言なら検認済みのもの)
全部用意できなくても集められない書類は依頼した司法書士が可能な限り集めてくれますのでご安心ください
預金口座の相続手続きの流れ
相続した預金口座の解約手続きの流れをご説明いたします。
銀行など金融機関に問い合わせ
まずは、金融機関に相続が発生した(預金の名義人が亡くなった)ことを届け出ます。
届け出することにより口座が凍結されます(一部の相続人が勝手に引き出すことはできなくなります)。
金融機関からは、相続届など被相続人の口座を解約するための書類を貰います(郵送・窓口)。
また、残高証明書も発行してもらいましょう。
必要書類を金融機関に提出
被相続人の戸籍謄本一式や相続人の戸籍謄本・印鑑証明書など必要書類一式と相続届を金融機関に提出します。
相続届には相続人全員の署名押印が必要です。
相続人の口座に入金
金融機関にもよりますが、書類提出から1~3週間で入金されます。
代表者に一括して振り込んでもらう方法と相続人別に金額を指定して振り込んでもらう方法があります。
残高証明書・入出金明細の取得について
相続財産を調査するために過去の取引明細が必要な場合や、相続税の申告のため相続発生日時点での残高証明書が必要な場合の取得方法を紹介します。
これらの書類は上記の口座名義変更と異なり、相続人の1人からでも請求することが可能です。
【必勝な書類】
- 被相続人の戸籍の謄本
- 請求する相続人の戸籍謄本
- 請求する相続人の印鑑証明書
- 残高証明発行依頼書(各銀行の相続用の書式)
ネット系銀行の相続手続きも同じ
実店舗や通帳がないネット銀行の相続手続きも上記と同じです。
ただし、口座の発覚自体が難しいという特徴があります。
【ネット銀行を見つける方法】
- 他の銀行の預貯金通帳からネット銀行への振り込み履歴和がないか。
- 被相続人のメールをチェック。
- 主要なネット銀行へ連絡して確認する。
監修者:黒川聡史

保有資格と所属団体
- 司法書士:東京司法書士会所属:登録番号4230号
- 行政書士:東京都行政書士会所属:登録番号第19082582号
- FP(FP技能士1級:日本FP協会CFP®)
経歴
昭和51年生まれ。平成13年司法書士と行政書士の資格取得後、都内司法書士事務所で勤務。平成19年に独立開業し、平成30年に法人化し司法書士法人黒川事務所となる。また、ファイナンシャルプランニング技能士1級及びCFP®を取得しFPとしても活動している(合同会社つなぐ)。