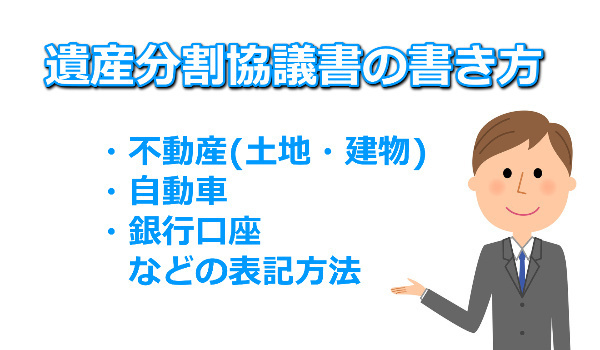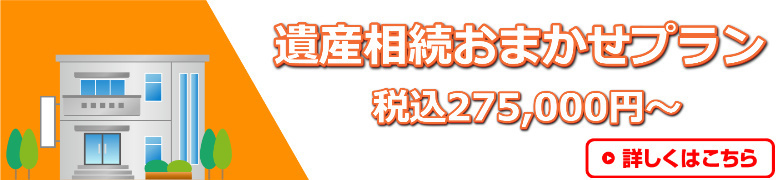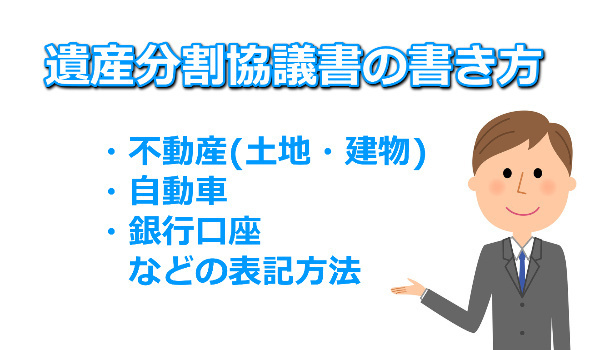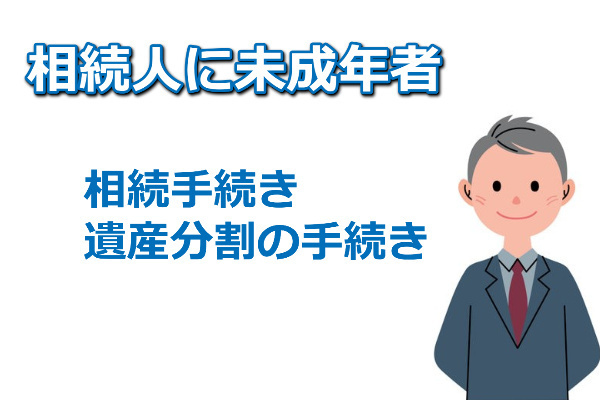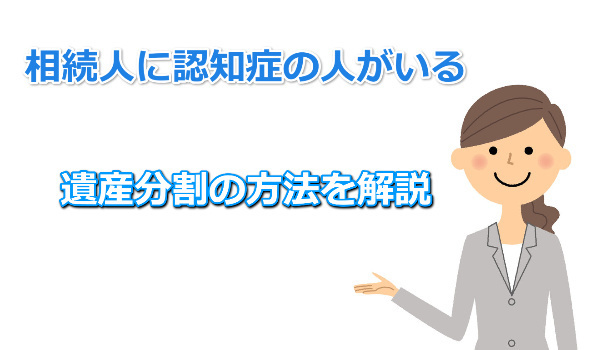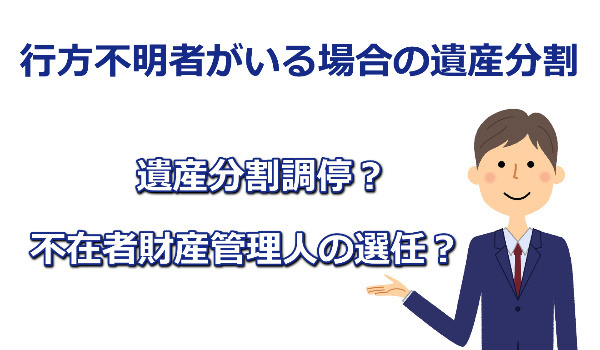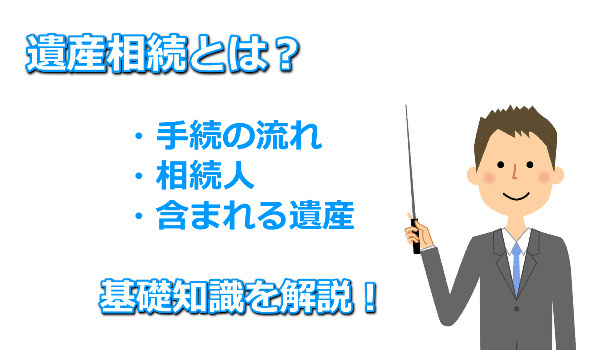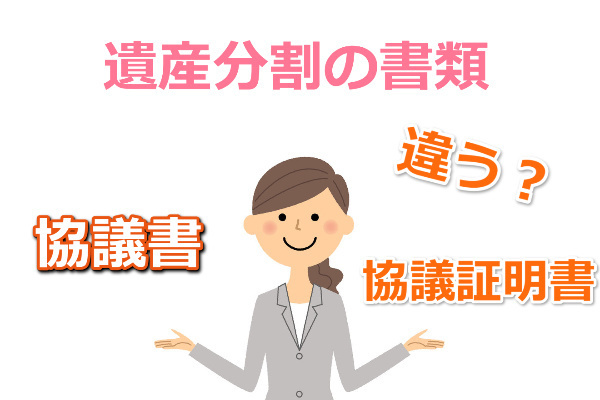相続・遺言に関する手続の総合案内(合同会社つなぐ(FP)×司法書士法人黒川事務所×行政書士黒川事務所の運営サイト)
遺産分割の手続きの流れと分割方法について

遺産分割とは、「誰が」「どの財産を」「どの方法で」「どれだけ取得するか」について、相続人全員で協議し、相続財産を分けることをいいます。
遺言がある場合でも、相続人全員で遺言に反する遺産分割をすることも可能ですが、一般的には遺言に従うケースが多いです。
遺産分割協議に相続人全員が参加していなかった場合は、その分割協議は無効となってしまいます。
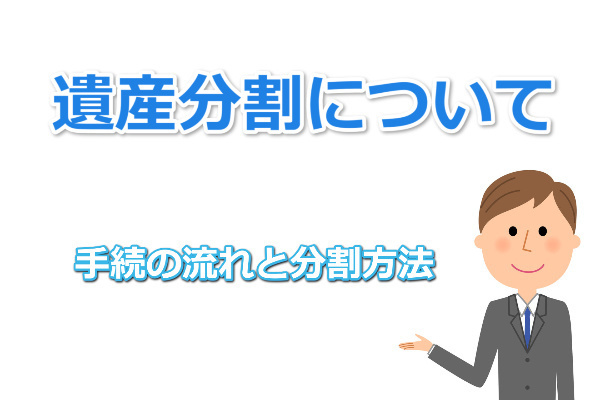
遺産分割の流れ
遺言の有無を確認する
遺言書の有無を確認しましょう。
自筆遺言証書は、自宅や銀行の貸金庫だけでなく法務局で保管されているケースもあります。
公正証書遺言の有無は、公証役場で調べることが可能です。
相続財産の確認
預金などのプラスの財産だけでなく債務などのマイナスの財産も含めて相続財産がどれくらいあるか・金額にしてどれくらいなのかを整理しましょう。
相続人の確定
遺産分割協議は相続人全員の同意が必要です。
相続人の一部でも欠けていれば無効になります。
お亡くなりになられた方の戸籍謄本を出生まで遡って取得して相続人を確定します。
相続人で遺産分割協議をする
遺産分割協議と言っても、一堂に会して話し合いをする必要はなく持ち回りで協議しても大丈夫です。
遺産の無事に配分についての話し合いができれば、「遺産分割協議書」という書類を作成し合意内容をまとめます。
遺産分割協議書は、相続登記や銀行預金などを解約する場合にも使用しますので、全員が実印を押印し印鑑証明書とセットにしておきます。
話がまとまらない場合は裁判所で「調停」「審判」
相続人間で分割協議がまとまらない場合は、裁判所へ遺産分割調停を申立てることになります。
裁判所の調停委員が間に入って、話し合いを行います。
調停でも協議がまとまらない場合は、審判へ移行します。
審判になれば裁判所が分割について最終的な判断を下します。
遺産分割の方法
現物分割
遺産そのものを現物で受け取る方法です。遺産分割で一番多いのがこの現物分割です。
たとえば・・・
- 例えば親の住んでいた土地・建物⇒長男
- 親の所有していた別荘⇒次男
- 預貯金の1000万円⇒長女
この現物分割をする場合、各相続人の相続分をきっちり分けることが困難となるため、代償分割で補完するケースもあります。
代償分割
相続分以上の財産を取得する場合、その代償として他の相続人に金銭を支払う方法です。
たとえば・・・
- 長男が親の会社の資産の株式や店舗を相続
- その代わりに、長男が次男に代償金(1000万円)を支払う
換価分割
遺産を売却して金銭に変換した上で、その金額を分ける方法です。現物を分割してしまうと価値が低下する場合などは、この方法が採られます
- 唯一の相続財産である不動産を売却して、相続人で分配する
遺産分割の期限|いつまでにする?
遺産分割はいつまでにしなければいけないというルールはありませんが、相続税の申告期限までには済ませておくのがベストです。
相続税の申告・納付は「相続開始から10か月以内」です。
期限までに遺産分割が成立している必要がある代表的な税額の軽減
相続税の申告・納付期限内に遺産分割協議が終わっていないと、遺産分割協議が完了していることを前提とした減税措置を受けられなくなることがあります。
配偶者の税額の軽減
配偶者の税額の軽減とは、亡くなった方の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、「①1億6千万円か②配偶者の法定相続分の金額」のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
この制度は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっているので、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。
(ただし、相続税の申告書又は更正の請求書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、申告期限から3年以内に分割したときは税額軽減の対象になります)
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、亡くなった方と一緒に住んでいた自宅の土地を相続した場合、330㎡まで土地の評価を80%減額できる制度です。
この特例の適用を受けるには、対象となる土地を遺産分割で取得する必要がありますので、遺産分割が終わっていないと適用を受けることができません。
遺産分割協議書の作成
遺産分割が成立したら「遺産分割協議書」を作成しましょう。
【ポイント】
協議が成立した日付を記載し、相続人全員で署名・実印で押印しましょう。
(相続登記や預金の解約の際に、実印の押印と印鑑証明書が求められます)
【被相続人】
氏名・亡くなった日・最後の住所・本籍地を記載しましょう。
【不動産】
登記簿謄本(全部事項証明書)に記載されている内容と同じように記載しましょう。
【預金】
金融機関名、支店名、預金の種類、口座番号を記載して預金内容を特定できるようしましょう。
【自動車】
車検証に記載されているとおりに登録番号や車台番号まで記載しましょう。
遺産分割協議に参加できない相続人がいる場合
未成年者がいる場合
未成年者がいる場合は、親権者が遺産分割協議をすることになります。
しかし、親権者も同じく相続人の場合は、利益相反といって未成年者と利害が対立することになります。この場合は、家庭裁判所で特別代理人を選任して、特別代理人が未成年者に代わって手続きをすることになります。
認知症など意思表示ができない人がいる場合
相続人に認知症の方がいる場合は、家庭裁判所に成年後見を申立てて成年後見人を選任します。
そして、成年後見人が遺産分割協議に参加することになります。
行方不明者がいる場合
行方不明者がいる場合は、家庭裁判所で不在者財産管理人を選任してもらい、行方不明者に代わって不在者財産管理人が遺産分割協議に参加します。
遺産分割など相続のお手続きは当事務所へご相談ください
遺産分割協議のご相談も含め、当事務所は相続手続きのトータルサポートを心がけております。
初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。