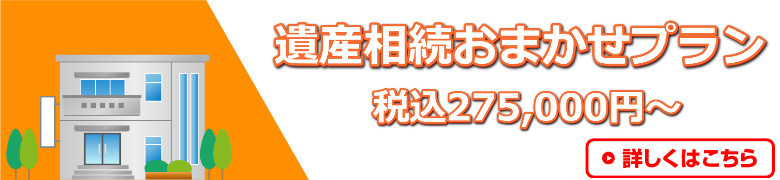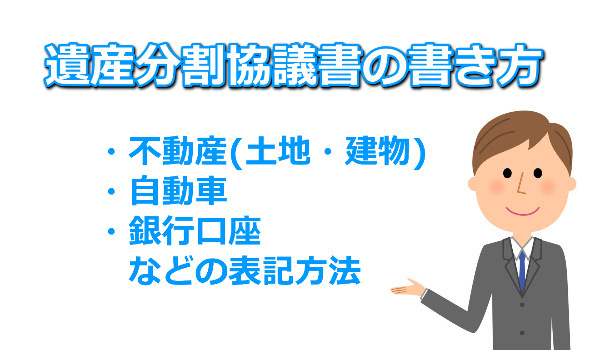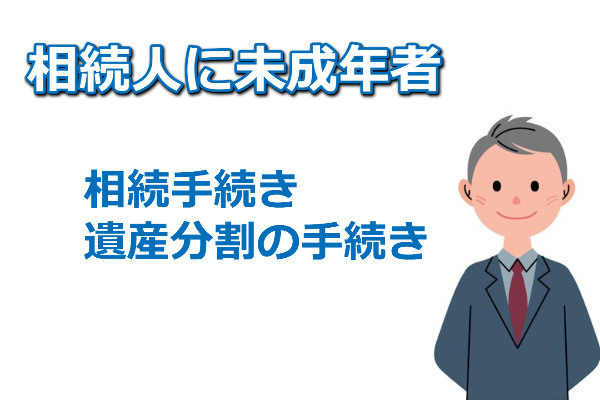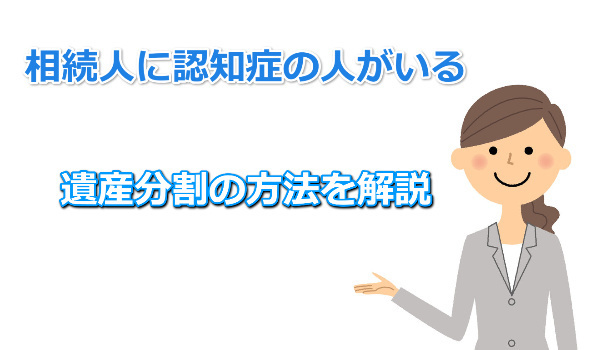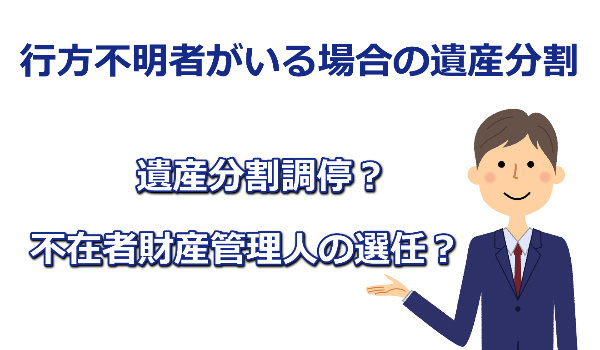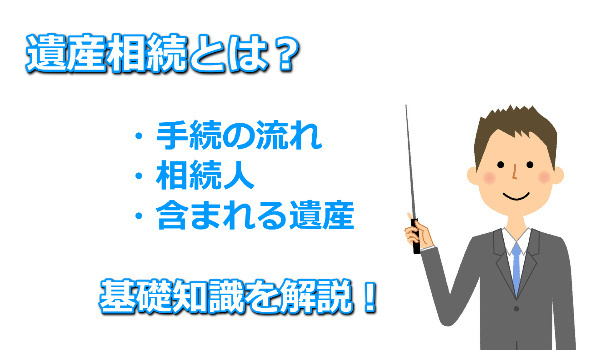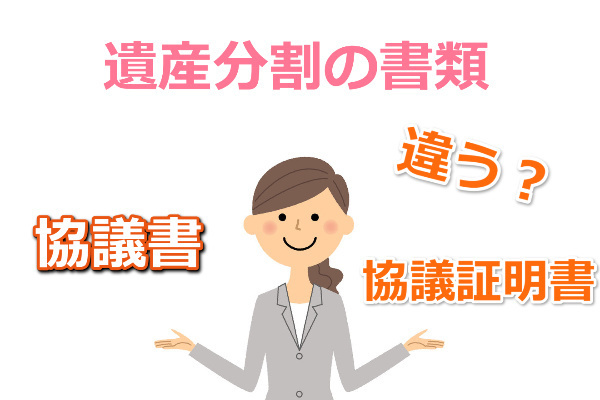相続・遺言に関する手続の総合案内(合同会社つなぐ(FP)×司法書士法人黒川事務所×行政書士黒川事務所の運営サイト)
相続人に未成年者がいる場合の相続手続き(遺産分割協議の方法)
相続人に未成年者がいる場合(相続人が配偶者と子供のケースなど)は、未成年者は自ら遺産分割協議に参加できません。
多くのケースでは家庭裁判所に未成年者の特別代理人の選任を申立てる必要があります。
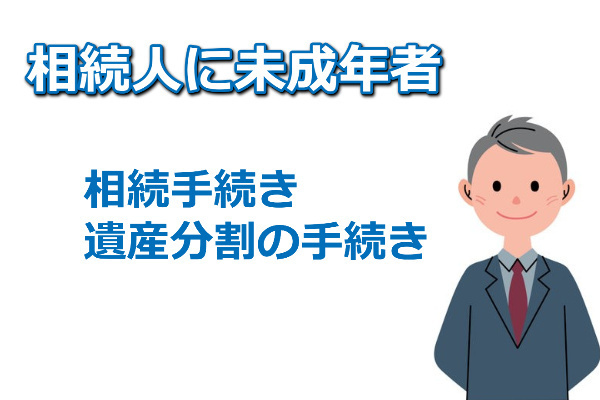
未成年者が相続人にいる場合の手続き

未成年者は単独で遺産分割協議に参加できません。
親権者が代わりに遺産分割協議に参加することになりますが、多くのケースでは親権者も相続人です(夫が亡くなり妻と未成年の子が相続人など)。
そのため、親権者と未成年者の利益相反の関係(一方が得をすると一方が損をする関係)になり、この場合は親権者が未成年者の代理として遺産分割協議をすることはできません。
このようなケースでは家庭裁判所に未成年者の特別代理人の選任を申立てる必要があります。
未成年者の特別代理人は誰がなる?
特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てても、裁判所が候補者を探してくれるわけではありません。通常は、申立時に候補者を記載し、その候補者が特別代理人に就任します。
もちろん他の相続人はなれませんので、相続人ではない親戚が就任するケースが多いでしょう。
(夫が亡くなり妻と未成年の子供が相続人の場合は、祖父祖母などに依頼するなど)
未成年者が2人いる場合は、別々の人が2人特別代理人に就任します。
候補者が見つからない場合は、相続手続きを依頼している専門家もなってくれるケースがあります。
遺産分割協議の内容についての注意事項
特別代理人の選任を申し立てる際に、遺産分割協議の案を裁判所に提出します。
この遺産分割協議の案は、法定相続分に応じた遺産分割の内容にする必要があります。
親権者が全部取得するような遺産分割協議は原則として認められません。
特別代理人選任から遺産分割協議までのながれ
未成年の相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に特別代理人選任を申し立てます。
申立ができるのは親権者や利害関係者です。
(申立に必要な書類)
- 特別代理人選任申立書
- 収入印紙800円
- 未成年の戸籍謄本
- 親権者の戸籍謄本
- 特別代理人の候補者の住民票
- 遺産分割協議書案など
内容によっては必要書類が異なることもありますので申立てる家庭裁判所に事前に確認しましょう。
特別代理人が遺産分割協議書に押印する
未成年者の特別代理人が選任された場合は、裁判所に提出した内容の遺産分割協議書に特別代理人が押印します。
この遺産分割協議書を利用して登記手続きや銀行口座の解約手続きを行います。