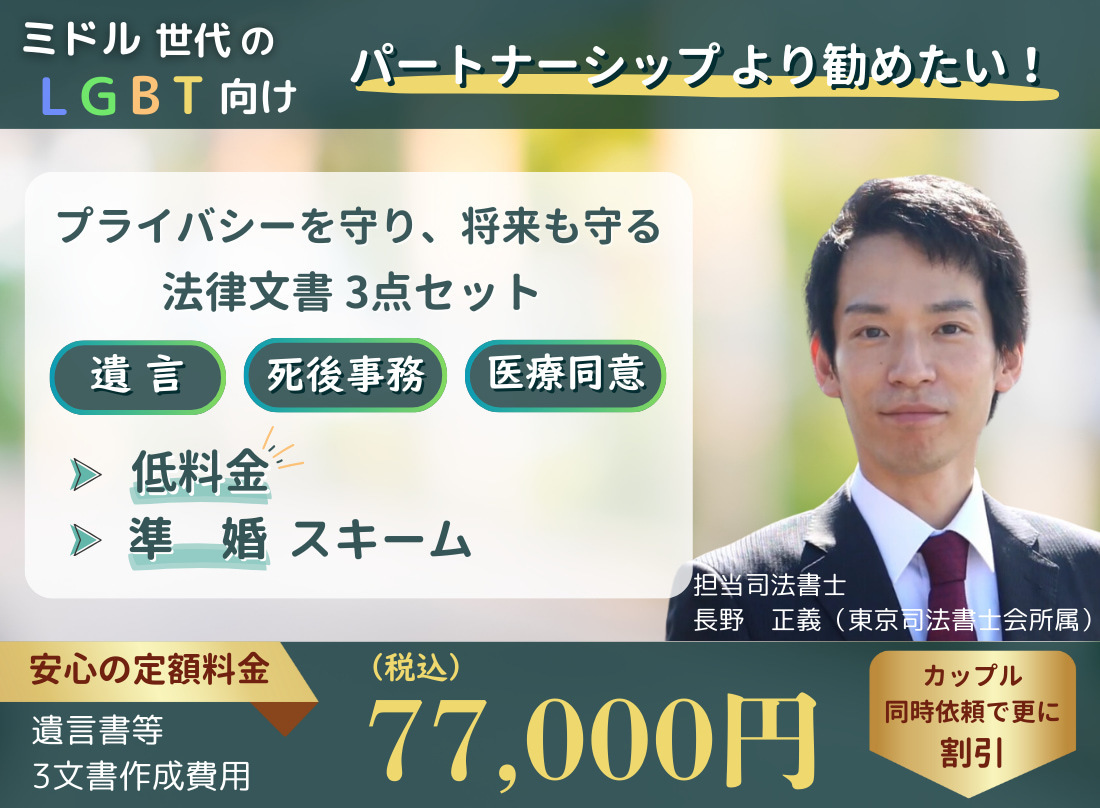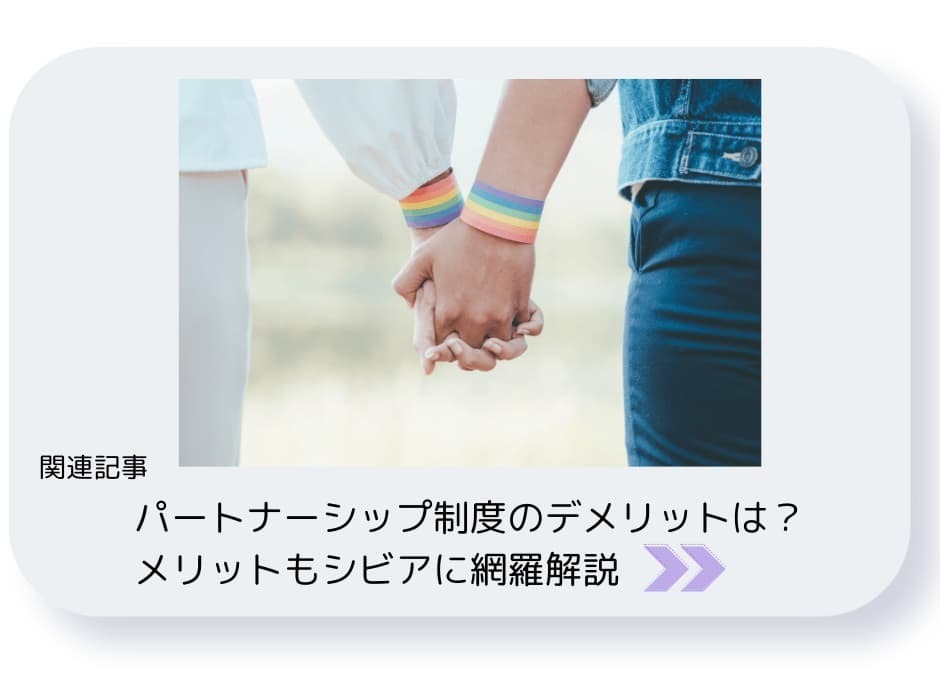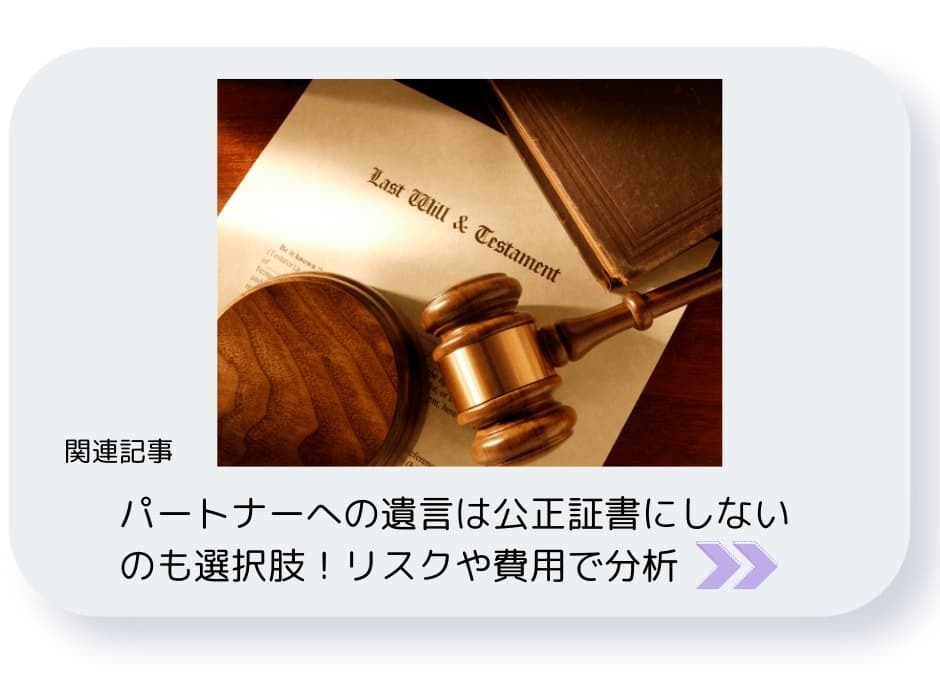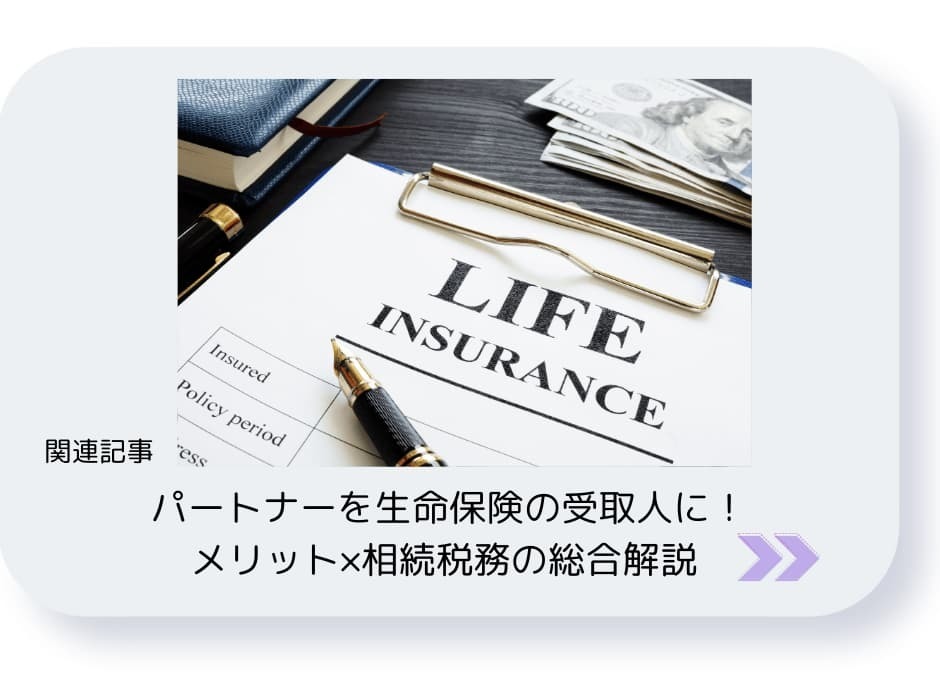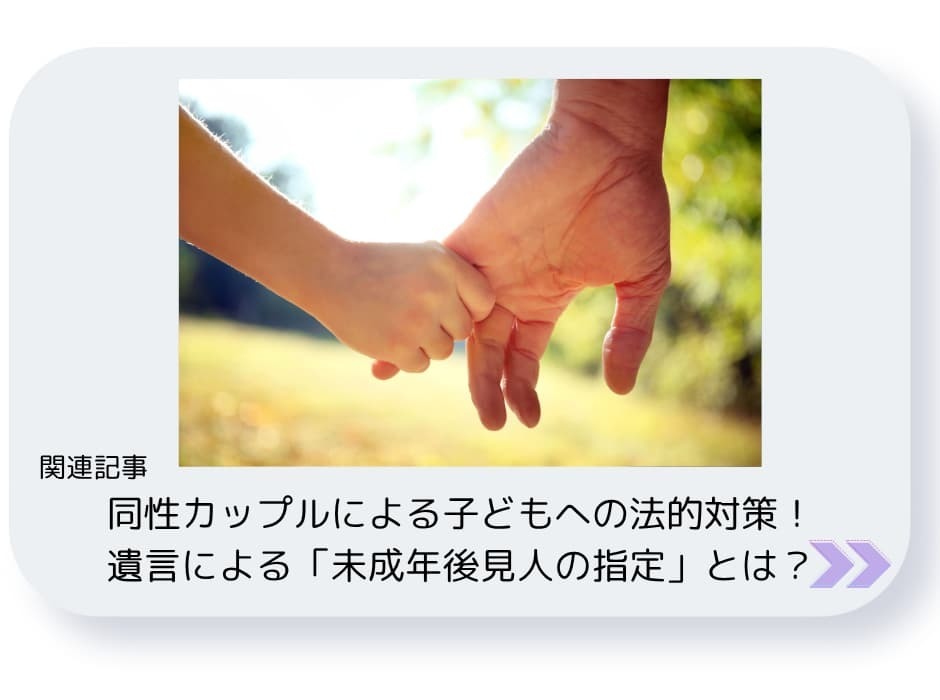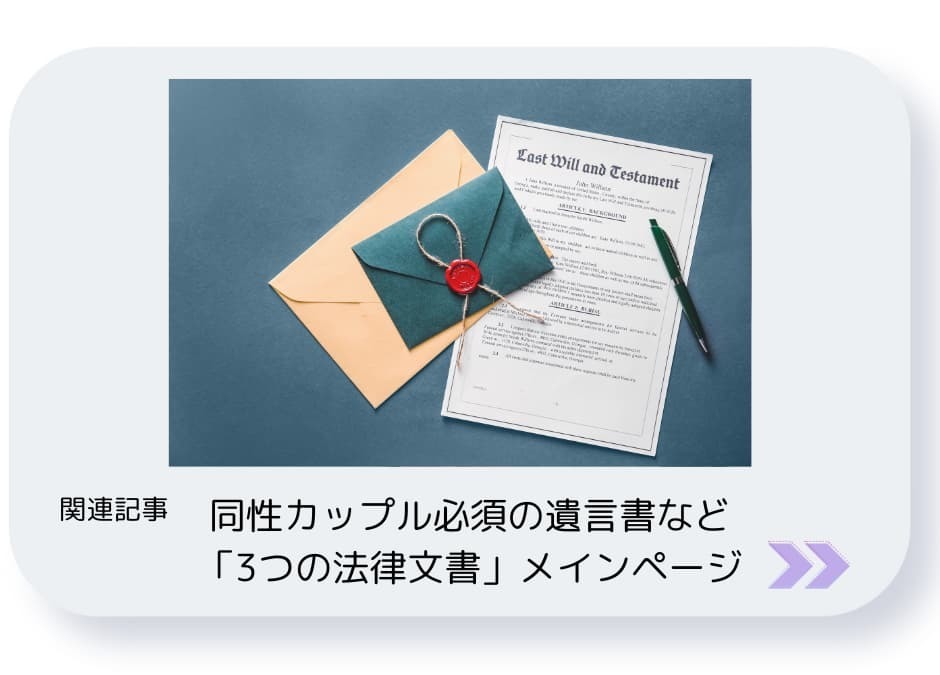相続・遺言に関する手続の総合案内(合同会社つなぐ(FP)×司法書士法人黒川事務所×行政書士黒川事務所の運営サイト)
LGBT(同性)カップルの相続対策!パートナーへの遺言書のポイント7つ
最終更新日:2025年7月10日
「長年連れ添ったパートナーに財産を残したい」
レズビアンやゲイなどの LGBTの方が、ご自身に万一があったときに備えて同性パートナーへの遺産承継を考えるときは、遺言書が有効な法的対策となります。
なぜなら、パートナーシップ制度に登録(宣誓)しても、相続対策にはならないからです。
これは、異性間の結婚と同じような共同生活をパートナーと長年送り、同性事実婚と呼べる状態であったとしても同様です。
同性パートナーのために遺言書を作成する際、ポイントとなる事項がいくつかあります。
今回は、特に重要なポイント7つを詳しく解説していきたいと思います。
各ポイントをしっかり深堀りしているため専門的な内容が含まれますが、分かりやすさも目指しましたので、もしご自身で遺言書の作成を検討されている方はぜひ参考にされてください。
共同遺言はせず公正証書等にしよう
遺言書に書く内容の解説に入る前に、同性カップルの方向けに遺言書の方式について解説します。
一言で言えば、「①お一人につき一つの遺言書を作成して、②役所で審査・保管される方式を選択する」ことをお勧めします。
具体的には、①共同遺言は避けて、②公正証書遺言を利用するか、自筆証書遺言を利用する場合でも法務局に保管しておこう、ということになります。
それぞれ下記で詳しく解説していきます。

遺言書の種類は大きく分けて公正証書遺言(公証人という法律専門職に作成してもらう遺言)と自筆証書遺言(公証人の関与なく自分で作成する遺言)があります。
どこの法律系ネット記事も公正証書遺言を推奨していますが、ミドル世代の同性カップルの方が遺言書を作るなら、自筆証書遺言も有効な選択肢と当事務所は考えています。
公正証書遺言は公証人のチェックを受け、公証役場で保管されるため、やはり確実性は高いです。
他方で自筆証書遺言も、令和2年に法務局保管制度が施行されたことにより、法務局職員のチェックを受けた上で法務局で保管してもらうことが可能になったため、選択肢として十分検討に値するようになりました。
公正証書遺言と自筆証書遺言については下記の記事で徹底的に比較解説をしているので、よければご覧ください。
遺贈の種類に気を付けよう
遺言書で財産を贈与することを遺贈と言いますが、遺贈にも法律で複数の種類が用意されています。
遺言書は、どの種類の遺贈を選択するのかを意識しながら作成することは必須といえます。
なぜなら、遺贈の種類によって、その効力に大変重要な違いが出てくるからです。
下記では、遺贈の種類について、その意義や特徴から、選択のポイントまで詳しく解説していきます。

遺贈は3種類ある
一部包括遺贈は避ける
一部包括遺贈の場合は遺産分割協議が必要になるため、避けるべきです。
遺産分割とは、相続又は遺贈された持分割合などを参考にしつつ、具体的に誰がどの財産を取得するのかを決めることです。
遺産分割の例
| 遺言書の記載 | 田中太郎(パートナー)に対し全遺産の2分の1を遺贈する(一部包括遺贈) |
|---|---|
| 遺産分割協議の例 | 唯一の相続人である姉の鈴木花子は、遺産のうちの不動産(査定額1000万程)を取得する 一部包括遺贈を受けた田中太郎(パートナー)は、遺産のうちの預貯金(残高700万程)と株式(評価額300万程)を取得する |
そしてこの遺産分割の協議は、相続人と、一部包括遺贈を受けた人との全員で行い、合意に達する必要があります。
つまり、ご自身の親族とパートナーとは、全ての遺産を取得できないという面で利益が対立する中で、話し合いをしなければならなくなってしまいます。

一部包括遺贈に近づける方法
上記のように一部包括遺贈は避けるべきですが、財産形成の途上にあるミドル世代の遺言の場合は、概括的な定め方の方がご意向に沿う場合も少なくないと思います。
例えば、「配偶者と兄弟姉妹の法定相続」に近付ける形で「遺産の4分の3はパートナーに、4分の1は兄弟に残したい」といったご希望を伺うことがよくあります。
その場合は次善の策として、パートナーに全部包括遺贈などをしつつ、遺言書に下記のような定めを設けて、パートナーへの遺贈を「負担付遺贈」としたり、後で解説する「付言事項」を活用することを検討してみてもよいでしょう。
一部包括遺贈の代替策
| 遺言書の記載例 | |
|---|---|
| 負担付遺贈 | 田中太郎(パートナー)は、前条の全部包括遺贈の負担として、遺言者の姉の鈴木花子に対し、遺言者の全預貯金の合計額の4分の1相当額の金員を、遺言者の死亡から1年以内に贈与するものとする。 ただし、田中太郎に遺贈した財産の価額が遺言者の親の遺留分侵害額請求によって減少したときは、その減少の割合にかかわらず田中太郎の負担を全部免責する。 |
| 付言事項 | 田中太郎(パートナー)には、遺言者の姉の鈴木花子に対し、遺言者の全預貯金の4分の1相当額に近い金額の金員を贈与することを検討してもらいたい。 とはいえ、かかる贈与を行うか否か、及び贈与を行う場合の具体的金額は、遺言者の晩年の遺志を汲み取りつつ、田中太郎の裁量のみで決めてもらってかまわない。 |
借金も遺贈の種類で変わる
相続人無しなら全部包括遺贈
当事務所では、ミドル世代の遺言をお勧めしているため、遺言の種類について、親などの法定相続人がいる前提でこれまで解説してきました。
しかし、法定相続人が一人もいない場合には少し話が変わってきます。
既にご両親や祖父母がご逝去されており、かつ、ご自身が一人っ子でご兄弟もいないというような場合です。
このような場合には、一部包括遺贈を避けるだけでなく、特定遺贈も避けて、全部包括遺贈にしておいた方が無難です。
というのも、特定遺贈や一部包括遺贈の場合には、死後に裁判所に対し「相続財産清算人」の選任申立てが必要になる可能性があります。
この手続の詳細は割愛しますが、この手続の下では、遺言書どおりにパートナーへの遺贈がなされるのか不確実となったり、何十万円という費用が必要になるなど、大きなデメリットを伴います。
遺留分に気を付けよう
遺言書を作成する際は、遺留分への配慮がとても重要です。
なぜなら、遺留分をめぐって相続人と遺贈を受ける人との間でトラブルに発展することが少なくないからです。
この問題は、遺言書で幾つか対策を講じることで、リスクを減らすことができます。
下記では、遺留分とは何なのかということから、その対策まで、詳しく解説していきます。

遺留分は相続人の強い権利
遺留分とは、分かりやすく言えば、「法定相続人に最低限確保される、遺産の一部請求権」のことです。
「最低限」というように、この請求権は遺言書でも奪うことができません。
例えば、遺言書で「パートナーに全財産を遺贈する」と書いておいても、一部の法定相続人はパートナーに遺留分の請求をすることで、遺産を一部もらい受けることができます。
遺留分を請求できる法定相続人のことを「遺留分権利者」といいますが、具体的に誰かというと、概ね下記のとおりです(法律上の配偶者はいない前提です)。
ここでのポイントは、兄弟姉妹は遺留分権利者ではないという点です。
遺留分権利者
| ケース | 遺留分権利者 |
|---|---|
| 亡くなった方に子供がいるとき | 子供 |
| 亡くなった方に子供がいないとき | 親 (又は祖父母) |
遺留分の金額も民法で決められており、配偶者がいない前提で言えば、下記のとおりです。
遺留分の金額
| ケース | 遺留分の金額 |
|---|---|
| 遺留分権利者が子供 | 遺産全体の評価額の2分の1 |
| 遺留分権利者が親 | 遺産全体の評価額の3分の1 |
| ※子供ないし親が複数名いる(生存している)場合 | 上記の金額を人数で分ける |
親の遺留分に注意
遺留分は急ぎの支払いが必要
遺留分の請求がされたら、原則として即時一括で支払う必要があります。
例えば、上記の例で、唯一の遺産である住宅を遺贈した場合は、その時価査定額の3分の1相当額をすぐに支払う必要があります。
その場合に、預金などがないと、支払いが遅れて遅延損害金の支払義務も生じたり、住宅売却の検討を迫られるなど、苦慮することになってしまいます。

遺留分対策の第一は流動資産
一般的な遺留分への対策は、遺贈する財産を少な目にすることです。
例えば遺留分権利者が親なら、パートナーには遺産全体の3分の2相当額の財産の遺贈にとどめるわけです。
しかし、LGBTの方の遺言の場合は、前記のように割合での指定は一部包括遺贈となるため避けるべきですし、財産を特定して遺贈額を調整するのも、財産形成の途上であるミドル世代の方の遺言の場合はなかなか難しいと思います。
そうなると次の対策としては、現金化しやすい預貯金や株などの流動資産を多めにパートナーに遺贈しておくということになります。そのような遺言書と併せて、保険金受取人をパートナーに指定する生命保険への加入も検討に値します。
遺留分対策の第二は順位付け
前記のとおり遺言書でも遺留分の請求自体を排除することはできませんが、遺贈の贈り先がパートナー以外にもいるときは、遺留分請求に対応しなければならない遺贈先に順番を付けることはできます(民法1047条1項2号但書)。
例えば、「遺留分請求がされたときは、まず佐藤次郎(パートナー以外の遺贈先)が支払い、佐藤次郎への遺贈財産相当額を佐藤次郎が支払ってもなお遺留分に足りない場合に限り、パートナーも支払う」という意味合いで、下記のように定めます。
遺留分の負担順位の定めの例
| 遺言書の記載例 |
|---|
| 遺留分侵害額請求が万一なされたときは、遺言者は、当該遺留分侵害額についてまず佐藤次郎が負担し、次に田中太郎(パートナー)が負担するものと定める。 |
「相続させる」を併用しよう
もし将来的に国が同性婚を認めたら、パートナーと同性婚されますか?
そのお気持ちが少しでもあるなら、遺言書には「遺贈する」旨の定めに「相続させる」という読み替え規定を設けておきましょう。
この一手間で節税などのメリットにつながる可能性があります。
下記では、この「相続させる」文言活用のテクニックについて詳しく解説していきます。
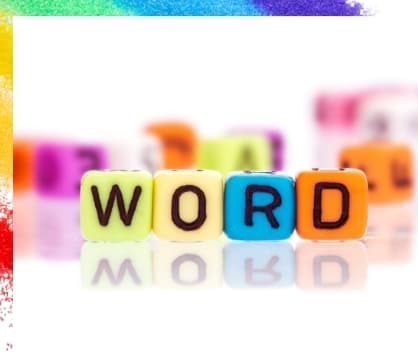
遺産承継の2種類の文言
「遺贈する」と「相続させる」の効力の違い
同性カップルでの「相続させる」遺言
同性カップルの方は、法的には親族ではなく相続人にはなれません。
そのため、遺言書の文言は基本的に「遺贈する」を用いることになります。
しかし、もし将来的にパートナーとの間で、養子縁組をする可能性や、同性婚が法制化された場合に同性婚をする可能性があるのでしたら話は変わります。
養子縁組や同性婚をすればパートナーは相続人の地位を得るため、そのような可能性がある場合には、下記のような「相続させる」遺言への読み替え規定を設けることも積極的に検討しましょう。
そうすることで、パートナーは節税などのメリットを享受することが可能になります。
「相続させる」読替規定の例
| 遺言書の記載例 |
|---|
| 遺言者の死亡時点において、田中太郎(パートナー)が遺言者の相続人の地位にあるときは、本件遺言において「遺贈する」とあるのは「相続させる」と読み替えるものとする。 |
祭祀承継者を指定しよう
もしご自身が亡くなられたときは、遺骨や位牌という形になっても、そばに居ることでパートナーの悲しみを少しでも和らげてあげたい。
そう思われるのでしたら、祭祀承継者としてパートナーを指定しておきましょう。
下記では、祭祀承継者の意義や必要性、デメリットの有無まで、詳しく解説していきます。

祭祀承継者が遺骨も承継
祭祀承継者とは、「祭祀財産」を承継する人のことです。
祭祀財産の所有権は、他の一般的な財産とは別の相続ルールが適用され、法定相続人が相続せず、祭祀承継者が取得することになります(民法897条)。
祭祀財産とは、具体的には下記になります。
祭祀財産
| 祭祀財産の種別 | 具体例 |
|---|---|
| 系譜 | 家系図 |
| 祭具 | 仏壇 仏具 |
| 墳墓 | お墓 |
若い世代の方はこのような財産にあまり馴染みがないかもしれません。
しかし、判例では遺骨の所有権も祭祀財産に準じて取り扱われるものとされていますので(最判平成元年7月18日)、重要な問題です。
つまり、「祭祀承継者」として遺言書等でパートナーを指定しておかないと、葬儀の主導や遺骨の管理を誰がするのか争いになったときに、裁判沙汰で決着を付けるという事態になってしまいます。
そのため、葬儀や納骨(散骨)、永代供養などをご自身の親族ではなくパートナーに任せたいとお考えの方は、祭祀承継者として指定しておいた方が良いでしょう。
祭祀承継者の指定の例
| 遺言書の記載例 |
|---|
| 遺言者は、遺言者の祭祀を主宰すべき者として田中太郎(パートナー)を指定する。 |
遺言執行者を指定しよう
遺言内容を実現するには、不動産の名義変更や預金の引出しなど、死後に多くの手続が必要になります。
パートナーに不動産等を遺贈しても、実際の名義変更等の手続で、法定相続人となる親族の協力が必要になるのが原則です。
しかしそれでは、遺贈の実現に支障が生じるリスクもあるため、遺言書でパートナーを遺言執行者にも指定しておくことをお勧めします。
この記事では、遺言執行者の意義や指定のテクニックについて詳しく解説していきます。
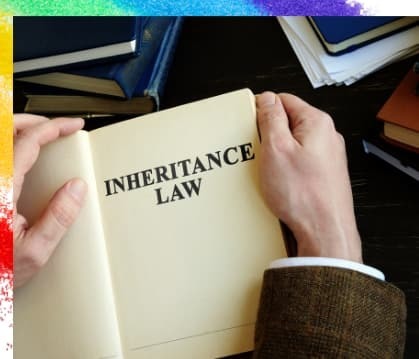
遺言執行者で遺贈が円滑に
遺言執行者は復任も可能
遺言書で指定された遺言執行者は、さらに別の人に遺言執行を任せることも可能です(民法1016条)。
パートナーを遺言執行者に指定しておけば、パートナーは司法書士や弁護士などの専門家に後から遺言執行の依頼をすることも可能です。
最近は、遺言執行に注力する専門家の数もかなり増えているので、専門家を探すのに苦労するということも少ないでしょう。
遺言執行者は遺贈先で分ける
遺言執行者は、複数名を指定したり、遺言執行者ごとにその権限を分けることも可能です(民法1017条1項但書)。
そのため、遺贈の送り先がパートナー以外にもいるときは、下記のように遺贈先ごとに遺言執行者を指定しておくと、「自分のことは自分でやる」という構造にできるので、都合がよいことも多いでしょう。
遺言執行者の指定の例
| 遺贈の例 | 遺言書の記載例 |
|---|---|
| 実家関連の不動産は兄に、 それ以外の全遺産はパートナーに遺贈したい | 実家関連の不動産遺贈の遺言執行者として姉の鈴木花子を指定し、 それ以外の遺贈の遺言執行者として田中太郎(パートナー)を指定する |
付言事項を活用しよう
遺言書に書く内容には、付言事項(ふげんじこう)というものがあります。
この事項には法的効力を伴わないので、書かなくても大きな問題はありません。
しかし付言事項がないと、ご自身の親族とパートナーとの間で親交がない場合などには、親族側は遺贈の背景となる遺言者の気持ちや経緯などがよく分かりません。
その結果、パートナーへの恨みを買い、無用なトラブルに発展する可能性が高まります。
この記事では、付言事項とはどういうものかというところから、そのメリットまで、詳しく解説していきます。
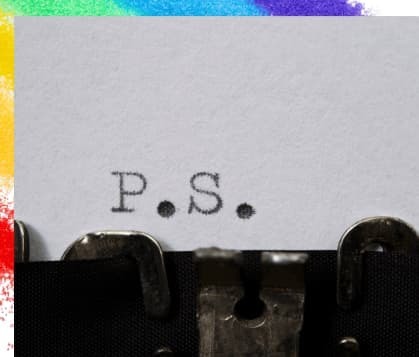
遺言書で書く内容は2種類
付言事項でトラブル回避
付言事項には法的拘束力はありませんが、死者の気持ちが伝わることで、揉めごとが発生するリスクを減らすことができます。
例えば、葬儀についての希望を書いておけば、ご親族とパートナーが葬儀の主導権争いをしなくて済む可能性が高まります。
また、遺贈をした背景事情を記載しておけば、パートナーが遺留分請求を受けるリスクも減らすことができます。
遺留分は、前記のとおり遺留分権利者に最低限確保された権利ですが、権利を行使して実際にお金の請求をするかどうかは遺留分権利者の自由です。
そのため、遺留分が問題になりそうなときは、親族に向けて、穏当な対応を希望する旨やその理由となる事情・気持ちなどを少しでも書いておいた方がよいでしょう。
付言事項の例
| 遺言書の記載例 |
|---|
| 第○条(姉への付言事項) 田中太郎(パートナー)は僕が生涯にわたり大変お世話になった人なので、遺産承継を上記の配分とすることについて田中太郎と争わずに協力して対応してもらえたら、とても嬉しく思います。 |
補足:未成年後見人を指定しよう
レズビアンのカップルの場合は、連れ子等で子どものいるカップルも稀ではないと思います。
その場合、万一の親亡き後の子どもの行く末は非常に重要な問題であり、その問題への手当として遺言書での「未成年後見人の指定」というものがあります。
未成年後見人とは、親権者が死亡等で不存在となった場合に、親権者と同等の権限を行使できる「親代わり」とも言える存在です。
自分の身に万一があった場合に備えて、遺言書でパートナーを未成年後見人に指定しておくことも可能です(民法839条)。
この点は、子どものいる同性カップルにとっては遺言書作成の重要ポイントになりますが、子どもがいないカップルには関心が薄い話題かと思いますので、別の記事で詳しく解説したいと思います。
本サービスの担当・執筆者

長野 正義(ながの まさよし)
保有資格
- 司法書士(東京司法書士会所属/登録番号:第8353号)
- 個人情報保護士
- 知的財産管理技能士(二級)
経歴等
昭和57年 東京都文京区 生まれ
平成16年 中央大学 法学部法律学科 卒業
平成22年 司法書士試験 合格
平成23年 簡易裁判所の訴訟代理権試験 合格
一般企業の法務部、大手の司法書士法人等を経て、現職。
メッセージ
裁判所への書類や企業間契約書など、法律文書の作成を専門として15年程の実務経験があります。定型文中心の行政申請業務が主流の司法書士業界では珍しい経歴かもしれません。
現在は特に、同性カップルの法的課題に対する支援に注力しており、遺言書や医療同意委任契約など、法的効力や実務上の実効性を重視したサポートを行っています。
「一人の人生の大事な局面に関わる責任」を重く受け止め、依頼者の思いに応える成果を提供できるよう、今後も研鑽を続けて参ります。
好きな言葉
・至誠一貫 ・第一義
趣味
・茶道(裏千家/許状:行之行台子)