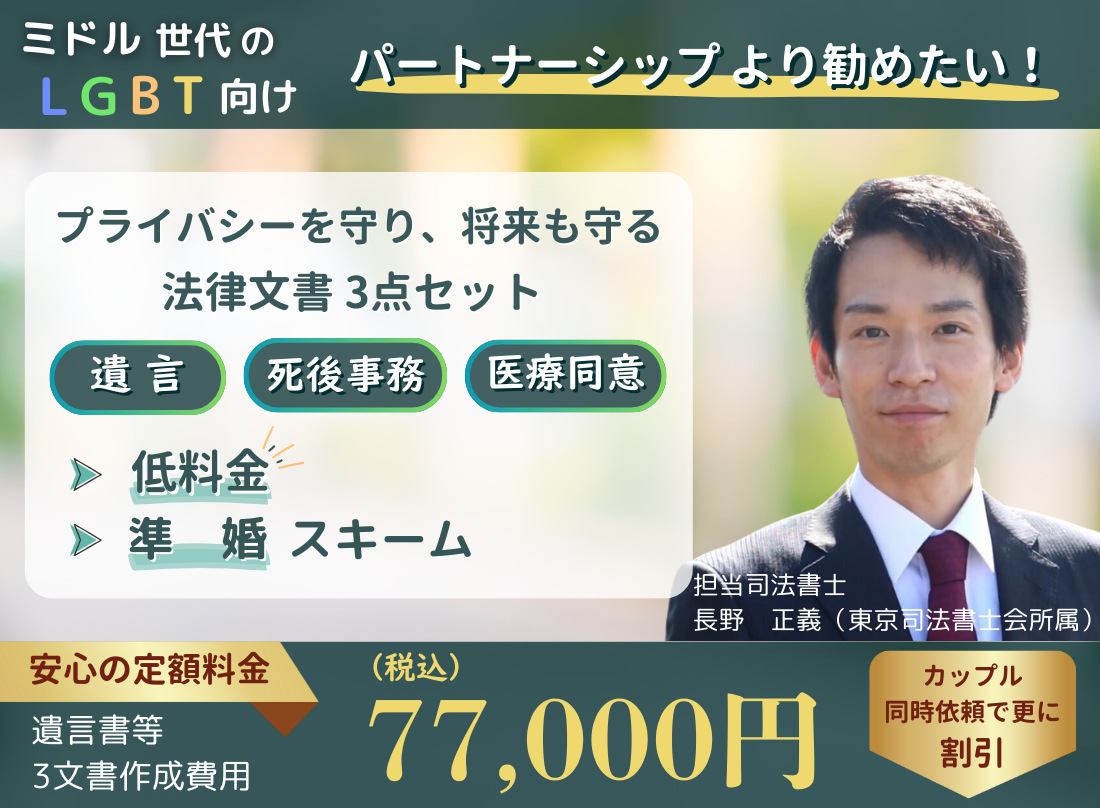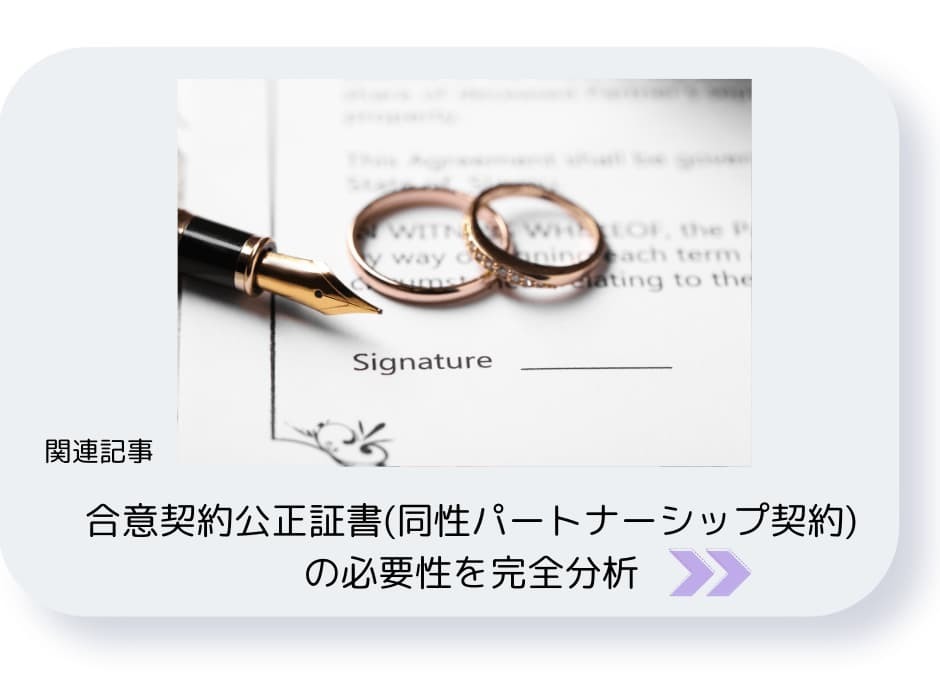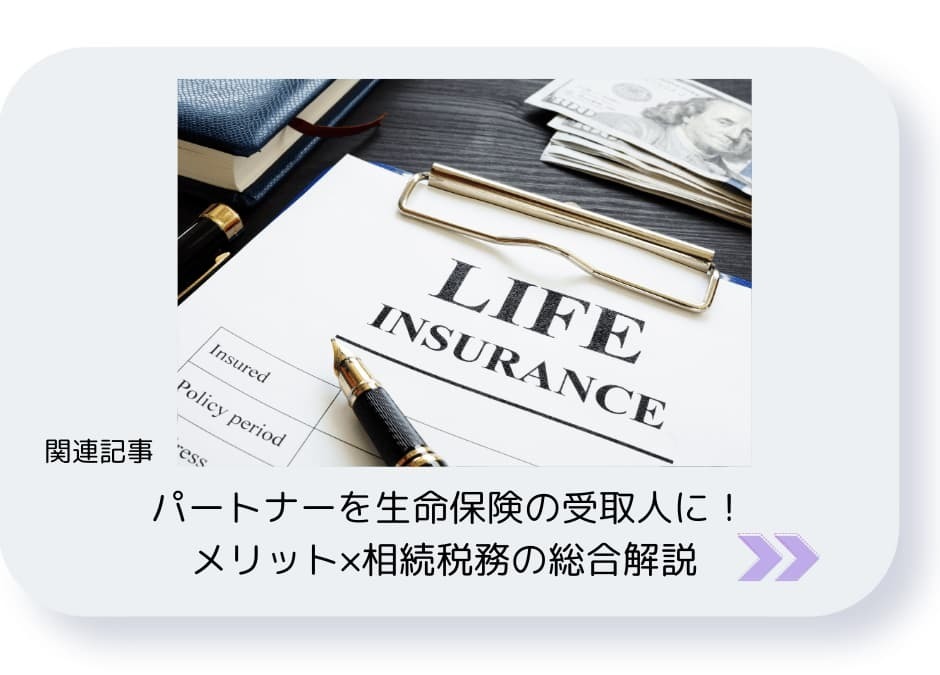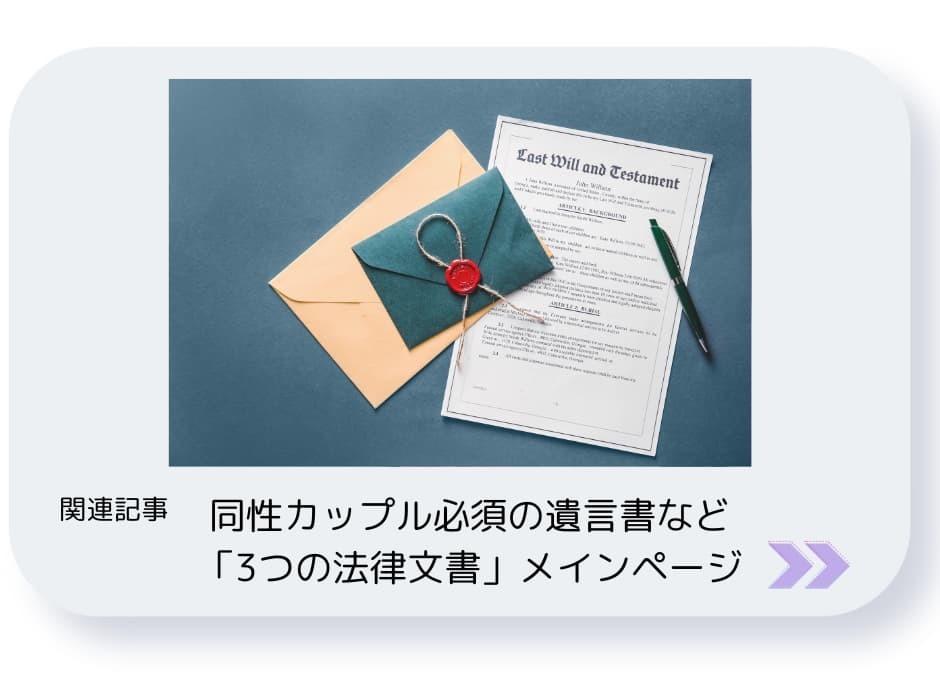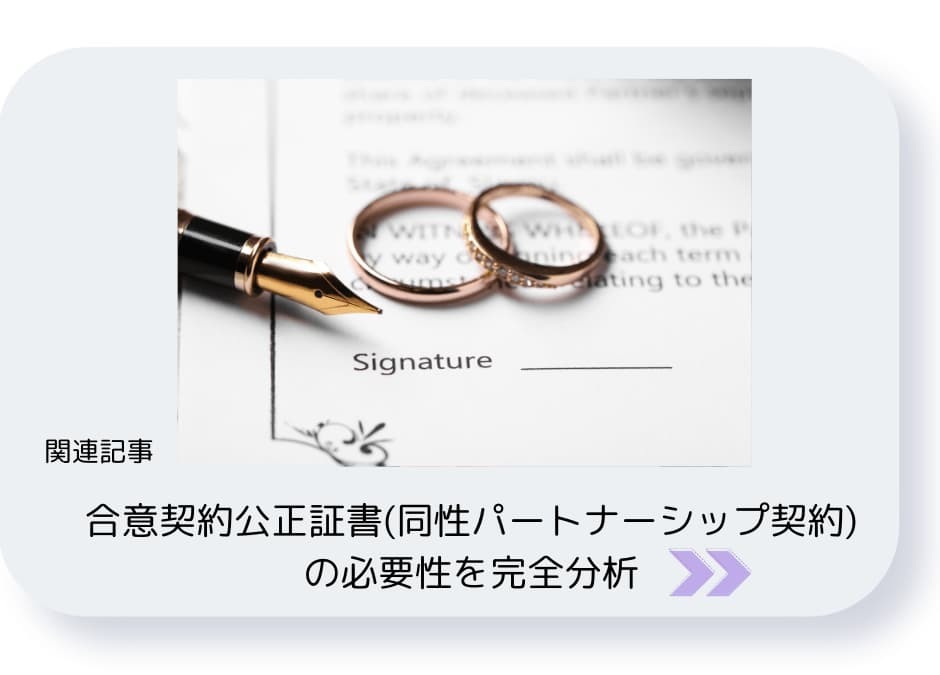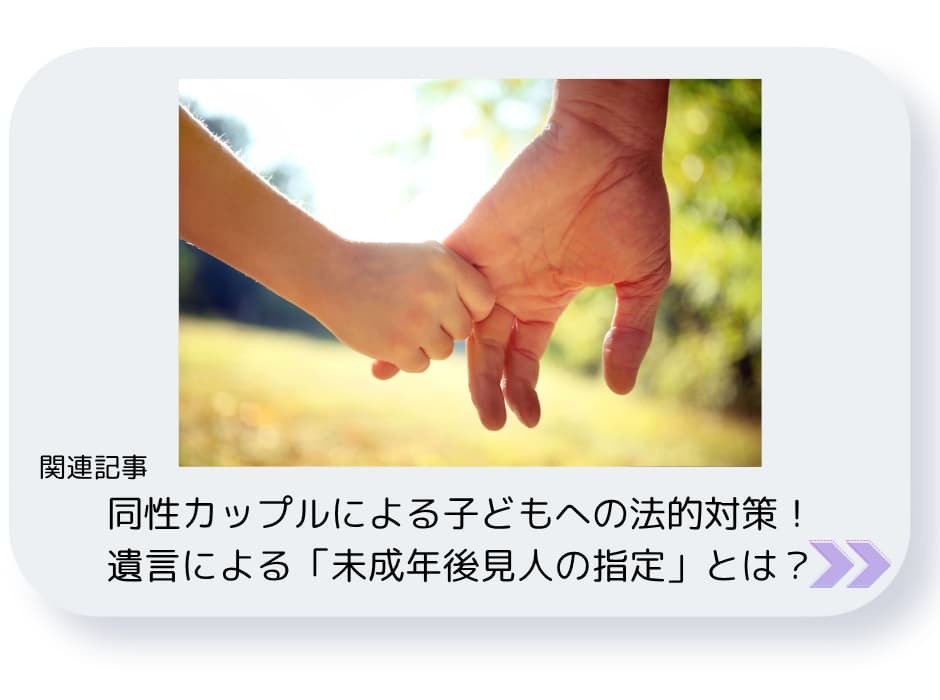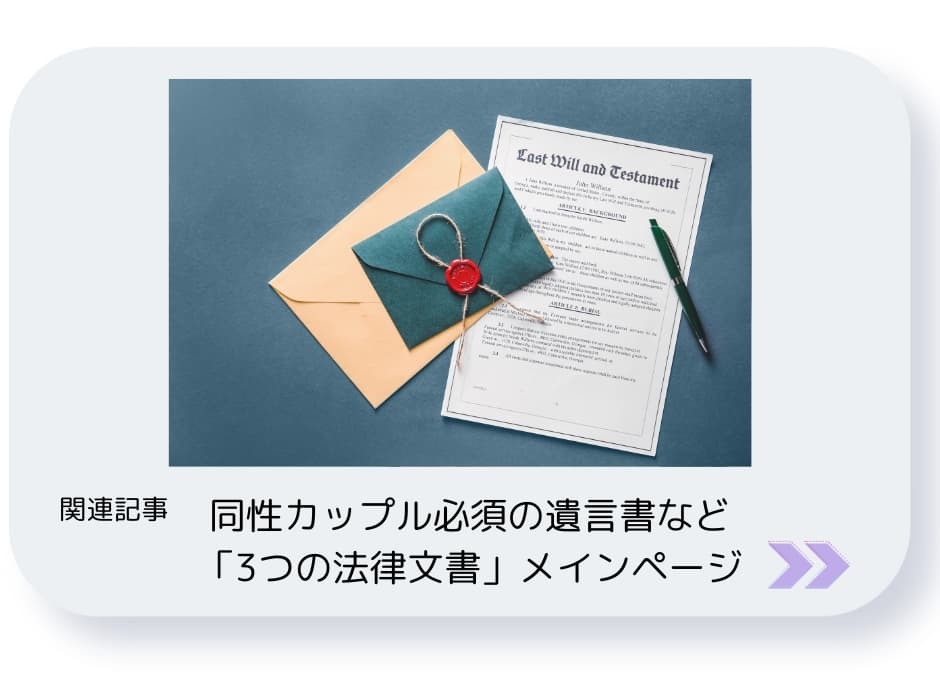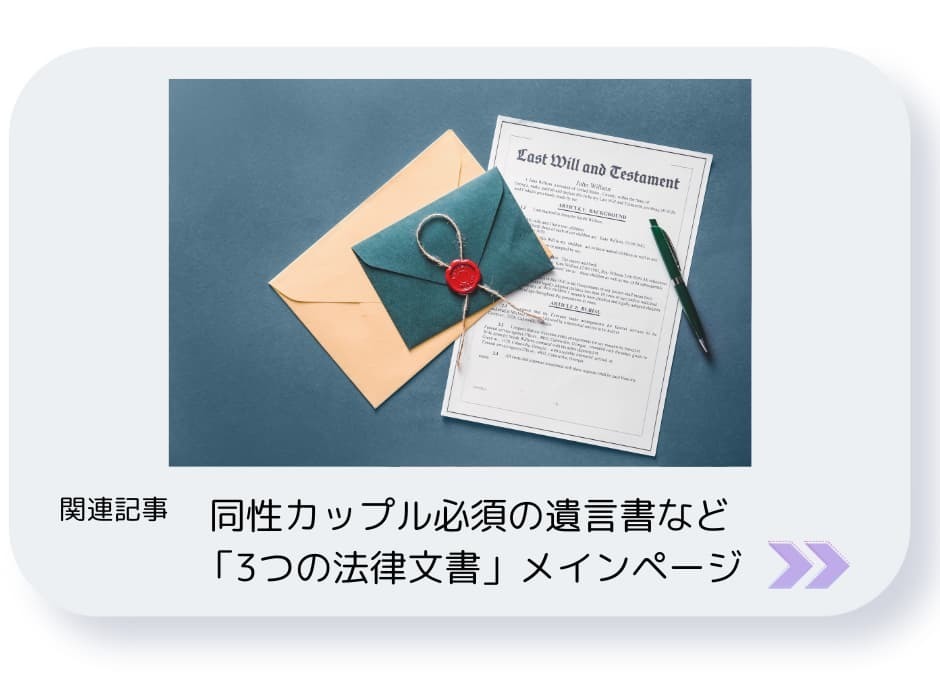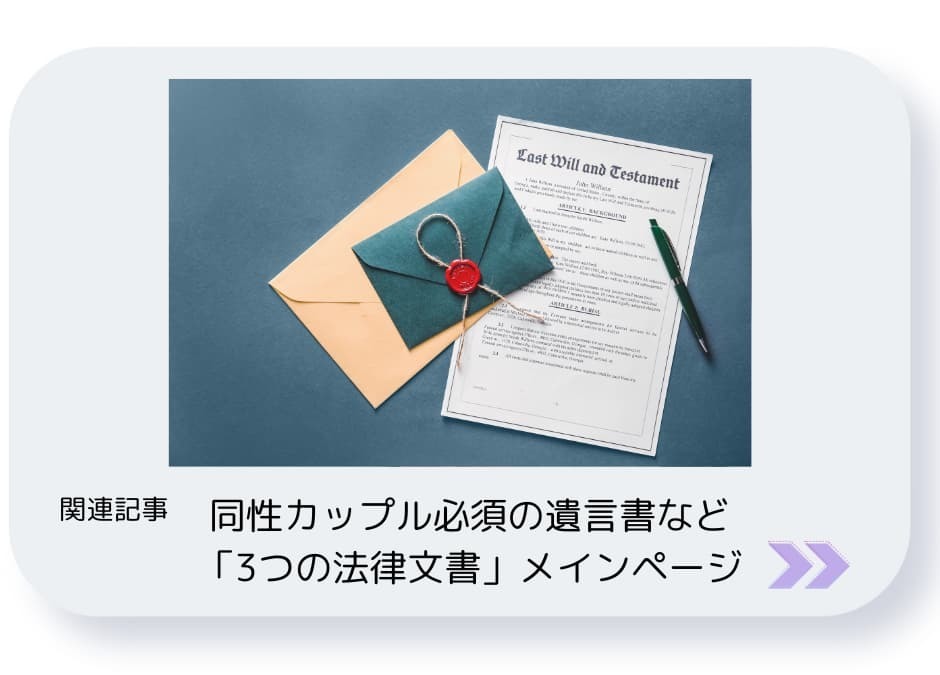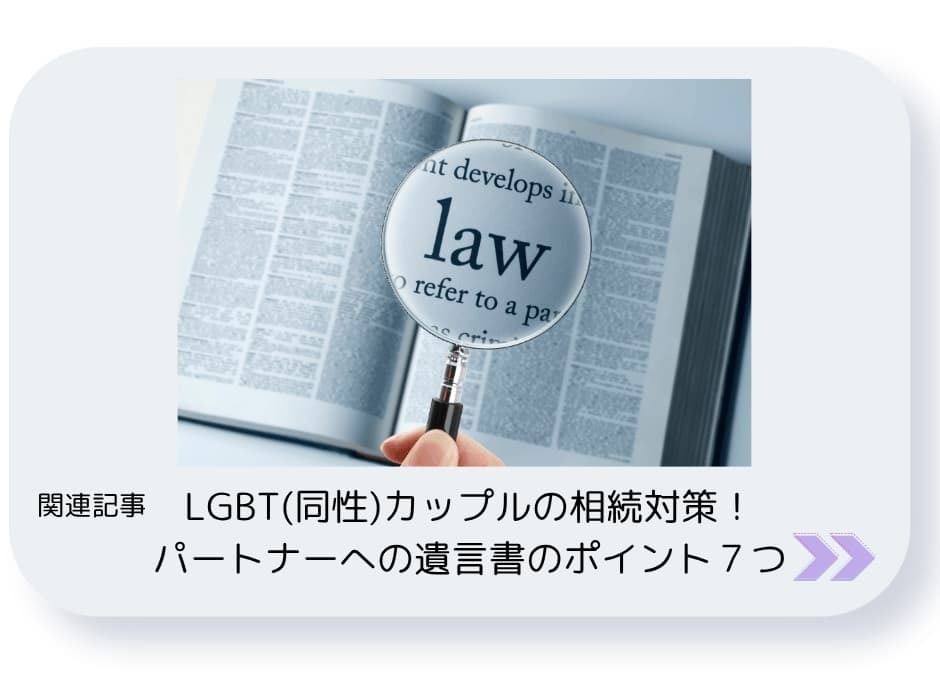相続・遺言に関する手続の総合案内(合同会社つなぐ(FP)×司法書士法人黒川事務所×行政書士黒川事務所の運営サイト)
パートナーシップ制度のデメリットは?メリットもシビアに網羅解説
最終更新日:2025年11月17日
「パートナーシップについて、セレモニーの側面ではなく具体的なメリット・デメリットを知りたい」
レズビアンやゲイなど、LGBTの方向けのパートナーシップ契約(準婚姻契約)や、自治体(市区町村などの役所)のパートナーシップ登録(宣誓)制度に注目が集まっています。
登録した同性カップルの数は、2026年には日本全国で10,000組に達する勢いのようです。
この記事では、それらの契約や制度のメリット、さらにはその限界(デメリット)についても詳しく解説していきます。

パートナーシップ制度のメリットは色々なサービス
民間サービスが受けやすくなる
住宅ローンでのペアローン利用が可能に
みずほ銀行やフラット35など、全国的に多くの金融機関において、同性パートナーと一緒にペアローンや収入合算ローン等を組むことを可能とする取組みが開始されています。
この面は、高額な住宅購入を検討しているカップルにとっては大きなメリットになります。
保険で配偶者と同様の取扱いが可能に
保険金受取人の指定については、同居を証明するための住民票の提出だけで同性パートナーを指定することを可能とする保険会社も増えてきており(ライフネット生命やアクサ生命など)、この面でのパートナーシップの必要性は従前より低くなってきていると言えます。
クレジットカードでの家族カードの作成が可能に
携帯電話の家族割やポイント・マイルの家族利用が可能に
勤務先によっては福利厚生の対象に
行政サービスが受けやすくなる
-この章の目次-
2-2-1.全国自治体でのパートナーシップ制度の傾向と分析
2-2-1-1.全国の行政サービスの例
2-2-2.都道府県と市区町村のパートナーシップ制度の関係
2-2-3.東京・大阪・愛知県のパートナーシップ制度
2-2-3-1.東京のパートナーシップ制度
2-2-3-2.大阪のパートナーシップ制度
2-2-3-3.愛知県のパートナーシップ制度
行政サービスの中にも、その自治体のパートナーシップ登録証を提示することによって、家族同様のサービスを受けることが可能になるものがあります。
まずはパートナーシップ登録による日本全国自治体での行政サービス活用を概観分析した上で、三大都市の自治体(東京・大阪・愛知県)を例に挙げて具体的に有用か見ていきたいと思います。

全国自治体でのパートナーシップ制度の傾向と分析
登録証の提示により利用可能となる行政サービスの範囲は、自治体によってかなりの格差がみられます。
例えば、全国に先駆けてパートナーシップ制度を開始した渋谷区では、主に公営住宅への同居申込が可能になる点に現状限られています(2025年1月1日現在)。
>>渋谷区公式サイト「パートナー関係にある方などが利用できる行政サービス一覧」
お住まいの自治体のホームページ等で、受けられるサービスが公表されていることが多いので、一度ご確認されることをお勧めします。
まだまだ制度の黎明期という面から仕方ないのかもしれませんが、手厚いサービスとはいえない自治体が少なくない印象です。
日本全国の自治体において既に実施されたことがあるサービスの例を列挙すると、下記のとおりです。
登録証提示による行政サービスの例
| 住宅 | ・公営住宅への同居申込 ・新生活の家賃補助 ・住宅ローンの利息補助 |
|---|---|
| 税 | ・住民税証明書の交付 ・保険料の納付相談 |
| 防災 | ・災害見舞金 ・被災証明書等の交付 ・仮設住宅への入居 |
| 環境 | ・公営墓地の使用 |
| 困窮者支援 | ・生活困窮者自立相談支援 ・住居確保給付金 ・生活保護の認定 ・DV相談 |
| 介護 | ・要介護認定代理申請 ・介護施設負担額軽減の判定 |
| 子育て | ・保育所等の利用 ・保育所等の送迎者登録 ・就学困難者への就学援助 |
なお、登録証の提示がなくても配偶者と同様の扱いで利用できる行政サービスもあります。上記に例示したサービスの中でも、自治体によっては登録証の提示なく利用可能なものが多数含まれます。
親切な自治体は、登録証提示の要否を分けて利用可能な行政サービスを一覧表で紹介しています。例えば名古屋市や広島市です。
>>名古屋市公式サイト「名古屋市ファミリーシップ制度 制度の内容」
パートナーシップ登録のメリットを把握する上では、登録証の提示が必須なのかという点にも着目して確認されるとよいでしょう。
都道府県と市区町村のパートナーシップ制度の関係
「都道府県」と「その都道府県内の市区町村」の双方がパートナーシップ制度を導入している場合、そのどちらかで登録することも、両方で登録することも可能です(各自治体の登録条件を満たすことはもちろん必要です)。
両方で登録すれば、両方の自治体での行政サービスを受けることが可能になります。
さらに、東京都などは、都内の多くの自治体(足立区や町田市など)と協定を結び、都の登録証を取得していなくても、区や市の登録証を提示しさえすれば、都のほとんどの行政サービスを受けることも可能になっています。
お住まいの自治体のホームページ等で、受けられるサービスを確認するときは、都道府県と市区町村の両方を確認し、また、その連携の程度も確認されることをお勧めします。
東京・大阪・愛知県のパートナーシップ制度
東京のパートナーシップ制度
東京都においてパートナーシップ登録(宣誓)をすることで受けられる主な行政サービスは、以下のとおりです。
・公営住宅への共同入居
・里親制度
・犯罪被害者等の支援事業
・霊園貸付事業
大阪のパートナーシップ制度
大阪府においてパートナーシップ登録(宣誓)をすることで受けられる主な行政サービスは、以下のとおりです。
・公営住宅への共同入居
・里親制度
・生活困窮者自立支援制度
愛知県のパートナーシップ制度
愛知県においてパートナーシップ登録(宣誓)をすることで受けられる主な行政サービスは、以下のとおりです。
・公営住宅への共同入居
・犯罪被害者等の支援事業
>>詳しくは愛知県公式サイト「愛知県ファミリーシップ宣誓制度について」を参照
パートナーシップ制度の限界
法的効力がない
-この章の目次-
3-1-1.遺産相続でのデメリット
3-1-2.税や社保でのデメリット
3-1-3.貞操義務でのデメリット
3-1-4.財産分与でのデメリット
3-1-5.子供の親権でのデメリット
3-1-6.在留資格でのデメリット
遺産相続でのデメリット
パートナーシップ制度で解決できない大変大きな問題は、相続権がないことです。
民法の遺産承継制度はそのほとんどが対象を親族に限定しているため、パートナーシップ制度に登録しても対象外のままです。
唯一、「相続人不存在」という制度があり、亡くなった方と生計を共にするなど、特別の縁があった人(特別縁故者)が遺産を承継する道を残しています(民法958条の2)。
パートナーシップ制度に登録すれば、その特別縁故者として裁判所に認定されやすくはなるでしょう。

しかし、「相続人不存在」という名前のとおり、特別縁故者が遺産を承継できるのは、亡くなった方に相続人となるべき親族が誰もいないというレアケースに限定されています。
具体的には、亡くなった方に兄弟がおらず、かつ、亡くなった方のご両親も既に他界しているようなケースです。
つまり、パートナーシップ制度への登録だけでは、大半のケースで1円も遺産をもらい受けることができません。
そのため、遺言書や養子縁組など別の法的制度を活用して相続対策をしておく必要があります。
遺言書の重要性については、下記の記事で詳しく解説しているので、よければぜひご覧ください。
税金や社会保険でのデメリット
カップルのどちらかの収入が低くても、所得税や住民税の配偶者減税を受けたり、社会保険の扶養に入ることはできません。
しかしこの面では、子どもがいなくて共働きの多い同性カップルでは、二人とも一定程度の収入があることが多く、デメリットに映らないことも多いかと思います。
住民票の続柄と扶養の可能性
社会保険の扶養については、同性婚が認められない前提であっても、将来的には同性パートナーも扶養に入ることが可能になるかもしれません。
社会保険は税法と異なり、結婚届を出していない男女の事実婚の配偶者も、住民票の続柄に「妻(未届)」「夫(未届)」と記載されていれば扶養に入ることが可能です。
まだ少数ですが一部の自治体では、同性カップルの住民票について、パートナーシップ制度の利用を条件に、同様の夫婦としての記載を認める取組みを始めています(東京都世田谷区・中野区など)。
>>世田谷区公式サイト「パートナーシップ宣誓等を行った方の住民票の続柄変更に関する手続」
国は同性パートナーへの扶養認定に反対の立場ですが、今後も男女の事実婚と同性カップルの事実婚を同様に扱う流れは強まるでしょうから、同性婚よりも早く認められる可能性は十分あると言えるでしょう。

貞操義務でのデメリット
パートナーシップ制度に登録しても、結婚と異なり「貞操義務(浮気をしない義務)」は生じません。
そのため、万一浮気をされてしまっても、パートナーやその浮気相手に慰謝料を請求することはできません。
ただし、同性パートナーとの関係が異性間の事実婚(内縁)に近い状態に達していれば、異性間に準じて慰謝料を請求することが可能です(宇都宮地裁真岡支部令和元年9月18日判決)。
この裁判例は女性同士のカップルでの事案であり、100万円の慰謝料が認められました。
このような「同性間の事実婚」と認められるためには、単なる同棲では足りず、「婚姻意思」(夫婦として生きていく意思)が外観からも分かるような形で、結び付きの強い共同生活を送っていると認定される必要があります。
この認定は、下記のような諸事情を加味して総合判断されますが、パートナーシップ制度への登録はその一事情として加点評価されるでしょう。
同性事実婚の認定事情
・3年以上の同居
・家計の同一
・住民票の同一世帯
・同性婚可能な国に出向いて結婚
・結婚式や披露宴の開催
・2人の関係の周囲へのカミングアウト
・共同生活のための住居購入
財産分与でのデメリット
パートナーシップ制度に登録したカップルの関係が万一破綻してしまっても、「財産分与」を請求することはできません。
結婚した夫婦の離婚の場合であれば、一方が専業主婦(夫)のケースも含め、夫婦が共同生活を営む間に築いた財産の原則2分の1の分与を請求することができますので、その差は大きいですね。

それでは、この点も前記の浮気慰謝料のように、同性パートナーとの関係が異性間の事実婚(内縁)に近い状態に達していれば、請求可能になるのでしょうか。
残念ながら、現在の裁判例では否定されています(横浜家庭裁判所令和4年2月14日判決)。
この裁判例は、結婚が異性間でしか認められていないのだから事実婚(内縁)も認められず財産分与は不可能と断じています。
しかし、同性カップルの財産分与に関する裁判例は少なく、前記の浮気慰謝料での裁判例のように同性カップルの共同生活関係も法的保護に値すると判断する裁判官もいますので、今後は別の判断がなされる可能性も十分にあります。
とはいえこの点も、結婚と同様に確実に財産分与の権利を生じさせたい場合は、パートナーシップ「契約」(準婚姻契約)を締結し、財産分与に関しても取り決めておくのがよいでしょう。
子どもの親権でのデメリット
親権とは、未成年者の教育監護権や財産管理権、契約等代理権を含む権利です。
特にレズビアンのカップルの場合は連れ子等で子どもがいるケースも稀ではなく、親権は非常に重要な問題ですが、パートナーシップ制度に登録(宣誓)しても親権について一切の効力を及ぼすことはできません。
結婚した夫婦のように共同親権を行使できないのはもちろん、同性カップルのお二人のうち子どもの実親(血の繋がった親)である方が万一亡くなった場合、親権を行使できる者が不存在となりますので、子どもの財産管理など様々な面で不都合が懸念されます。
この点は、遺言書で対策が可能です。遺言書で「未成年後見人の指定」という親代わりの指定が可能なので、実親でないパートナーを未成年後見人に指定することを検討しましょう。
在留資格でのデメリット
市外に引っ超すと利用不可
一部自治体では費用が結構かかる
パートナーシップ制度への登録自体は無料ですが提出書類の準備にそれなりの費用がかかる自治体があります。
特に提出書類に公正証書が含まれる自治体は高額になります。
東京23区を例に挙げると、渋谷区や港区ではパートナーシップ契約(準婚契約)の公正証書(港区は公証人の署名認証でも可)を提出する必要があり、作成には13,000円(諸雑費を含めると約15,000円)の公証役場手数料がかかります。
さらに渋谷区では、パートナーシップ契約の他に、任意後見契約の公正証書も原則提出する必要があり、それらの契約の公正証書の作成に合計65,000円前後の公証役場手数料がかかります。

このように渋谷区では費用が一定程度かかるので、それが権利擁護のハードルにならないように助成金制度を設けて、割当ての予算が続く限りは大部分を補填できるようにしているようです(令和7年5月30日現在)。
>>渋谷区公式サイト「渋谷区パートナーシップ証明書取得助成金」
パートナーシップ制度に併せて準婚姻契約を公正証書で準備することで、結婚した男女間に近い権利義務をパートナーとの間に発生させることが可能です。
そのため必要費と考えることも可能ですが、男女間では無料の結婚届を出すことでそれらの権利義務を発生させることができるので、それとの対比の面では費用負担がデメリットと言えるでしょう。
パートナーシップ制度のご利用を検討される際は、お住まいの自治体のホームページで、受けられるサービスと併せて必要書類も早めに確認されることをお勧めします。
パートナーシップ制度のよくあるQ&A
-この章の目次-
賃貸でパートナーシップ制度は有効ですか?
公営住宅の賃貸では有効です。パートナーシップ制度を導入している自治体では、共同入居を認めている自治体が多数です。
他方で、民間の賃貸での有効性は限定的だと思います。
大家さんとしては、①賃料をきちんと払ってくれて、②綺麗に使ってくれそうであれば、同性の2人が入居するとして、その二人が事実婚の関係にあるのかどうかは重要な審査対象ではありません。
レズビアンのカップルの方がゲイのカップルよりも入居しやすいという話もたまに聞きますが、女性2人の方が綺麗に使ってくれそうだから、というところだと不動産業者から聞きました。
そのため、事実婚の有無よりも、収入や職業、年齢や性別、保証人の有無といった他の要素の方が重要視されるでしょう。その意味でパートナーシップ登録証の効果は限定的といえると思います。
ゲイのカップルであっても、高齢でなく安定した職業に就いている場合、不動産を探すのにそこまで苦労した(同性カップルという理由で賃貸をほとんど断られる)という話はパートナーシップ制度施行前から聞いたことがありません。

病院での看護でパートナーシップ制度は有効ですか?
公営病院では有効なことが少なくないといえます。パートナーシップ制度を導入している自治体では、配偶者に近い対応を公営病院に課している自治体が一定程度あります。例えば大阪府堺市では明示的にその旨の公表もしています。
他方で、民間の病院での有効性では限定的だと思います。
詰まるところ、万一患者が亡くなった場合に慰謝料等の法定相続人となる親族でなければ協力対象にならないという判断がなされる可能性は十分あります。
そのため、パートナーシップ制度への登録だけではなく、医療の面会や手術等への同意に関する契約を締結しておくべきです。
パートナーシップ「契約」においてその条項を設けて、第三者への有効性の証明のためその契約を公正証書にしておくのも対策にはなりますが、医療に関して独立の手厚い契約(医療同意委任契約)を締結しておくのがベストです。
医療同意委任契約の重要性については下記の記事で詳しく解説しているので、よければぜひご覧ください。
お葬式や遺骨を守る面でパートナーシップ制度は有効ですか?
かなり限定的といえるでしょう。法的には他人のパートナーよりも親族を優先すべきという判断が、葬儀屋さんや裁判所においてなされる可能性は低くないと思います。
この点も、死後事務や、遺骨を含む祭祀財産の承継について、パートナーシップ「契約」において条項を設けて、第三者への有効性の証明のためその契約を公正証書にしておくのも対策にはなりますが、遺言書や死後事務に関して独立の文書を用意しておくのがベストです。
そのため、当事務所では同性カップルにお勧めの「法律文書3点セット」に遺言書と死後事務委任契約を含めています。

パートナーシップ制度に登録すると家族にバレますか?
パートナーシップ制度は、基本的に公表や第三者の閲覧を前提とした制度ではなく、公務員には秘密保持義務があるため、制度登録それ自体で親族等にバレるリスクは低いでしょう。
例えば、小田原市では「宣誓者の秘密が明らかにされることはありません」と明記し、アウティング(本人の許可なく暴露すること)とならないように十分な配慮の姿勢を示しています(出典「パートナーシップ宣誓制度利用ガイドブック(令和7年4月1日~)」 )。
しかし、パートナーシップ制度の目的は、民間や行政において夫婦同様の各種サービスを受けることにあり、そのためには各サービスの窓口に登録証の提示が必要になるため、パートナーシップ制度を活用すればするほど秘密保持にも限界が出てくるといえるでしょう。
性的指向という機微な個人情報について、できる限りプライバシーを守りながらパートナーとの将来に法的に備えたいという方にも、遺言書等の「3つの法律文書」サービスをお勧めしていますので、詳しくは下記のページもご覧いただければ幸いです。
パートナーシップ制度申請の必要書類や手間は多いですか?
パートナーシップ制度の申請に必要な書類は、概ね以下のとおりです。
ただし、自治体によって必要書類やその発行手数料が異なることがあります。特に大きな違いとして、一部の自治体では高額な公正証書が必要になることは前記のとおりです。
パートナーシップ制度申請の必要書類
・住民票(1通300円)
・戸籍謄本(1通450円)
・社員証(通称名での登録を希望する場合)
まとめ
住宅ローンのペアローンを検討されているカップルや、登録証の提示により手厚い行政サービスが認められている自治体にお住まいの方は、パートナーシップ契約ないし登録制度によるメリットは少なくありません。
そのため、まずはお住まいの自治体のホームページをご確認されることをお勧めします。
パートナーシップ制度のデメリットとして、法的効力はなく相続対策や親権への手当にはならないので、遺言書や養子縁組といった法的制度活用も検討する必要があります。
パートナーとの関係を「法的に強くする」ための実効的な備えとして、当事務所では遺言+医療同意委任+死後事務委任の「3つの法律文書」をお勧めしています。
本サービスの担当・執筆者

長野 正義(ながの まさよし)
保有資格
- 司法書士(東京司法書士会所属/登録番号:第8353号)
- 個人情報保護士
- 知的財産管理技能士(二級)
経歴等
昭和57年 東京都文京区 生まれ
平成16年 中央大学 法学部法律学科 卒業
平成22年 司法書士試験 合格
平成23年 簡易裁判所の訴訟代理権試験 合格
一般企業の法務部、大手の司法書士法人等を経て、現職。
メッセージ
裁判所への書類や企業間契約書など、法律文書の作成を専門として15年程の実務経験があります。定型文中心の行政申請業務が主流の司法書士業界では珍しい経歴かもしれません。
現在は特に、同性カップルの法的課題に対する支援に注力しており、遺言書や医療同意委任契約など、法的効力や実務上の実効性を重視したサポートを行っています。
「一人の人生の大事な局面に関わる責任」を重く受け止め、依頼者の思いに応える成果を提供できるよう、今後も研鑽を続けて参ります。
好きな言葉
・至誠一貫 ・第一義
趣味
・茶道(裏千家/許状:行之行台子)