相続・遺言に関する手続の総合案内(合同会社つなぐ(FP)×司法書士法人黒川事務所×行政書士黒川事務所の運営サイト)
不動産相続で払う税金、相続税の計算方法や控除制度について
不動産を相続したら、相続税が発生する可能性があります。ただしすべてのケースで相続税が発生するわけではありません。
また相続税の申告や納税には「期限」もあるので、土地や建物の相続人になったら早めの対処が肝心です。
今回は不動産を相続したときにどういった税金がどのくらいかかるのか、専門家が解説します。
実家やマンションなどの不動産を相続された方はぜひ参考にしてみてください。
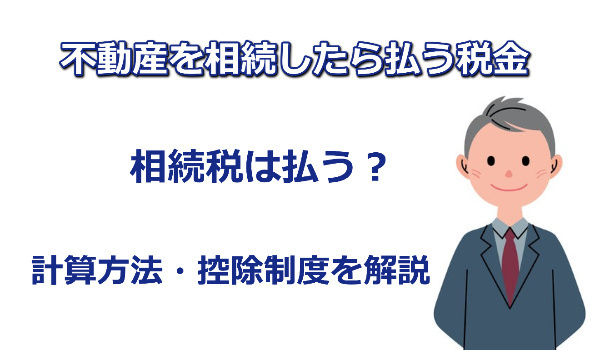
1.相続税が発生するケース
不動産を相続したときに高額になりやすい税金が「相続税」です。
相続税は、一定額以上の遺産を相続したときにかかります。
不動産を相続したからといって必ず相続税がかかるとは限りません。相続税には「基礎控除」が適用され、遺産の評価額が基礎控除を下回る場合には相続税はかからないのです。
相続税の基礎控除
相続税の基礎控除の金額は、以下のとおりです。
3,000万円+法定相続人数×600万円
たとえば配偶者と子ども3人が相続人になる場合、基礎控除の金額は3,000万円+600万円×4名=5,400万円となります。
この事例では遺産額が全体で5,400万円を下回っていたら相続税はかかりません。
2.相続税の計算方法
相続税はどのようにして計算するのか解説します。
遺産の評価を行う
まずは遺産を評価しなければなりません。
不動産については定められた計算方法があります。
土地の相続税評価方法
土地の相続税評価額は「相続税路線価」によって評価します。相続税路線価とは、宅地などの市街地にあって道路に面している土地の1㎡あたりの単価です。
路線価を調べて土地の面積を掛け算すると、基本的な土地の相続税評価額が明らかになります。
路線価の設定のない場所では「評価倍率」を利用します。評価倍率とは、固定資産税評価額に一定の数字を掛け算して相続税評価額を求める方法です。
相続税路線価や評価倍率によって求められた金額は、時価の8割程度となるのが一般的です。さらに、土地を貸し付けている場合には借地権価額を差し引けるので、土地の評価額はより低くなります。
※土地については、小規模宅地等の特例の適用があれば最大80%の評価減になるケースもあります。
建物の相続税評価方法
建物の相続税評価額は「固定資産税評価額」を用いて求めます。
固定資産税評価額は時価のおおむね7割程度になるのが一般的です。
マンションやアパートなどの物件を賃貸している場合、借家権価額や底地の借地権価額を差し引けるので、さらに評価額を下げられます。
以上のように不動産の評価額は現金資産より低くなるケースが多いので、生前に相続税の節税のために不動産を購入される方も多数おられます。
遺産評価額から負債や葬儀費用を差し引く
遺産の評価額が出揃ったら、負債や葬儀費用の金額を差し引きましょう。
たとえば以下のような負債の金額を差し引けます。
- 借入金
- 未払い家賃
- 未払いの買掛金
- 未払いの水道光熱費
- 未払いの通信料
- 滞納税、滞納保険料
- 損害賠償債務
基礎控除を差し引く
こうして算出できた金額から「相続税の基礎控除」を差し引きましょう。
これで相続税の課税対象額が明らかになります。
たとえば、現金や不動産の合計額が1億円のケースで配偶者と子ども2人が相続人になる場合、1億円-4,800万円=5,200万円が課税対象価額となります。
法定相続分に割りつけて相続税額を計算
課税対象金額が出たら、法定相続分に割り付けて相続税額を計算します。
実際に相続する割合ではなく、まずは法定相続分に応じて計算しなければならないので間違えないように注意しましょう。
法定相続分に掛け算すべき相続税率は以下のとおりです。
相続税率と速算表
| 法定相続分に応じた金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | なし |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
たとえば課税対象金額が5,400万円で配偶者と子ども2人が相続する場合、以下のとおりです。
配偶者の相続税 課税対象価額5,400万円×2分の1=2,700万円
2,700万円×15%-50万円=355万円
子どもそれぞれの相続税 課税対象価額5,400万円×4分の1=1,350万円
1,350万円×15%-50万円=152万5000円
相続税額を合算
各法定相続人の相続税額がわかったら、税額を合算します。これがそのケースでかかる相続税額です。
上記の例の場合、355万円+152万5000円×2人分=660万円
全員で660万円分の相続税を払わねばなりません。
実際の取得割合に応じて負担額を計算
相続税額を実際の遺産相続割合に応じて割り付けます。
たとえば配偶者が全部相続する場合には、相続税額は全額配偶者負担となります。
控除を適用
相続税には各種の控除があるので、控除を適用して最終的な相続税額を求めます。
たとえば配偶者の場合、以下の多い方の金額までは相続税がかかりません。
- 法定相続分
- 1億6千万円
上記の事案でも、配偶者が5,400万円の全額を相続するなら相続税を払う必要はありません。子どもが相続する場合には一定の相続税額がかかります。
相続税の2割加算
相続人から遠い親族や親族でない人が遺産を受け継ぐ場合、相続税が2割加算されます。たとえば祖父母や兄弟姉妹、甥姪、代襲相続人ではない孫などが相続する場合などです。
税額計算の際に間違えないように注意しましょう。
相続税控除の制度
相続税を控除できる制度として以下のようなものがあります。
・配偶者控除
配偶者が相続人となる場合、法定相続分または1億6千万円までの相続には相続税がかからないとする控除制度です。
・未成年者控除
未成年者が相続人となる場合には、成人するまでの期間に応じて相続税が控除されます。
未成年者が満18歳になるまでの年数1年(1年未満切上げ)につき10万円で計算した額
・障がい者控除
障がい者が相続人となる場合には、85歳になるまでの年数分相続税が控除されます。
障がい者が満85歳になるまでの年数1年(1年未満切上げ)につき10万円(特別障害者は1年につき20万円)で計算した額。
・贈与税額控除
相続発生前3年間に贈与を行って相続税がかかるケースでは、すでに支払った贈与税額について相続税の控除を受けられます。
・相次相続控除
3.相続税の申告方法と期限
相続税がかかるケースでは、税務署へ相続税の申告をして納税しなければなりません。
納付先は管轄の税務署です。郵送や持参で申告書や遺産分割協議書などの必要書類を提出して税金を納付しましょう。
相続税の申告と納付には期限があり、「相続開始を知ってから10か月以内」とされています。過ぎてしまうと延滞税が発生し、不申告加算税などがかかってしまう可能性もあるのでくれぐれも遅れないように対処しましょう。
なお遺産に不動産が含まれている場合、自分で相続税を計算すると間違ってしまう方が多数です。適正に評価できず税金を払いすぎてしまうケースも少なくありません。
5.固定資産税について
不動産を相続すると、毎年固定資産税が発生します。市街地の場合には都市計画税もかかる可能性があります。
不動産を活用しなくても税金はかかり続けるので、使わない土地やマンションなどがあれば売却を検討するのもよいでしょう。
監修者:黒川聡史

保有資格と所属団体
- 司法書士:東京司法書士会所属:登録番号4230号
- 行政書士:東京都行政書士会所属:登録番号第19082582号
- FP(FP技能士1級:日本FP協会CFP®)
経歴
昭和51年生まれ。平成13年司法書士と行政書士の資格取得後、都内司法書士事務所で勤務。平成19年に独立開業し、平成30年に法人化し司法書士法人黒川事務所となる。また、ファイナンシャルプランニング技能士1級及びCFP®を取得しFPとしても活動している(合同会社つなぐ)。


