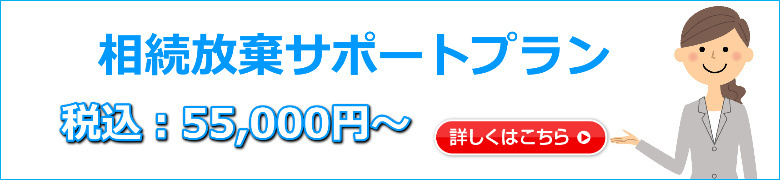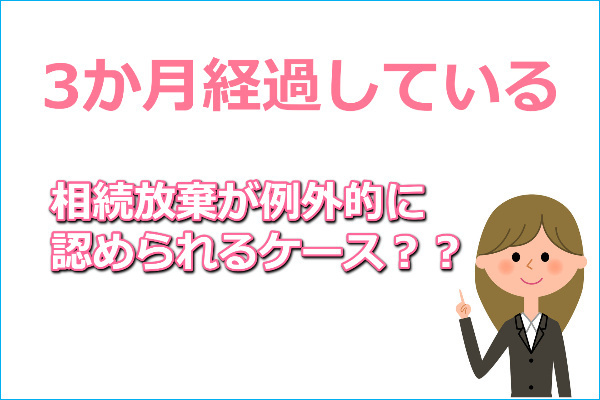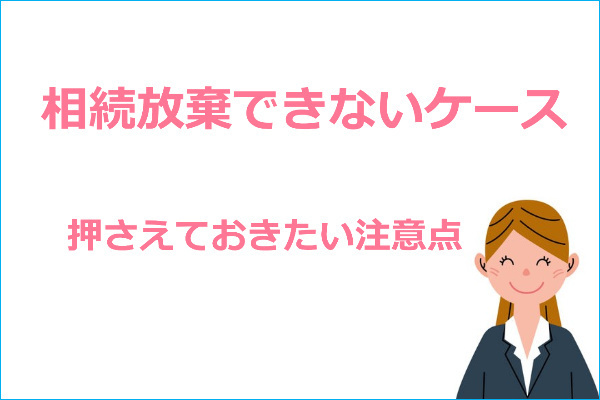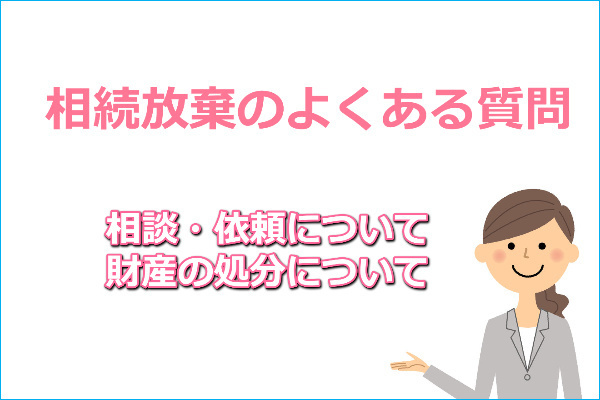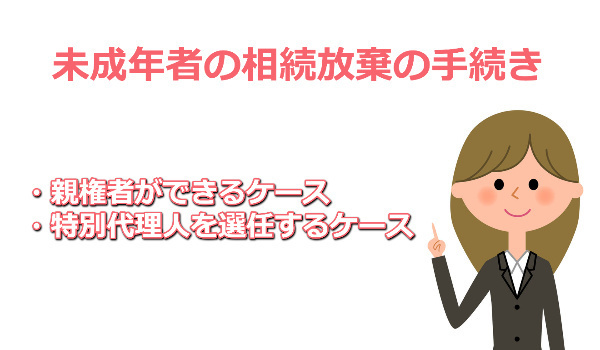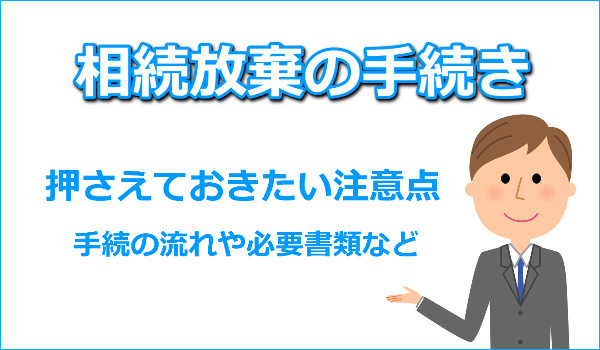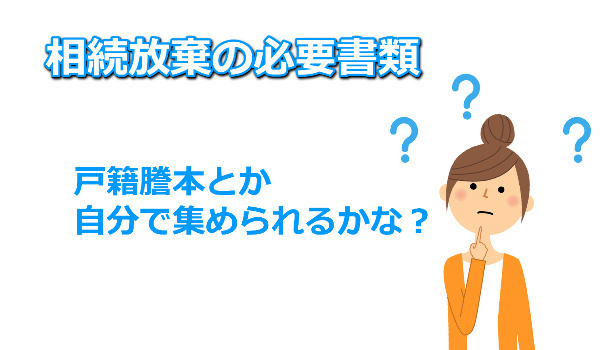相続・遺言に関する手続の総合案内(合同会社つなぐ(FP)×司法書士法人黒川事務所×行政書士黒川事務所の運営サイト)
相続放棄申述書とは?書き方や注意点を司法書士が解説
相続放棄するときには「相続放棄申述書」を作成しなければなりません。
不用意なことを書いてしまうと相続放棄が認められなくなる可能性もあるので、相続放棄申述書は非常に重要な書類です。
今回は相続放棄申述書の書き方や注意しなければならないケース、対処方法について、相続の専門家が解説します。
これから相続放棄しようとしている方はぜひ参考にしてみてください。
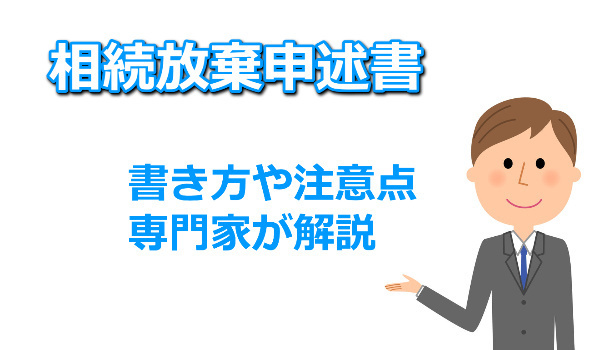
目 次
1. 相続放棄申述書とは
2-1. 書式を入手
2-2. 日付の記入、申述人の署名押印
2-3. 申述人の欄に記入
2-4. 法定代理人について
2-5. 被相続人の情報
2-6. 相続の開始を知った日
2-7. 放棄の理由
2-8. 相続財産の概略
4-1. 相続開始から3か月が経過している
4-2. 後順位の相続人がいる
5-1. 手間が省ける
2-1. 書式を入手
相続放棄申述書には、家庭裁判所の定める書式があります。まずはダウンロードして書式を入手しましょう。
成人のケースと未成年者のケースで書式が分かれているので、該当する方をお使いください。
成年
https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_13/index.html
未成年
https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_13_02/index.html
2-2. 日付の記入、申述人の署名押印
2-3. 申述人の欄に記入
2-4. 法定代理人について
2-5. 被相続人の情報
2-6. 相続の開始を知った日
相続放棄申述書には「申述の理由」という欄があります。
中でも「相続の開始を知った日」が非常に重要です。
相続放棄は「自分のために相続があったことを知ってから3か月以内」に申述しなければなりません。この期間を「熟慮期間」といいます。
一般的に「自分のために相続があったことを知る」日は「相続の開始を知った日」と一致するケースが多数です。そこで「相続の開始を知った日」から3か月を経過していると「熟慮期間を過ぎている」と判断されて相続放棄が受理されない可能性が高まります。
「相続開始を知った日」の欄に記入する際には、3か月を超えているかどうかに関して慎重になりましょう。もしも3か月を超えている場合、被相続人の死亡の事実を知らなかったなどの事情がないと相続放棄が受理されないリスクが高まります。
2-7. 放棄の理由
2-8. 相続財産の概略
3. 相続放棄照会書と回答書について
相続放棄申述書を提出しただけで相続放棄の手続が終わるわけではありません。
申述書が受け付けられてからしばらくすると、家庭裁判所から「相続放棄の照会書と回答書」が送られてきます。
こちらの回答書へ不備なく記入して返送しないと相続放棄が受理されません。
特に「相続開始から3か月が経過している場合」には裁判所が回答内容を慎重に検討するので、申述人としても慎重な対応が要求されます。
以下で相続放棄回答書に書くべき事項や書き方をご説明します。
【相続放棄回答書で聞かれる事項】
相続放棄の回答書に書く内容は以下のようなものです。
被相続人が死亡した事実を知った日
被相続人の死亡を知った日から3か月を経過していると相続放棄が受理されなくなる可能性があります。
把握している遺産内容
把握している範囲で良いので、正確に書きましょう。申告せずに使い込むと相続放棄が認められなくなるので、絶対にやってはなりません。
生前の被相続人との関係
死亡後3か月が経過していても、生前の被相続人とのかかわりが薄ければ相続放棄が認められる可能性もあります。
相続放棄が真意にもとづくかどうか
4. 相続放棄申述書や回答書を書くときに注意が必要なケース
4-1. 相続開始から3か月が経過している
5. 相続放棄を専門家に依頼するメリット、依頼すべきケース
5-1. 手間が省ける
5-2. リスクの高いケースでも受理される可能性が上がる
被相続人の死亡後3か月が経過している場合や、被相続人の死亡を知ってから3か月が経過してしまっている場合のように、相続放棄が受理されないリスクが高い事案があります。
こういったケースで素人対応をすると危険です。専門家に法律的な見地から相続放棄が受理されるべき事情を説明してもらわねばなりません。
司法書士などの専門家に依頼するとリスクの高いケースでも相続放棄が受理される可能性が大きくアップするので、自己判断せずに対応を相談しましょう。