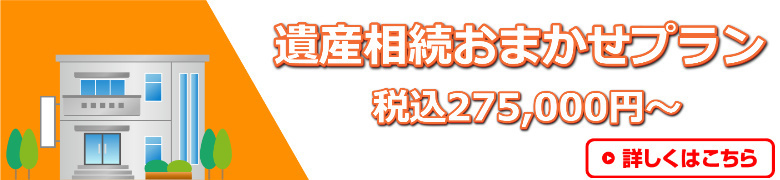相続・遺言に関する手続の総合案内(合同会社つなぐ(FP)×司法書士法人黒川事務所×行政書士黒川事務所の運営サイト)
離婚した前妻の子供がいる場合の相続の進め方と相続対策について
離婚経験のある方の場合、「前妻(前夫)との間に子ども」がいるケースがよくあります。
前妻や前夫との間の子どもにも相続権が認められます。
何の対策もしなければ、死亡時のご家族と共同で遺産分割協議を行わねばならず、大きなトラブルになってしまうケースも少なくありません。
今回は離婚した前妻や前夫との間に子どもがいる場合の相続の進め方と生前の相続対策についてご説明します。
離婚経験のある方やその配偶者の方は、ぜひ参考にしてみてください。
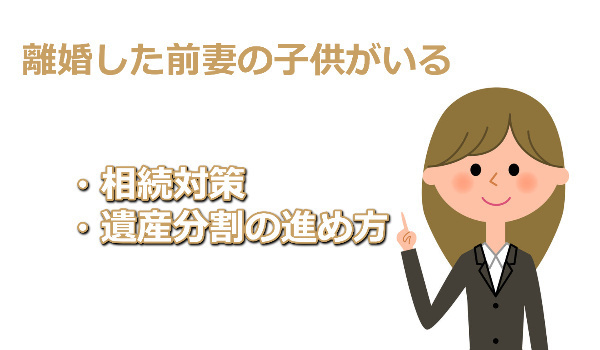
目 次
1-1. 子どもには相続権がある
1-2. 前妻・前夫との子どもの相続分
2-1. 死亡時の家族である妻や子どもが遺産を独占しようとする
2-2. 前妻の子どもと連絡が取れない
2-3. 遺産分割協議で合意できない
2-4. 前妻の子どもが未成年で前妻が遺産分割協議に参加する
2-5. 遺留分侵害額請求
3-1. 遺言書を作成する
3-2. 遺留分対策方法
1. 前妻や前夫との間の子どもにも相続権がある
1-1. 子どもには相続権がある
2. 前妻の子どもがいる場合によくあるトラブル
2-1. 死亡時の家族である妻や子どもが遺産を独占しようとする
2-2. 前妻の子どもと連絡が取れない
2-3. 遺産分割協議で合意できない
2-4. 前妻の子どもが未成年で前妻が遺産分割協議に参加する
2-5. 遺留分侵害額請求
3. 前妻の子どもがいる場合の生前の遺産相続対策方法
3-1. 遺言書を作成する
まずは遺言書の作成が必須です。
何もしなかったら、死亡時の家族の子どもと同じだけの遺産を前妻の子どもに渡す必要があります。
今のご家族に遺産を残したいのであれば、遺言書でできるだけ多くの遺産を今の家族へ遺すように指定しましょう。
たとえば自宅を今の家族へ相続させる内容にしておけば、前妻の子どもが家の持ち分を取得をするということにはなりません。
前妻の子どもの「遺留分」
前妻の子どもには「遺留分」が認められます。遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる最低限の遺産取得割合です。
子どもが相続人になる場合には遺留分割合は2分の1となります。つまり前妻の子どもには最大2分の1の遺留分が認められるのです。
遺留分を侵害すると、権利者は侵害者へ「遺留分侵害額請求」というお金の請求ができます。
遺留分を請求されると侵害者は遺留分侵害額を権利者へ払わねばなりません。手元に資金がなければ、遺産を売却して払わねばならない可能性もあります。
なお遺留分侵害が発生する可能性のある行為は以下の4つです。
- 遺言書による遺贈
- 相続開始前1年以内の贈与
- 遺留分を侵害すると知って行われた贈与
- 相続人に対する相続開始前10年以内の贈与
3-2. 遺留分対策方法
遺留分対策としておすすめは以下の2つの方法です。
前妻の子どもにも遺留分相当の遺産を遺す
遺言書で前妻の子どもにも遺留分相当の遺産を遺しましょう。そうすれば、前妻の子どもの遺留分を侵害しないので、遺留分侵害額請求が起こりません。
死亡時の家族に生命保険金を受け取らせる
死亡時の家族(遺留分の侵害者)へ生命保険金を受けとらせる方法もあります。
まとまった金額の生命保険金を受け取らせると、死亡時の家族はそのお金で遺留分侵害額を払えるのでスムーズに遺留分トラブルを解決しやすくなります。
また生命保険金には高額な相続税控除も認められるので、節税メリットも期待できます。
監修者:黒川聡史

保有資格と所属団体
- 司法書士:東京司法書士会所属:登録番号4230号
- 行政書士:東京都行政書士会所属:登録番号第19082582号
- FP(FP技能士1級:日本FP協会CFP®)
経歴
昭和51年生まれ。平成13年司法書士と行政書士の資格取得後、都内司法書士事務所で勤務。平成19年に独立開業し、平成30年に法人化し司法書士法人黒川事務所となる。また、ファイナンシャルプランニング技能士1級及びCFP®を取得しFPとしても活動している(合同会社つなぐ)。