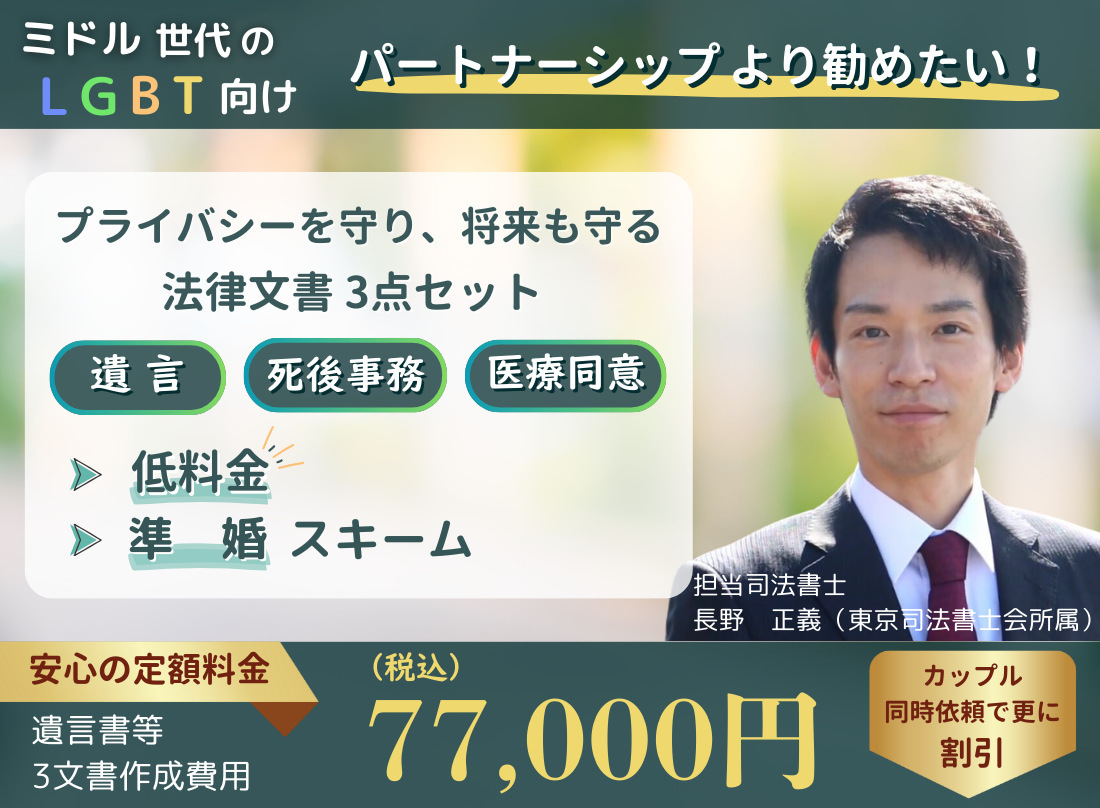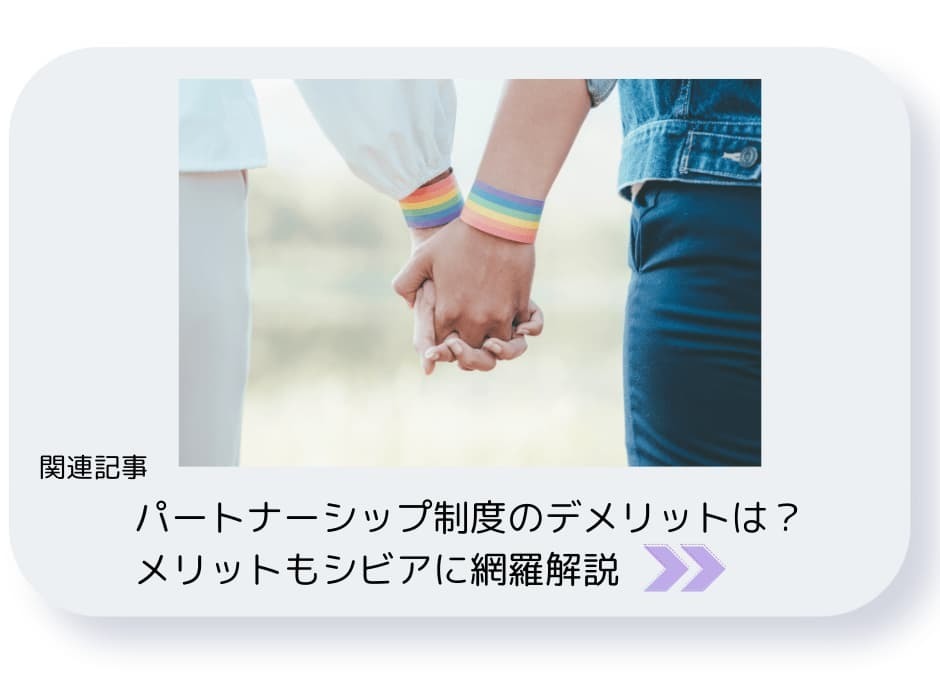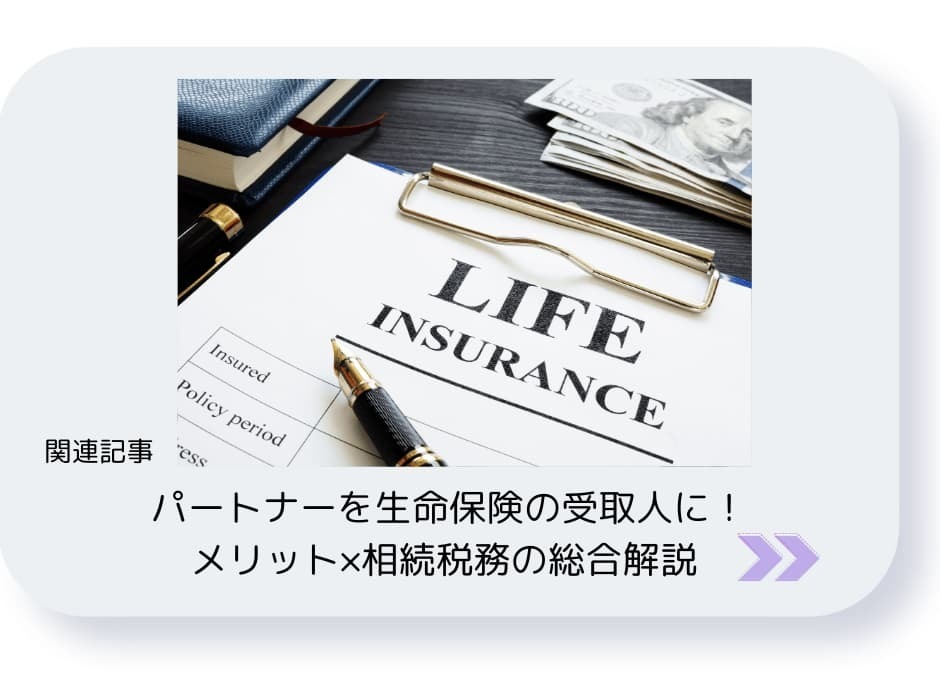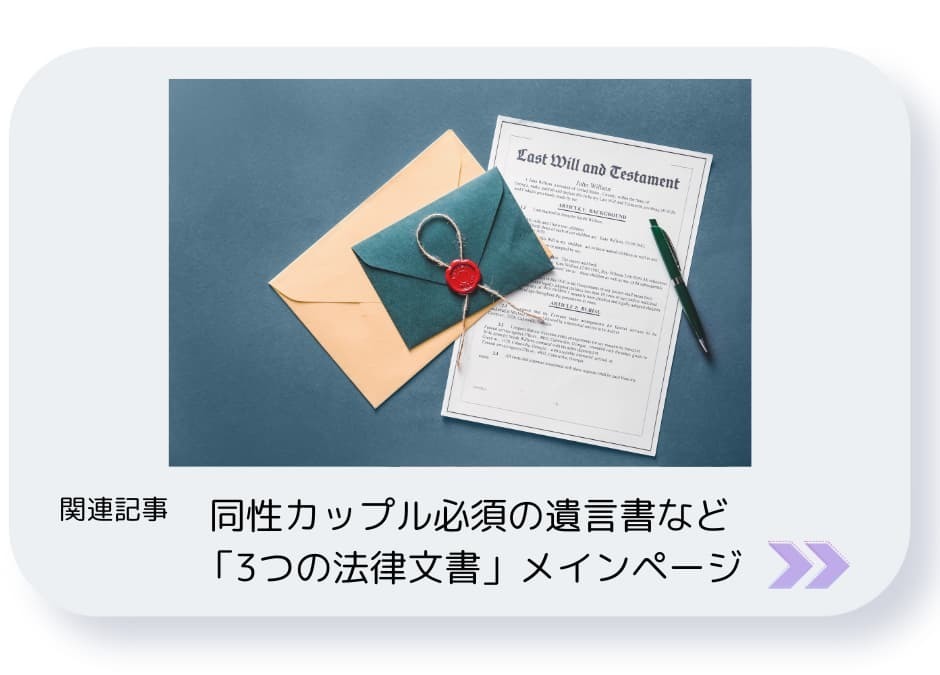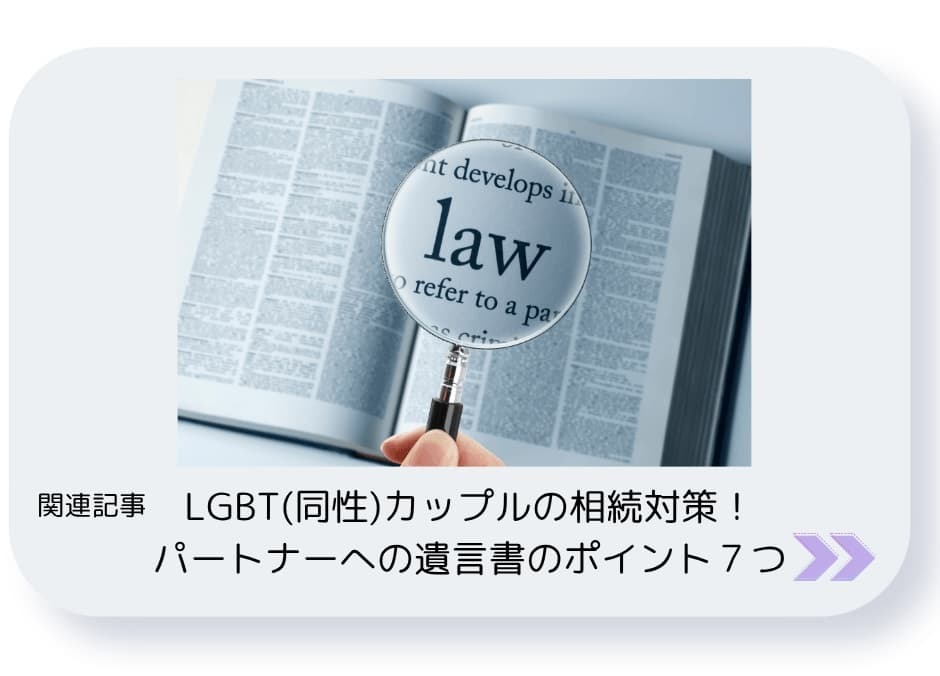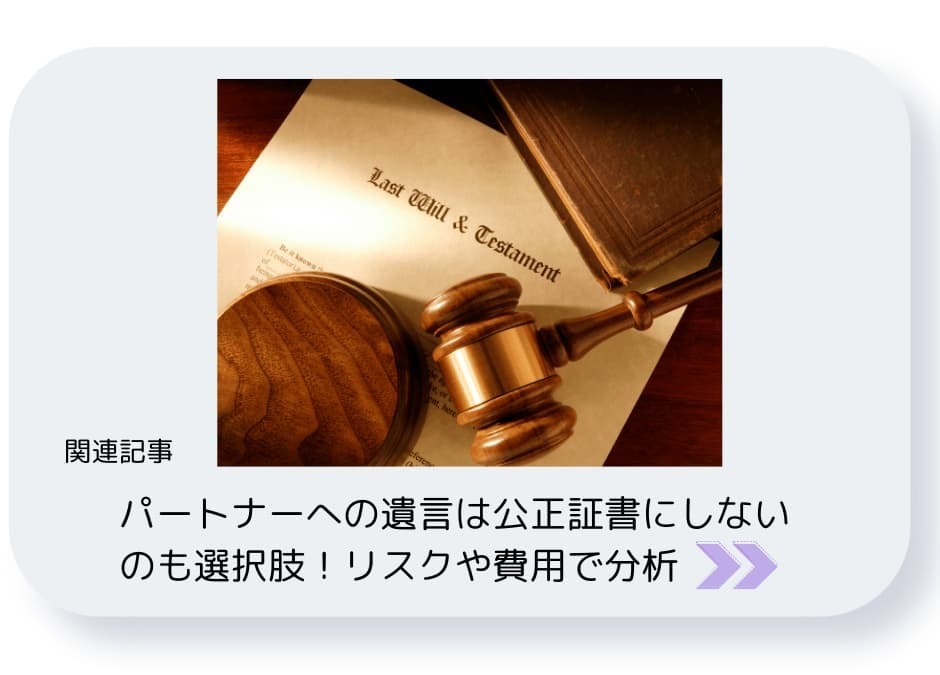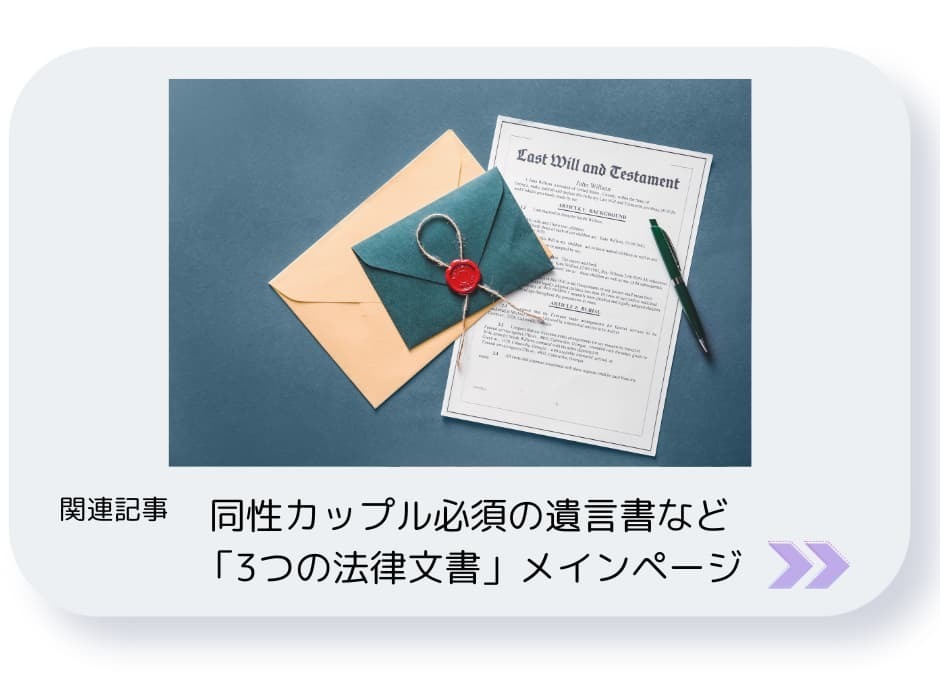相続・遺言に関する手続の総合案内(合同会社つなぐ(FP)×司法書士法人黒川事務所×行政書士黒川事務所の運営サイト)
合意契約に係る公正証書(同性パートナーシップ契約)の必要性を完全分析
最終更新日:2025年11月16日
「合意契約(同性パートナーシップ契約)の公正証書が本当に必要なのか、費用と併せて詳しく知りたい」
ゲイやレズビアンなど、LGBTの方で私の記事をご覧になっている方は、「合意契約に係る公正証書」という言葉を一度は目にしたことがあるかもしれません。
意味合いとしては、法的に結婚同等の関係を築くための契約のことですね。
この契約は異性間のカップルでも取り交わされることがあります。苗字の変更等を避けるために、あえて婚姻届を出さないケースです。しかし、今回は当事者を同性カップルの場合に限定して解説します。
今回の記事をご覧いただければ、合意契約の必要性や、その他の法的対策(医療同意委任契約・死後事務委任契約・遺言など)との関係、具体的な費用に至るまで、深くご理解いただけると思います。
これからの人生を共に過ごすことを誓ったカップルの方は、ぜひご覧ください。

合意契約の意味・呼び方
合意契約とは?
2人の間に結婚に近い権利義務を発生させることを主な目的として、民法が規律する夫婦間の条項などを盛り込んだ契約のことです。
盛り込む条項に特に制限はなく、自由に決めることができます(契約自由の原則)。
ただし、極端な内容を定めると公序良俗に反するものとして例外的に無効になります(民法90条)。
例えば、浮気に伴う慰謝料を1億円という著しい高額に設定するような定めです。
合意契約には重要事項のみ盛り込もう
上記のとおり合意契約中に何を盛り込むかは基本的には自由ですが、細かすぎる規定はあまりお勧めできません。
例えば、「お互いの誕生日は◯◯する」というような定めです。
契約というのは、一定の条件を満たしたら一定の結果が法的に強制されるという合意ですから、違反した場合のペナルティ(罰金や離婚原因への該当など)も規定ないし想定しなければなりません。
長年の共同生活の中で一定の軌道修正は見込まれるものですので、夫婦間の細かいルールを契約に盛り込むまでの必要があることは稀といえるでしょう。
合意契約がないとどうなる?(内縁など)
合意契約がない場合、一緒に生活している人との関係に法はどの程度の保護を与えてくれるのでしょうか。
この点を、同性カップルについて解説する前提として、まずは男女間の関係について分類整理すると下記のようになります。
男女間での共同生活の法的保護
| 同 棲 | |
|---|---|
| 意義 | 同居しているが、下記の内縁関係にまで至っていないカップル(典型例は、交際開始直後に同居したカップル) |
| 条件 | - |
| 効果 | なし(法的保護に値しない) |
| 内 縁 (事 実 婚) | |
| 意義 | 夫婦として生きていく意思(婚姻意思)があり、夫婦同然の共同生活を送っているが、婚姻届を提出していないカップル |
| 条件 | 下記のような事情の総合評価から、婚姻意思と夫婦共同生活の両方が客観的に存在すると認められる必要がある。 ・同居(一般的に3年以上) ・家計の同一 ・結婚式の挙式 ・冠婚葬祭に夫婦として出席 ・住民票の同一世帯員である |
| 効果 | 財産分与や慰謝料など、婚姻と同等の権利が広く認められる。 ただし、相続や苗字の変更など、婚姻届による戸籍制度を前提とした効果は認められない。 |
| 法 律 婚 | |
| 意義 | 結婚したカップル |
| 条件 | 婚姻意思に基づき、婚姻届を提出したカップル |
| 効果 | 相続権等も認められる |
同性カップルの合意契約の目的
-この章の目次-
3-1.目的① 夫婦間権利義務の創設
3-2.目的② 色々なサービスの利用
3-3.目的③ 他の性質の契約と合体
┗医療同意契約・死後事務委任契約
┗祭祀承継者の指定
┗死因贈与契約
3-4.目的③の補足 別文書がよい?
目的① 夫婦間権利義務の創設
(財産分与・慰謝料など)
合意契約での本来的目的は、夫婦間と同等の権利義務を発生させるということであり、具体的には以下のような規定を設けます。
・万一別れることになった場合の財産分与の定め
・正当な理由なく別れを切り出された側からの慰謝料請求の定め
財産分与の定めは、財産形成への貢献度に応じた平等を図るために、特に以下のようなケースのカップルにおいて必要性の高いものになります。
・カップルの一方がパート勤務や専業主婦(夫)で家事の大部分を担い、他方の仕事を支えているケース
・持ち家に同居していて、家の名義をカップルの一方の単独名義にしつつ、住宅ローンなどの居住費は他方も一部負担しているケース
また、慰謝料の定めについても、例えば「パートナーを愛しているけど昔浮気性だったのが少し心配」というようなケースでは、貞操義務などを具体的に明記することで、抑止力として機能するでしょう。
合意契約に最低限入れるべき条項
上記の財産分与の定めなど、合意契約に最低限入れるべき基本的な事項を以下に列挙します。
・婚姻意思の確認
・同居、協力、扶助の義務
・貞操義務
・婚姻費用の分担
・契約の解除事由
・財産分与
・慰謝料
いずれも同性婚関係を基礎付ける内容ですので、ご意向に反しない限りは盛り込んでおきましょう(裁判等で内縁関係成立の一資料にもなります)。
その上で、ご状況やご意向に応じて条項を追加していくと、バランスの取れた構成になります。
目的② 色々なサービスの利用
(パートナーシップ制度・住宅ローンなど)
契約というのは、第三者(契約当事者以外の者)に対しては効力が及びません。
2人の合意は2人を法的に拘束することはできても、他人に強制したり、違反の責任を追求することはできません。
しかし、契約を公正証書等で締結した場合には、2人の同性婚関係を客観的に明らかにする資料として外部に提示することは可能です。

そのような必要が生じる場面の典型例は、パートナーシップ制度への登録です。
一部の自治体では、一定の事項が記載された合意契約の公正証書がパートナーシップ制度登録の条件となっています。
東京都渋谷区はその代表例であり、必要な合意契約の作成方法がわかりやすく公表されています。
>>渋谷区公式サイト「渋谷区パートナーシップ証明 任意後見契約・合意契約公正証書 作成の手引き」
もう一つの典型例としては、住宅ローンの審査です。多くの金融機関が、同性カップルによる住宅ローンのペアローン等の条件として、合意契約の公正証書を求めています。
このほか、同性パートナーを生命保険の受取人に指定する際なども、合意契約の公正証書があれば手続がスムーズに進む保険会社が少なくありません。
目的③ 他の性質の契約と合体させ複数目的を達成
医療同意契約・死後事務委任契約
法的に親族になれない同性カップルは、パートナーが救急搬送された場合の面会や手術の同意、万一の場合の葬儀や役所への届出などを拒絶されるリスクがあります。
これらの対策としては、同性パートナーに予め医療関係の個人情報開示や治療方針決定の権限を付与する契約(医療同意委任契約)や、各種死後事務を委任する契約(死後事務委任契約)が有用です。
これらの契約は、独立文書で作成することも可能ですし、合意契約の一部として盛り込むことも可能です。
特に医療同意契約は合意契約に盛り込まれることが多いですね。
これらの契約の必要性については、以下の記事で詳しく解説しているのでよければご覧ください。
祭祀承継者の指定
自分の身に万一があったら、葬儀はパートナーに任せたい。位牌や遺骨の姿になっても、パートナーのそばにいてあげたい。
そのように思われるのでしたら、祭祀承継者を指定することが重要です。
位牌や遺骨など、祭祀財産は他の一般的な財産と異なるルールで承継されます。
具体的には、一般的財産のように法定相続人に承継されるわけではなく、承継先(祭祀承継者)について被相続人の指定があればそれにより、なければ家庭裁判所が決定することとされています(民法897条)。
祭祀承継者の指定方法に特に制限はありません。他の一般的財産と同じように遺言書の中で定めるのが一般的ですが、合意契約に盛り込むことも可能です。
祭祀承継者については以下の記事で詳しく解説しているので、よければご覧ください。
死因贈与契約
自分の身に万一があったら、同性パートナーに遺産を相続させてあげたい。
そのように思われる方は非常に多いと思いますが、結婚という方法が採れない中でも幾つかの法的対策の選択肢があります。
メジャーな方法である遺言や養子縁組のほか、死因贈与契約という方法も存在します。
死因贈与契約というのは、死亡した時に効力が発生する贈与契約です。
遺言による贈与(遺贈)も、死亡によって効力が発生するという点で共通しているため、民法は遺贈に関する規定を基本的に死因贈与契約に準用させています(民法554条)。
遺言と大きく異なる点の一つとして、形式について特に制限はありません。そのため、合意契約の一条項として盛り込むことも可能です。
しかし、あえて遺言ではなく死因贈与を選ぶ実益のあるケースは限られています。
死因贈与契約について詳しくは以下の記事をご覧ください。
目的③の補足 合意契約とは別文書の方がよい?
上記で述べた各契約ないし指定は、合意契約に盛り込むことも、独立文書で作成することも可能です。
それでは、どちらの方がよいでしょうか。
費用を極力抑えることを重視すれば、合意契約には医療同意委任と死後事務委任をコンパクトに盛り込んだ上で公正証書化しつつ、自筆証書遺言で遺贈と祭祀承継者の指定を行い、法務局に保管するのがお勧めです。
以上を用意するのに弁護士や司法書士に補助を依頼しなければ、費用は2万円弱で済みます。

合意契約の費用・形式
合意契約公正証書それ自体は高くない
合意契約公正証書の作成費用(公証人への手数料)は、基本費用が13,000円、諸雑費を含めても約15,000円です。比較的手頃ですね。
公証人手数料は2025年10月1日に値上がりしています。
本サイトではこの点を反映していますが、他の事務所のサイトでは合意契約公正証書の基本費用を11,000円とするなど、古い費用体系で案内しているところも多いのでご注意ください。
上記の例外として、死因贈与契約を合意契約に盛り込む場合には、贈与する財産額に応じて高額になります。
平均的な経済力の40代のカップルが双方向での全財産の死因贈与を盛り込む場合は、6万〜10万円程がかかります。

なお、医療同意委任契約や死後事務委任契約を合意契約とは別に公正証書で作成する場合は、それぞれ基本費用が13,000円、諸雑費を含めて約15,000円がかかります。
死因贈与ではなく遺言(+祭祀承継者の指定)を公正証書で作成する場合は、平均的な経済力の40代の方が作成するなら5万〜8万円程がかかります。(カップル両名が作成する場合は、その2倍になります)。
他方で、遺言を自筆証書で作成して法務局に保管する場合は、財産額にかかわらず法務局手数料の3,900円しかかかりません(2名なら7,800円)。
以上は、公証人や法務局への手数料です。もしこれらの文書作成について弁護士や司法書士の補助を依頼する場合は、別途報酬がかかります。
遺言についての、公正証書と自筆証書の公証人手数料や司法書士報酬は以下の記事で詳しく解説しているので、よければご覧ください。
合意契約は公正証書が望ましい
合意契約は方式について特に制限はないので、口頭での約束でも理論的には有効です。
しかし、言った言わないのトラブルになることが確実視されますので、書面での作成は必須と言えます。
費用を極力抑えるために公正証書化しない場合には、証拠力を高めるために以下のような対策を可能な限り施しておきましょう。
・手書きでの署名の上で実印を押捺して印鑑証明書を添付
・変造紛失等の防止のためにカップルが各一部を保管
・証人1〜2名を用意して一緒に署名捺印
以上のような方法があるとしても、合意契約は公正証書で用意しておくことを強くお勧めします。
公正証書費用は前述のとおり15,000円弱であり、その反面で以下のようにメリットが大きいためです。
まとめ
合意契約は、パートナーシップ制度登録や住宅ローン利用の際に条件とされている場合、受け身で必要性を認識されることと思いますが、収入格差があるカップルなどの場合には、財産分与の権利を付与することで公平を実現できるという面でも必要性の高いものになりますので、積極的に検討しましょう。
費用を極力抑えるなら、合意契約に医療同意や死後事務委任のシンプルな規定を盛り込みつつ公正証書化し、遺産や祭祀財産の承継については遺言で法務局保管にするという方法がお勧めになります。
他方で、内容の実現性等を重視する場合は、合意契約、医療同意、死後事務委任、遺言はそれぞれ独立文書で用意して内容の充実化をはかり、かつ、いずれも公正証書で用意するのがベストです。

他方で、収入格差がなく家計が基本独立採算のカップルであれば、合意契約を省くのも選択肢です。
誰でも必須といえる3つの法律文書(遺言・医療同意・死後事務委任)を当事務所ではセットでお手伝いさせていただくサービスを提供しています。
本サービスの担当・執筆者

長野 正義(ながの まさよし)
保有資格
- 司法書士(東京司法書士会所属/登録番号:第8353号)
- 個人情報保護士
- 知的財産管理技能士(二級)
経歴等
昭和57年 東京都文京区 生まれ
平成16年 中央大学 法学部法律学科 卒業
平成22年 司法書士試験 合格
平成23年 簡易裁判所の訴訟代理権試験 合格
一般企業の法務部、大手の司法書士法人等を経て、現職。
メッセージ
裁判所への書類や企業間契約書など、法律文書の作成を専門として15年程の実務経験があります。定型文中心の行政申請業務が主流の司法書士業界では珍しい経歴かもしれません。
現在は特に、同性カップルの法的課題に対する支援に注力しており、遺言書や医療同意委任契約など、法的効力や実務上の実効性を重視したサポートを行っています。
「一人の人生の大事な局面に関わる責任」を重く受け止め、依頼者の思いに応える成果を提供できるよう、今後も研鑽を続けて参ります。
好きな言葉
・至誠一貫 ・第一義
趣味
・茶道(裏千家/許状:行之行台子)