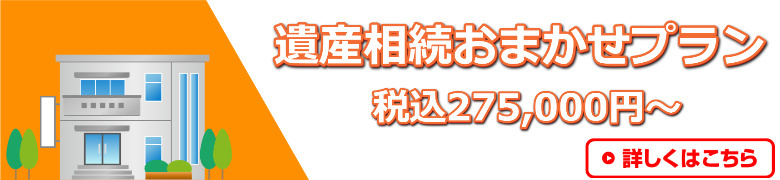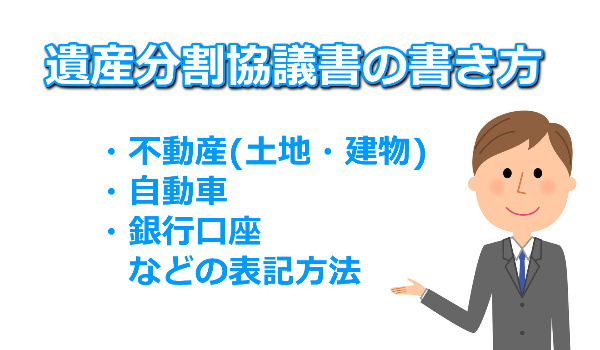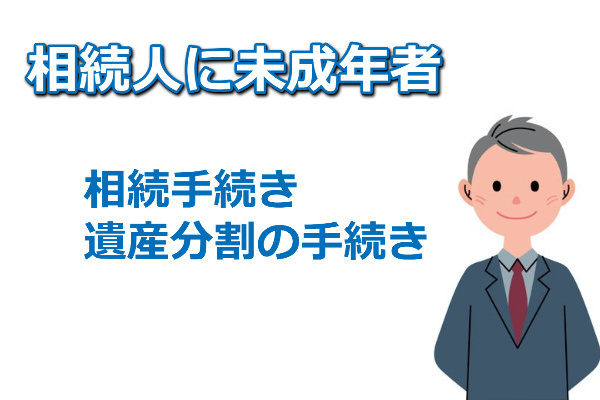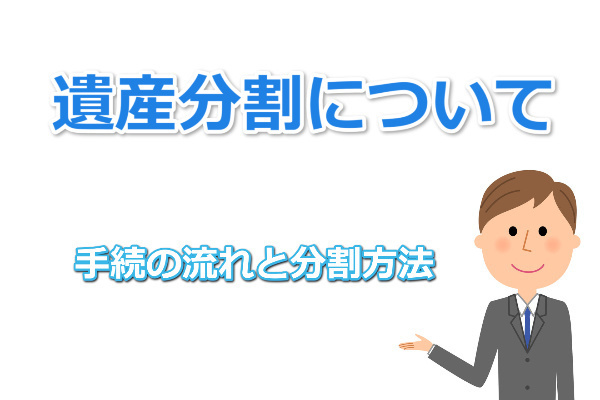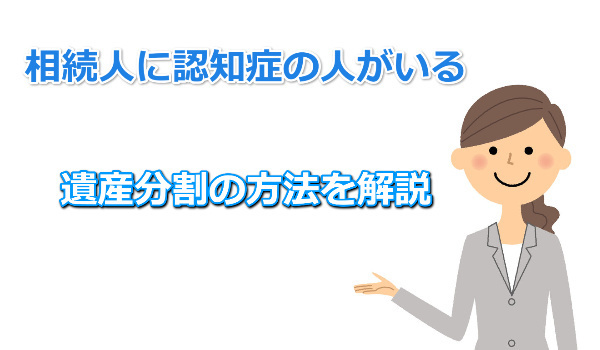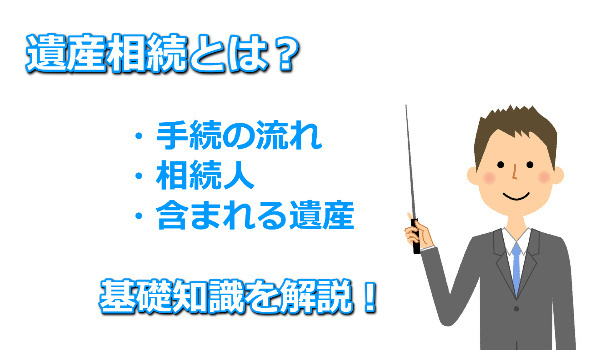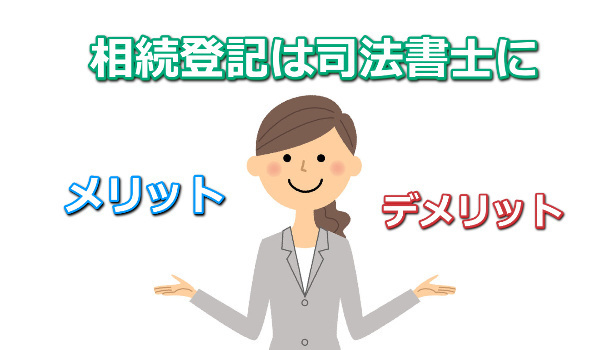相続・遺言に関する手続の総合案内(合同会社つなぐ(FP)×司法書士法人黒川事務所×行政書士黒川事務所の運営サイト)
行方不明者がいる場合の遺産分割協議の方法
相続人の中に行方不明な人がいる場合、その人を無視して遺産分割協議を進めることはできません。「不在者財産管理人」を選任する必要があります。
今回は相続人の中に行方不明者がいる場合の遺産分割協議の進め方をご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
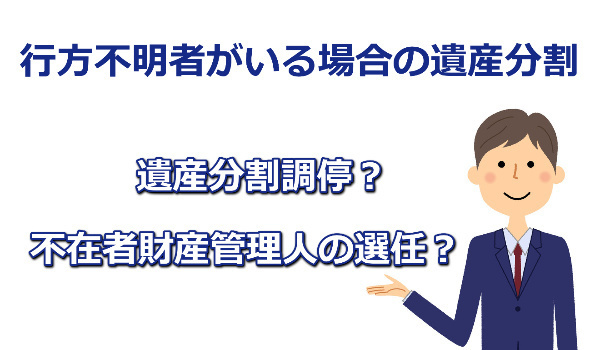
目 次
2-1. 預金の仮払い
2-2. 共有登記
3. 単に連絡を取れない場合
4-1. 不在者財産管理人とは
4-2. 不在者財産管理人の選任方法
4-3. 不在者財産管理人を選任する場合の注意点
2. 預貯金払い戻しや不動産の登記もできない
2-1. 預金の仮払い
3. 単に連絡を取れない場合
4. 行方不明になっているなら不在者財産管理人を選任
4-1. 不在者財産管理人とは
不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を本人に代わって管理する人です。
行方不明でも財産が残されている場合、誰かが管理しないと散逸したり債権者や関係者に迷惑がかかったりして不都合が生じます。本人が自分で管理できる状態になるまで、誰かが代わりに管理しなければなりません。
そこで利害関係人は家庭裁判所へ不在者財産管理人の選任を申し立てると、家庭裁判所が適切な人を選任してくれるのです。
遺産分割に参加して遺産を受け取る権利も財産権の一種なので、不在者財産管理人が選任されるとその人を交えて遺産分割協議を進められます。
4-2. 不在者財産管理人の選任方法
不在者財産管理人は、以下のような方法で選びましょう。
【申請できる人】
不在者財産管理人の選任を申し立てられるのは、本人の配偶者や相続人、債権者などの利害関係人や検察官です。
【申請先の家庭裁判所】
選任を申請する家庭裁判所は「不在者の最終住所地や居住地の家庭裁判所」です。
【必要書類】
申立時には以下の書類が必要です。
- 申立書(裁判所に書式があります)
- 不在者の戸籍謄本または全部事項証明書、戸籍附票
- 財産管理人候補者の住民票または戸籍附票
- 本人が行方不明であることがわかる資料
- 本人の財産資料(不動産登記事項証明書、預貯金通帳の写し、取引履歴、株式関係書類など)
- 相続人が申立てる場合には戸籍謄本どの相続関係がわかる資料
【費用】
1件について800円分の収入印紙が必要です。
他に連絡用の郵便切手を用意しなければなりません。
4-3. 不在者財産管理人を選任する場合の注意点
不在者財産管理人を選任する際には以下のような点に注意が必要です。
遺産分割協議が終わっても業務が続く
不在者財産管理人の業務は、遺産分割協議が終わった後も続きます。
いったん選任されると、本人が帰ってくるか死亡した事実が判明するまで財産管理を継続しなければなりません。
管理人が自分のために勝手に財産を使うと横領罪も成立してしまいます。
親族を不在者財産管理人にすると、遺産分割協議終了後の業務について負担が及んでしまう可能性があるので、誰を候補者に立てるかについては慎重な判断が必要となるでしょう。
本人が帰ってきたときにトラブルになる可能性
不在者財産管理人を選任しても、本人が帰ってきたら任務が解かれます。
このとき、本人は事情がわからないので「勝手に遺産分割をされた」ととらえる可能性もあります。すると、本人と不在者財産管理人との間でトラブルが起こってしまうでしょう。
以上のように、親族が不在者財産管理人になると余計な負担が及んだりトラブルになったりするリスクが高まります。
適切な候補者がいない場合には、はじめから司法書士や弁護士を選任するとスムーズに進められるので、関心ある方はお気軽にご相談ください。
5. 7年以上生死不明なら失踪宣告も可能
行方不明の相続人が7年以上生死不明であれば「失踪宣告」も検討できます。
失踪宣告とは、長期にわたって行方不明の人や死亡の可能性の高い人について「死亡した扱い」にする制度です。失踪宣告が認められると本人は死亡した扱いになるので、遺産分割協議に参加させる必要はありません。
行方不明者の相続人を遺産分割協議に参加させて遺産分割を進められます。
ただ失踪宣告してしまうと、本人が帰ってきたときにトラブルになる可能性が高くなります。帰ってくる可能性がある程度見込まれる場合には、失踪宣告よりも不在者財産管理人の方が良いでしょう。
失踪宣告か不在者財産管理人か、どちらの制度を利用すべきかについては専門的な判断が必要です。迷われたときには司法書士がアドバイスしますので、お気軽にご相談ください。
行方不明者がいる場合の遺産分割協議のまとめ
相続人の中に行方不明者がいる場合には、不在者財産管理人の選任や失踪宣告の申立など、いくつかの対処方法が考えられます。
被相続人の生前であれば遺言書を作成するのも有効な対処方法となります。
遺産相続時にお悩みごとがある場合には、専門家へ相談しておくと安心です。
当事務所でも積極的な対応を進めていますので、お気軽にご相談ください。
遺産分割協議書の関連記事を紹介
遺産分割協議書の書き方
相続人に未成年者がいる場合の遺産分割
遺産分割の手続きの流れと分割方法について
認知症の相続人がいる場合の遺産分割
遺産相続の流れや対象について
遺産分割協議(証明書)は協議書とは違う?
監修者:黒川聡史

保有資格と所属団体
- 司法書士:東京司法書士会所属:登録番号4230号
- 行政書士:東京都行政書士会所属:登録番号第19082582号
- FP(FP技能士1級:日本FP協会CFP®)
経歴
昭和51年生まれ。平成13年司法書士と行政書士の資格取得後、都内司法書士事務所で勤務。平成19年に独立開業し、平成30年に法人化し司法書士法人黒川事務所となる。また、ファイナンシャルプランニング技能士1級及びCFP®を取得しFPとしても活動している(合同会社つなぐ)。