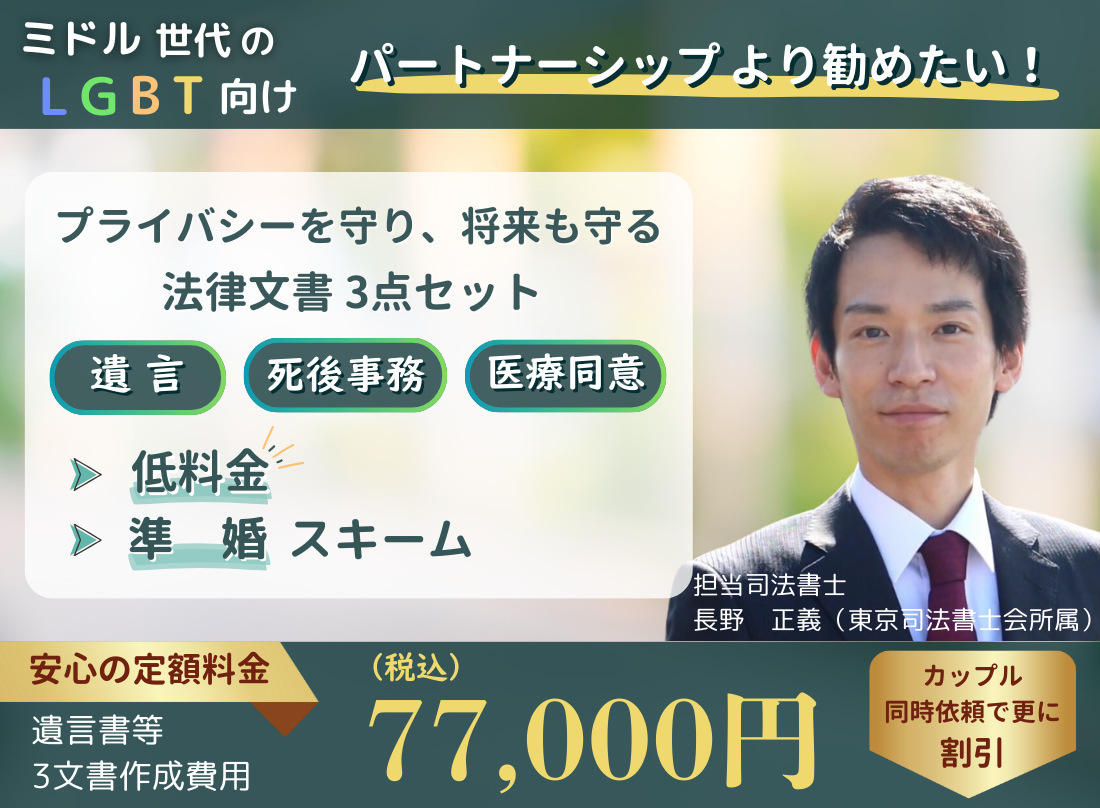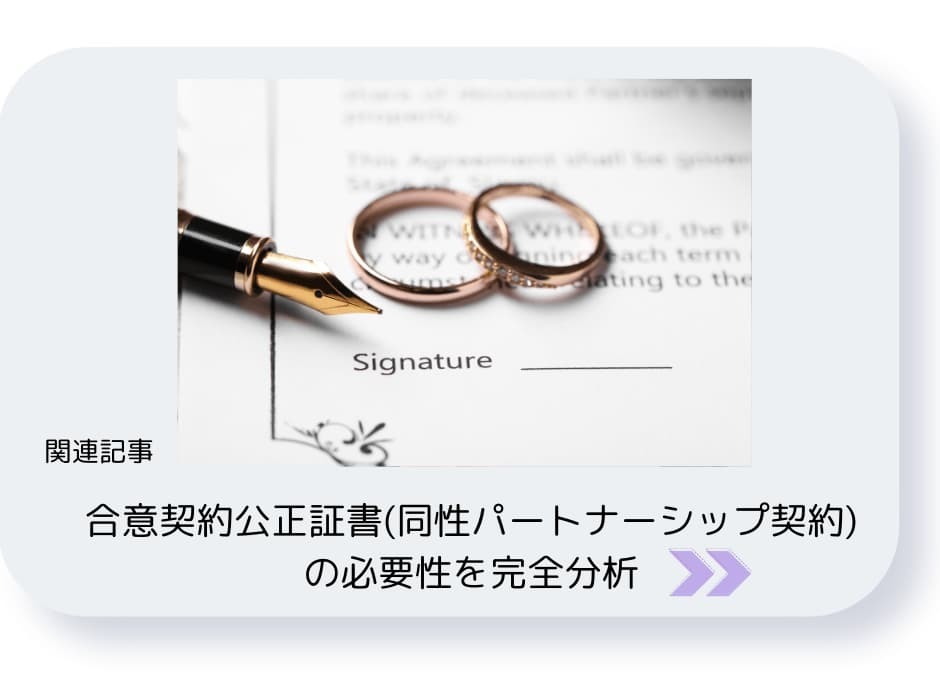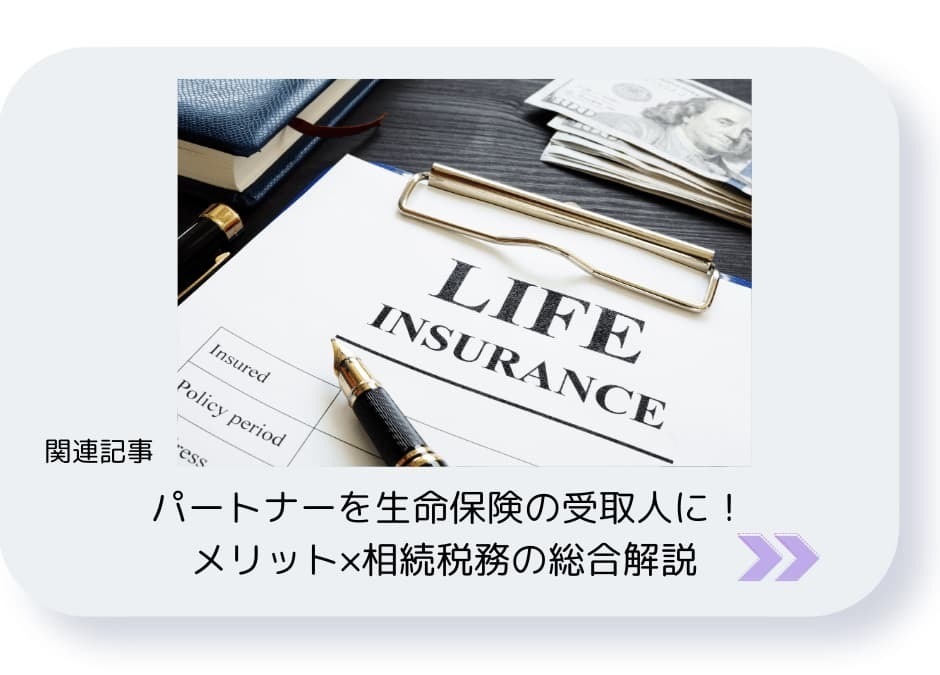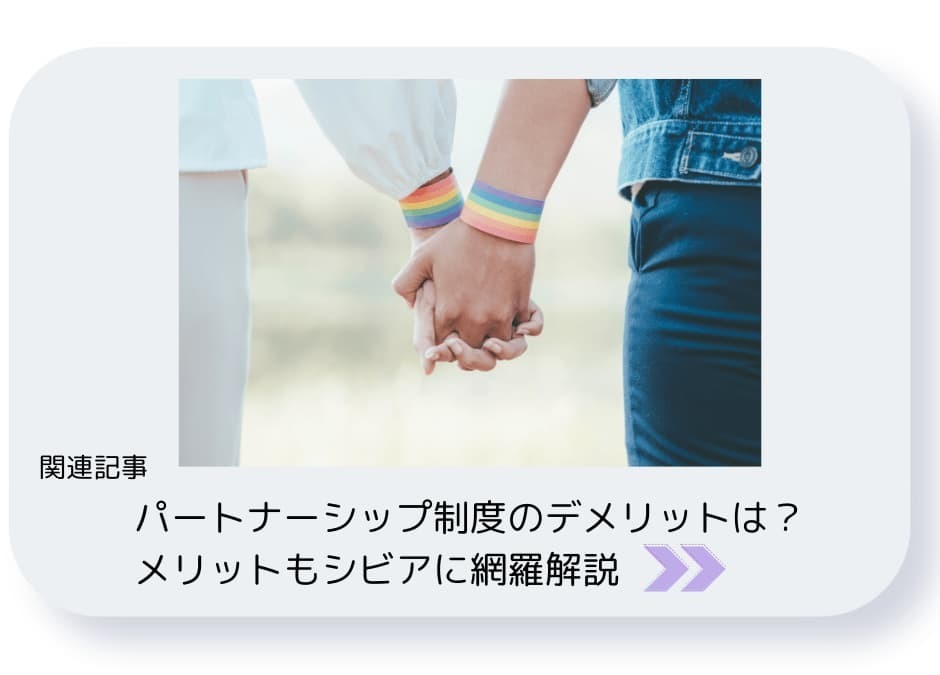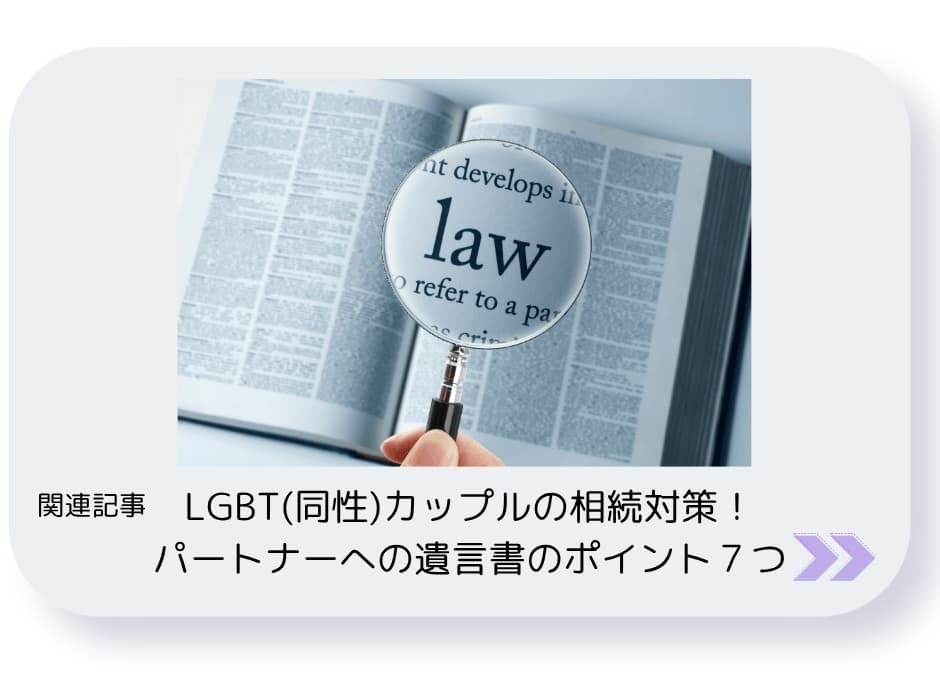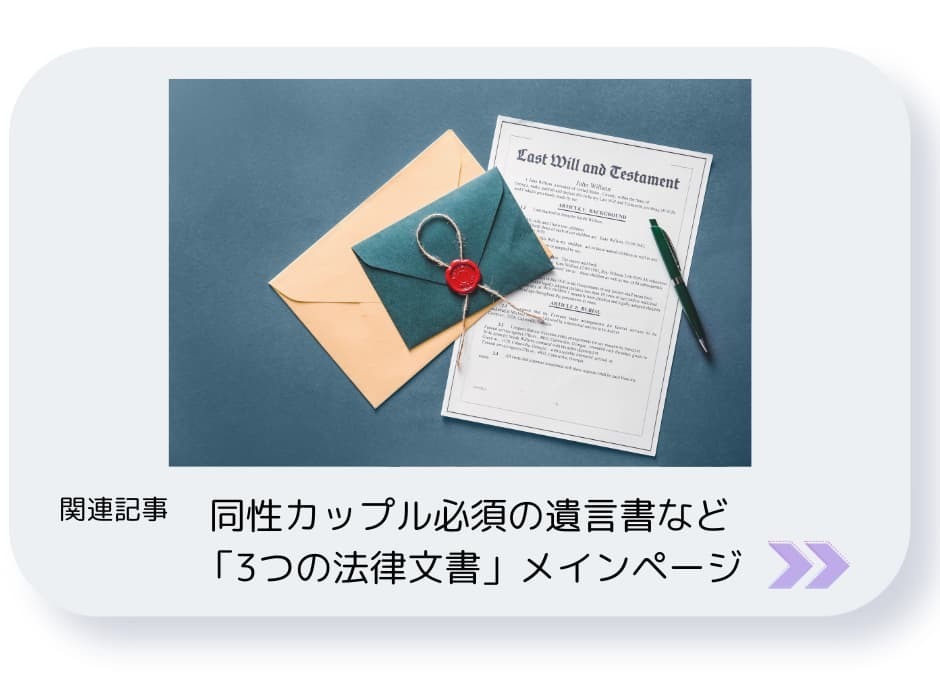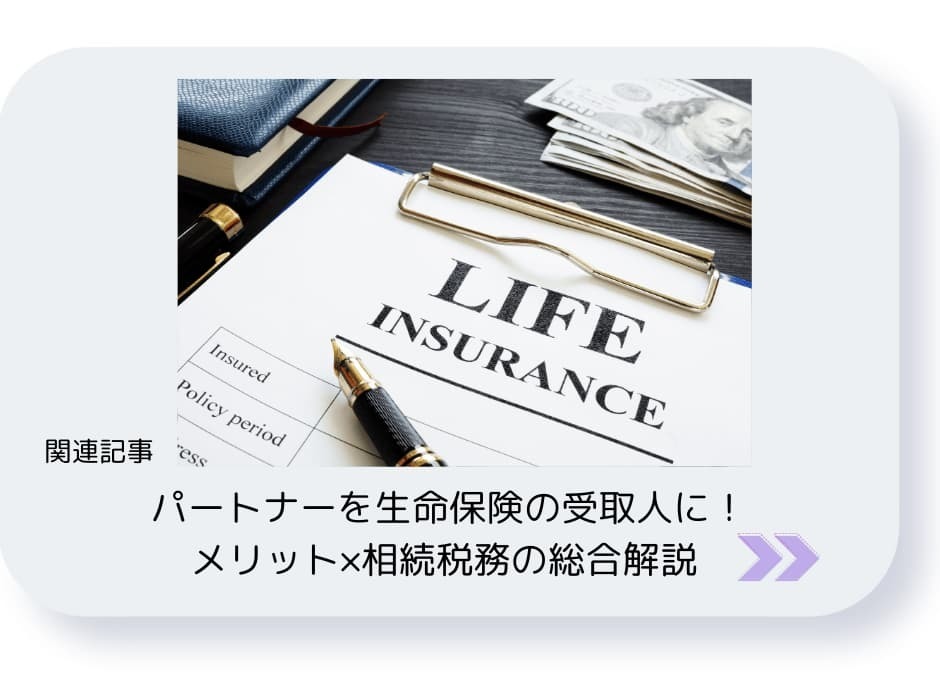相続・遺言に関する手続の総合案内(合同会社つなぐ(FP)×司法書士法人黒川事務所×行政書士黒川事務所の運営サイト)
LGBT(同性)パートナーとの住宅ローン!条件からリスク対策まで完全解説
最終更新日:2025年11月17日
「パートナーと一緒に住む家を買う際の、住宅ローンの組み方や注意点を知りたい」
ゲイやレズビアンなど、LGBTの方の権利擁護の機運が日本でも高まる中、同性カップルが共同で組める住宅ローンを多くの金融機関が販売するようになりました。
生涯を添い遂げることを誓ったカップルの方は、お2人のマイホームとなる物件購入の選択肢が広がるため、興味深く感じている方も多いと思います。
そこで今回は、同性カップルが住宅ローンを組む際の条件、収入合算等の選択肢やそのポイントについて解説していきます。
一般的な団信や住宅ローン控除の解説だけでなく、同性カップルが家を買った後に気をつけること、具体的には相続や財産分与を見据えた遺言書等の法的対策まで司法書士が詳しく解説していきます。
住宅ローンをご検討中のカップルはぜひご覧ください。

同性カップルで住宅ローンを組める金融機関
同性カップルが協力して組むことで借入額を増やせる住宅ローンを取り扱っている金融機関は、現在ではかなりの数に上ります。
具体例を挙げると、以下のとおりです。ご参考までに、下記の表での各銀行名に公式サイトへのリンクを貼っていますので、必要に応じて直接ご確認ください(なお、当事務所と各銀行との間で提携等の関係は一切ありません)。
LGBT向け住宅ローンを扱う金融機関の具体例
※各リンク先は、2025年9月に当事務所が各社の公式サイトを確認したものです。時間の経過により、リンク先の内容が古いものになっている可能性があります。
なお、金融機関の種類ごとの大まかな傾向としては、メガバンクは審査が厳しい、ネット銀行は金利は低いが実店舗の安心感はない、地方銀行は金利は高いが審査が通りやすいなどと言われますね。
同性カップルも、それぞれの希望に沿った特徴の金融機関を選べる時代になりました。
同性カップルも「フラット35」の利用が可能に
「フラット35」は、公的機関(独立行政法人 住宅金融支援機構)が民間の銀行等と提携して提供する住宅ローンです。申込みは民間の銀行等の窓口で行います。
特徴としては、最長35年の全期間固定金利であり、変動金利の上昇が続いている現在は特に安心感が強い点や、民間と異なる独自の審査基準により、年収が高くない方でも審査が比較的通りやすいとされている点などが挙げられます。
後述する「連生団信」を利用できることも特徴の一つです。

この公的サービスである「フラット35」は、2023年から同性パートナーとの収入合算による申込みが可能になりました。
2017年にみずほ銀行で初めて同性カップルによるペアローン等が利用可能になって以降、これに追随して収入合算の対応を可能とする金融機関は年々増えています。
その中でも「フラット35」の利用が可能となったことは、同性カップルによる住宅購入の選択肢を大きく広げる画期的な進展と言えるかと思います。
同性カップルで住宅ローンを組む条件(必要書類)
同性カップルが協力して住宅ローンを組む際の条件(必要書類)は、金融機関によって大きく異なります。
大別すると、以下の4パターンに分けられます。
LGBT向け住宅ローンの必要書類
① 準婚姻契約等の公正証書
② パートナーシップ制度の登録証明書
③ 同居が確認できる住民票
④ 特になし
多くの金融機関は、上記①又は②の提出を必要としています。
上記①については、準婚姻契約のほかに、任意後見契約の公正証書(及びその登記事項証明書)まで必要とする金融機関が多数です。これらの契約については後記のコラムをご参照ください。
また、上記②については、パートナーシップ登録の条件が厳格な東京都渋谷区の登録証明書しか受け付けない金融機関と、そうではなくどこの自治体のものでも受け付ける金融機関とがあります。
他方で、少数ではありますが、上記③又は④で足りるとする金融機関もあります。例えば楽天銀行や多摩信用金庫です。

このように、利用できる条件は金融機関によって大きく異なるので、住宅ローン商品を探す際は早い段階でその条件も確認するようにしましょう。
準婚姻契約とは?
準婚姻契約(合意契約、パートナーシップ契約とも呼ばれます)というのは、当事者間で結婚に近い権利義務を発生させる契約のことです。具体的には、扶助義務、関係解消時の財産分与や慰謝料の支払義務などを定めます。
準婚姻契約は公正証書にしなくても当事者間では法的に有効ですが、公正証書化したものを住宅ローンの条件とする金融機関が少なくありません。
また、多くの金融機関は準婚姻契約に下記のような文言を盛り込むことを住宅ローンの条件としています。必要な契約文言は各金融機関が定めているので、契約書作成前に正確に把握するようにしましょう。
「2人が真摯な関係にあり、同居し協力して生活費を分担する義務を負う」
任意後見契約とは?
同性カップルが組む住宅ローンの選択肢(収入合算・ペアローン)
住宅ローンの4つの形態
同性カップルが共働きの場合、住宅ローンの利用方法として下記の4つの選択肢があります。
住宅ローンの4つの形態の意義
| 単独ローン |
|---|
| どちらか一人だけが契約当事者になる形態 |
| 収入合算ローン(連帯保証型) |
| 一人が借主となり、他方はその保証人になることで、収入合算でローン審査を受けられる形態 |
| 収入合算ローン(連帯債務型) |
| 一本の住宅ローンについて2人が連帯債務者になる(借主として同じ責任を負う)ことで、収入合算でローン審査を受けられる形態 |
| ペアローン |
| 2人が別々の住宅ローンを同時に組む(それぞれが他方の住宅ローンの保証人にもなる)ことで、多額の借入れを受けられる形態 |
これらの4つの住宅ローンの相違点を一覧表にすると、下記のようになります。
住宅ローンの4つの形態の比較表(全体像)
| 単独 ローン | 連帯 保証型 | 連帯 債務型 | ペア ローン | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所有権 | 甲 | 甲 | 甲乙 共有 | 甲乙 共有 | ||
| 借入契約数 | 1本 | 1本 | 1本 | 2本 | ||
| 契約① | 契約② | |||||
| 借 主 | 甲 | 甲 | 甲乙 連帯 | 甲 | 乙 | |
| 保証人 | - | 乙 | - | 乙 | 甲 | |
| 団 信 | 甲 | 甲 | 甲(又は甲乙) | 甲 | 乙 | |
| 税控除 | 甲 | 甲 | 甲乙 | 甲 | 乙 | |
上記の表での団信や税控除(住宅ローン控除)の項目については、後で詳しく解説します。
住宅ローンの形態選択の判断基準
借入額を増やしたい場合は、収入合算ローンやペアローンは有用な選択肢になります。
その中でどれを選ぶべきかについては、ケースによって異なります。
もし同性カップルの一方の収入がそこまで大きくないときは、収入合算ローン(連帯保証型)を選ばれる方が多いでしょう。収入の少ない方は保証人となり、借主よりも一歩下がった返済義務を負う地位に就くわけです。
そうではなく、同性カップルお2人とも相当額の収入がある場合は、収入合算ローン(連帯債務型)かペアローンを選ばれる方が多いでしょう。
2人とも収入が一定額あれば借入額も大きくなるので、団信や住宅ローン控除の活用の必要性が高まるためです。

同性カップルが組む住宅ローンのポイントとリスク対策
同性カップルの場合、結婚した異性カップルが住宅ローンを組む場合とは異なるポイントもあります。
下記では、上記の4つの住宅ローンの形態について比較できる形で、それぞれのポイントやリスク、その法的対策まで詳しく解説していきたいと思います。
住宅ローンの4つの形態の比較表(ポイントの比較)
| 死亡に伴う返済リスク | 住宅ローン控除額 | 準婚姻契約の必要性 | 遺言書の必要性 | |
|---|---|---|---|---|
| 単独ローン | 小 | 小 | 大 | 大 |
| 連帯保証型 | 大 | 小 | 大 | 大 |
| 連帯債務型 | 大 | 大 | 小 | 大 |
| ペアローン | 小 | 大 | 小 | 大 |
一方死亡に伴う返済リスク(団信)
住宅ローンを組む際には、団信(団体信用生命保険)の適用範囲が重要になります。
団信は、「借主」が亡くなったときに住宅ローン残高が完済される生命保険です。ただし、借主以外が亡くなっても保険金は支払われません。
以上の前提で、住宅ローンの各形態を見ていきます。
単独ローン
→死亡に伴う返済リスクは低い
単独ローンの場合で借主自身が亡くなったときは、団信で完済できるため、同居のパートナーは住宅ローンで困ることはありません。
収入合算ローン(連帯保証型)
→死亡に伴う返済リスクは高い
収入合算ローン(連帯保証型)で、借主ではなく保証人のパートナーが亡くなったときは大変です。住宅ローンはそのまま残り、収入合算により多額の借入れを行なっているため、一方のみの収入では返済継続が困難になりやすくなります。
このような事態に備えるためには、保証人の方も別の生命保険への加入を検討しましょう。
収入合算ローン(連帯債務型)
→死亡に伴う返済リスクは高い
補足:収入合算ローン(連帯債務型)と連生団信
一部の金融機関では、連生団信(連生団体信用生命保険)と呼ばれる、「連帯債務者」の方が亡くなった場合もカバーできる団信も提供しています。例えば三井住友銀行やフラット35です。
ただし、保険料として住宅ローン金利が一定割合上乗せされるというデメリットがあるため、平時の返済負担は若干重くなることになります。
ペアローン
→死亡に伴う返済リスクは低い
住宅ローン控除の活用
住宅ローンを組むと、「借主」は多くのケースで住宅ローン控除という所得税等の減税措置を受けることができます。
例えば一般の中古物件(既存住宅)の住宅ローンであれば、控除のポイントは下記のようになります。
住宅ローン控除のポイント(例:一般の中古物件)
Point1.控除額(節税金額)
当年控除額=控除基準額×0.7%
※控除基準額は、「その年の住宅ローンの年末残高」又は「2000万円」のどちらか低い金額
Point2.控除方法
上記控除額がその年の所得税から差し引かれ、年末調整や確定申告の際に還付(その年の所得税で控除しきれないときは、翌年の住民税から控除)
Point3.控除期間
最長10年間
上記のように、一般の中古物件の住宅ローンであれば最大で140万円(2000万円×0.7%×10年間)の節税効果があります(2025年現在)。かなり大きい額ですよね。
この制度の詳細は、下記の国土交通省のサイトをご欄ください(サイト中央部の「概要」の箇所の表が分かりやすいかと思います)。
住宅ローン控除も、借主本人にしか適用されません。以上の前提で、住宅ローンの各形態を見ていきます。
単独ローン・
収入合算ローン(連帯保証型)
→住宅ローン控除の活用は限定的
単独ローンはもちろん、収入合算ローン(連帯保証型)の場合も、借主は1人ですから、節税効果は限定的となります。
例えば、一般の中古物件の住宅ローンの場合、5000万円の住宅ローンを組んでも、そのうち2000万円だけが控除基準額となります。その結果、節税効果は前記のとおり最大で140万円にとどまります。
収入合算ローン(連帯債務型)・
ペアローン
→住宅ローン控除の活用は効果的
準婚姻契約の必要性
同性カップルの場合、万一その関係が破綻することになっても「財産分与」を請求することはできません。
この点は、パートナーシップ制度に登録したり、同性事実婚(内縁)と呼べる状態であったとしても同様です。
異性間では結婚するか事実婚の状態であれば、離婚の際には一方が専業主婦(夫)のケースも含め、夫婦が共同生活を営む間に築いた財産の原則2分の1の分与を請求することができますので(民法768条)、その差は大きいですね。
最近は都市部の中古マンション価格が上昇の一途をたどっており、不動産の価値が住宅ローンを大きく上回ることも珍しくなくなりました。異性間であれば多額の分与を請求できる可能性が、残念ながら同性カップルでは閉ざされています。
以上の前提で、住宅ローンの各形態を見ていきます。

単独ローン・
収入合算ローン(連帯保証型)
→準婚姻契約の必要性は高い
単独ローンや収入合算ローン(連帯保証型)の場合は、不動産の所有者名義は基本的に一方のみになります。
この場合に同性カップルが万一別れることになると、仮に一切の家事を担う形で年収が高い方のパートナーの仕事を長年支えていた場合であっても、財産分与が認められていないため、家事を担った側からの財産請求は困難です。
この点をカバーしたい場合は、準婚姻契約が有用な対策となります。法律が財産分与を認めていなくても、契約を結べば当事者間では法的に有効であり拘束力を持ちます。
そのため、準婚姻契約の中で、財産分与について民法の条文に近い条項を設けたり、より具体的に分配の対象財産やその割合に関する条項を定めておくとよいでしょう。
収入合算ローン(連帯債務型)・
ペアローン
→準婚姻契約の必要性は比較的低い
収入合算ローン(連帯債務型)やペアローンの場合は、不動産の所有者名義は基本的にお二人の共有となります。お2人の住宅ローンの負担割合に応じて、持分(所有権の割合)を決めるのが一般的です。
例えば5000万円の物件を、ペアローンでAさんが3000万円の住宅ローンを組み、Bさんが2000万円の住宅ローンを組んで購入したときは、所有者名義は「共有者 持分5分の3 Aさん 持分5分の2 Bさん」となります。
この場合に同性カップルが万一別れることになると、この持分割合を参考にして、比較的公平な解決を図ることが可能です。
具体的には、一方の持分割合に相当する金額を支払って他方が単独所有者となり居住を続けることや、マイホームを売却した上で持分割合に応じて売却代金を分配するなどして、共有状態を解消することになります。
遺言書の必要性
同性カップルの場合、どちらかに万一のことがあっても、そのパートナーに相続権はありません。
この点も、パートナーシップ制度に登録したり、同性事実婚(内縁)と呼べる状態であったとしても同様です。
異性間で結婚していれば、夫婦の一方が亡くなった場合は必ず他方が相続人となり、少なくとも遺産の半分を承継できますので(民法890条・900条)、その差は著しく大きいものがあります。
その前提で、住宅ローンの各形態を見ていきます。
単独ローン・
収入合算ローン(連帯保証型)
→遺言書の必要性は高い
単独ローンや収入合算ローン(連帯保証型)の場合は、不動産の所有者名義は基本的に一方のみになります。
この場合に名義人が亡くなると、その不動産も含めて全ての遺産を名義人の相続人である親族に持っていかれることになります。
もし名義人に相続人となるべき親族が誰もいなければ、「相続人不存在」という制度により、パートナーは特別縁故者として遺産を承継できる可能性はありますが(民法958条の2)、かなりのレアケースに限られます。
そのため、遺言書での対策が必須と言えるでしょう。
遺言は相続に優先するため、遺言書でマイホームをパートナーに遺贈(遺言での贈与)する旨を定めておくことを強くお勧めします。
収入合算ローン(連帯債務型)・
ペアローン
→遺言書の必要性は高い
収入合算ローン(連帯債務型)やペアローンの場合は、不動産の所有者名義は基本的にお二人の共有となります。
この場合にどちらかが亡くなると、その共有持分は相続人である親族が承継することになります。その結果、遺されたパートナーは、亡くなった共有者の親族とマイホームを共有することになります。
この場合、遺されたパートナーは、相続された共有持分を親族から買い戻すために持分相当額の支払いをするなどの対応に迫られ、もし相続人である親族との間で話し合いが成立しない場合は裁判沙汰で決着を付けることになります。
名義人に相続人となるべき親族が誰もいなければ、パートナーは共有者という地位に基づき遺産の共有持分を承継できますが(民法255条)、かなりのレアケースになります。
まとめ
LGBTの権利擁護の広まりから、同性カップルが協力して住宅ローンを組むことが可能な金融機関は全国的に存在するようになり、また、利用の条件や収入合算等の形態について多様な融資商品が販売されるようになりました。
同性カップルによるマイホーム取得の選択肢が増えていることは素晴らしいことだと思います。
他方で、同性カップルには財産分与や相続が認められていませんから、法的な対策を検討する必要があります。
特に遺言書は、住宅ローンの形態を問わず、遺されたパートナーのために必須といえるものでしょう。
また、パートナーへの遺贈に伴う遺留分侵害や相続税(又は不動産取得税)への対策として、生命保険の活用も検討に値します。
本サービスの担当・執筆者

長野 正義(ながの まさよし)
保有資格
- 司法書士(東京司法書士会所属/登録番号:第8353号)
- 個人情報保護士
- 知的財産管理技能士(二級)
経歴等
昭和57年 東京都文京区 生まれ
平成16年 中央大学 法学部法律学科 卒業
平成22年 司法書士試験 合格
平成23年 簡易裁判所の訴訟代理権試験 合格
一般企業の法務部、大手の司法書士法人等を経て、現職。
メッセージ
裁判所への書類や企業間契約書など、法律文書の作成を専門として15年程の実務経験があります。定型文中心の行政申請業務が主流の司法書士業界では珍しい経歴かもしれません。
現在は特に、同性カップルの法的課題に対する支援に注力しており、遺言書や医療同意委任契約など、法的効力や実務上の実効性を重視したサポートを行っています。
「一人の人生の大事な局面に関わる責任」を重く受け止め、依頼者の思いに応える成果を提供できるよう、今後も研鑽を続けて参ります。
好きな言葉
・至誠一貫 ・第一義
趣味
・茶道(裏千家/許状:行之行台子)