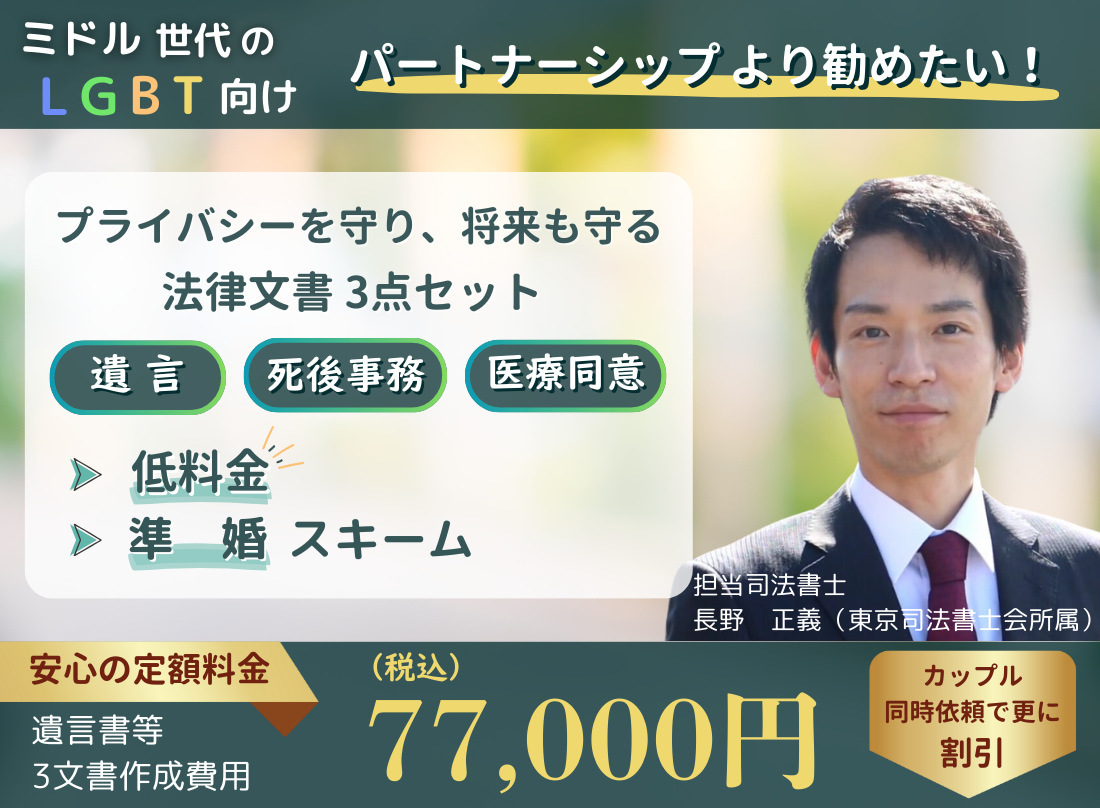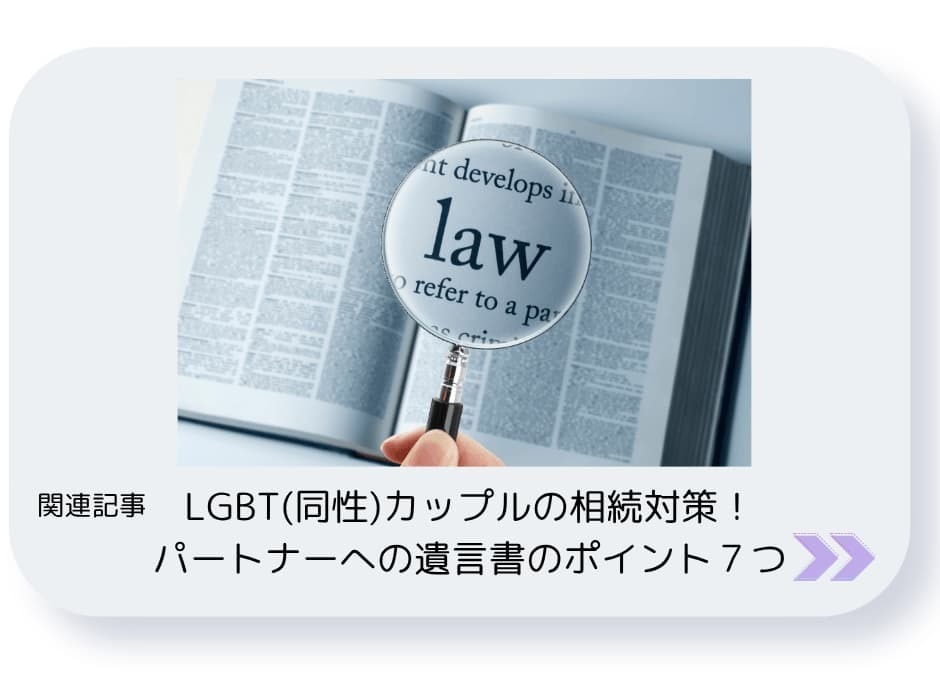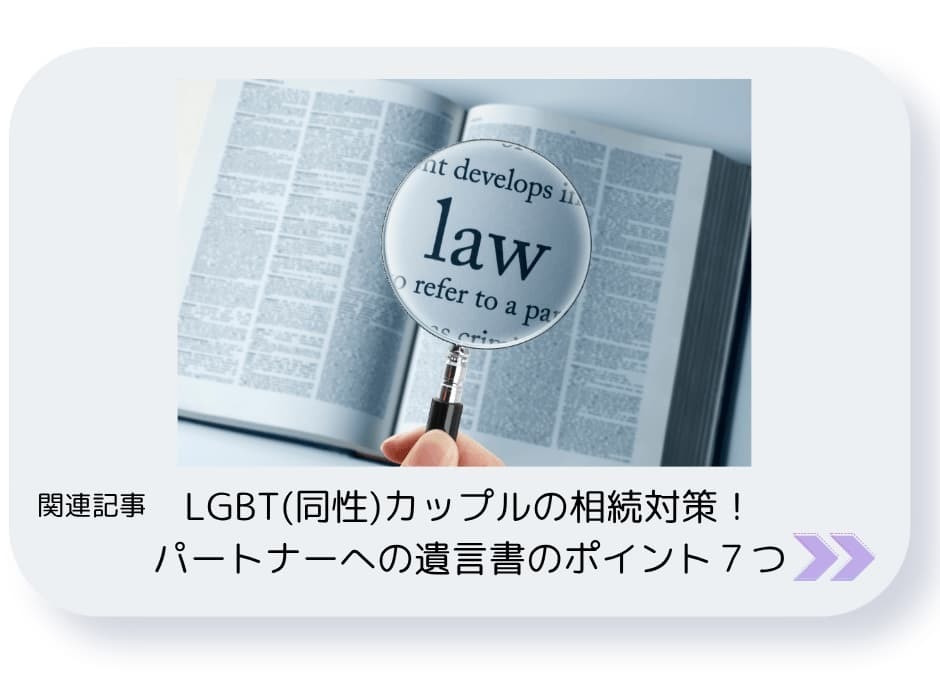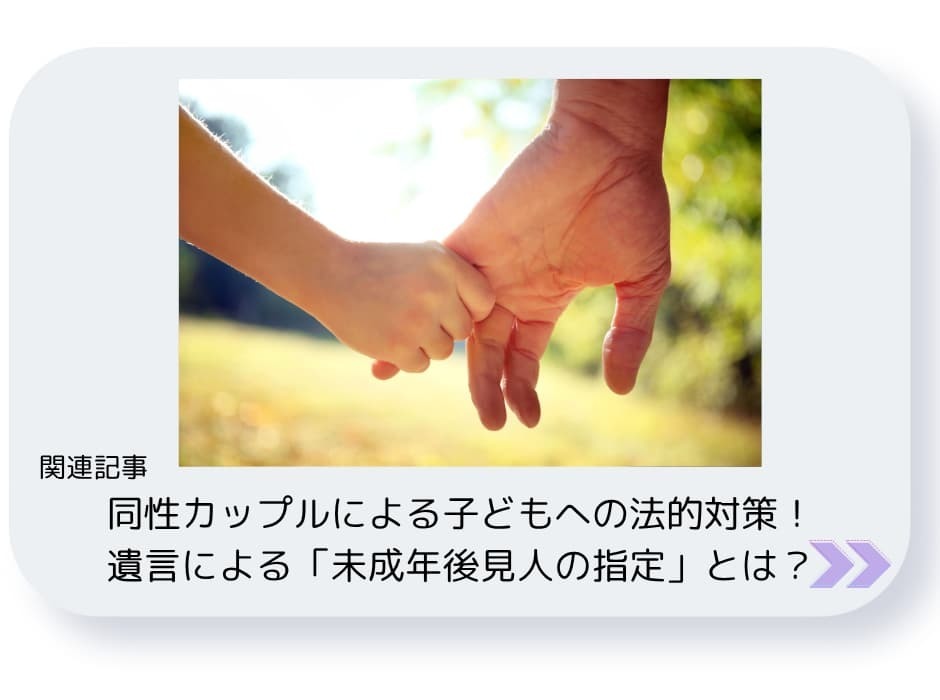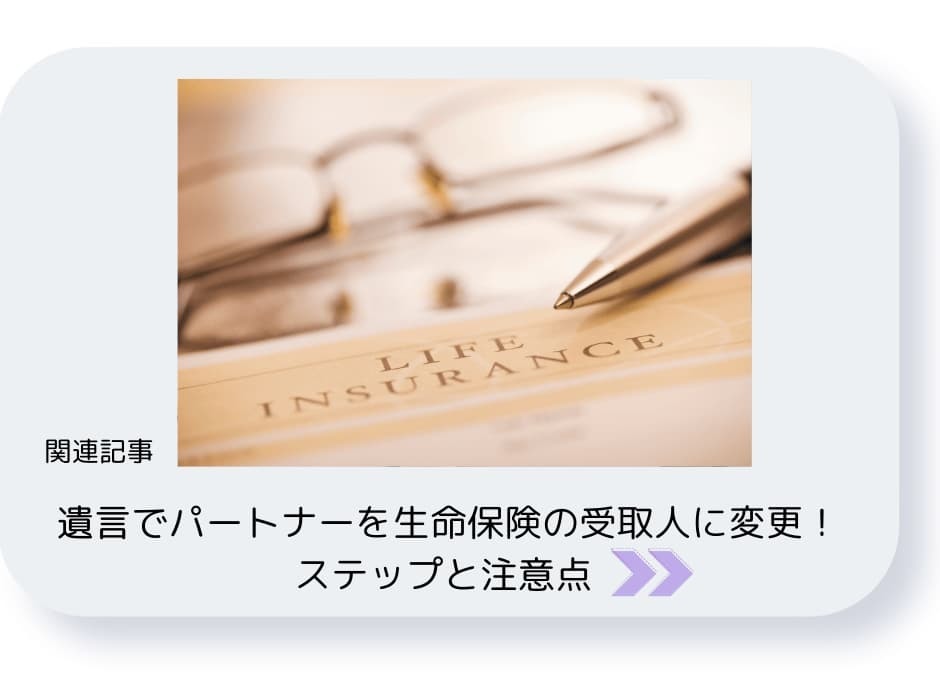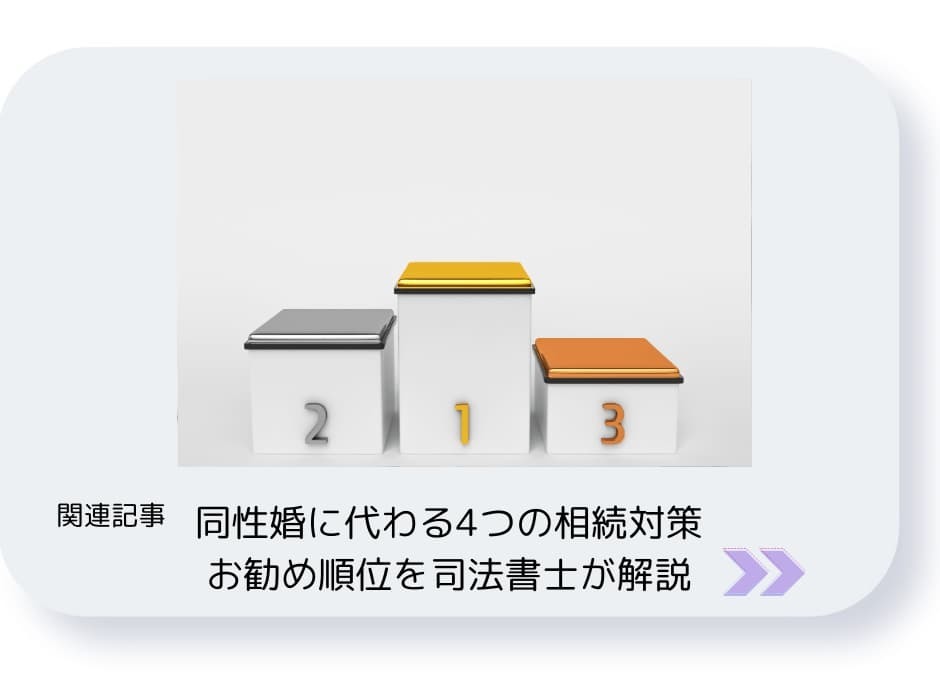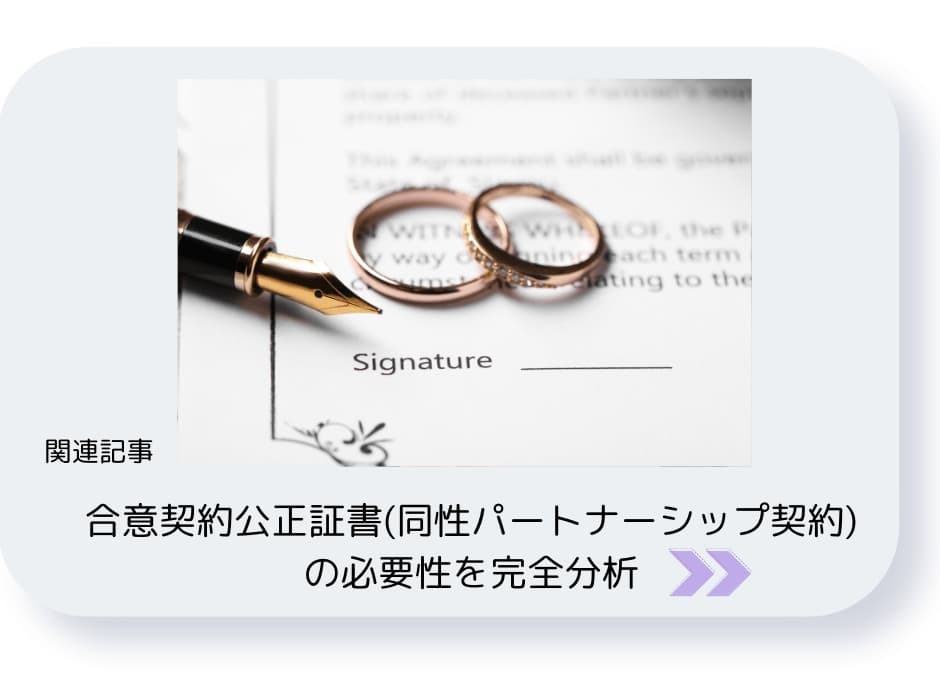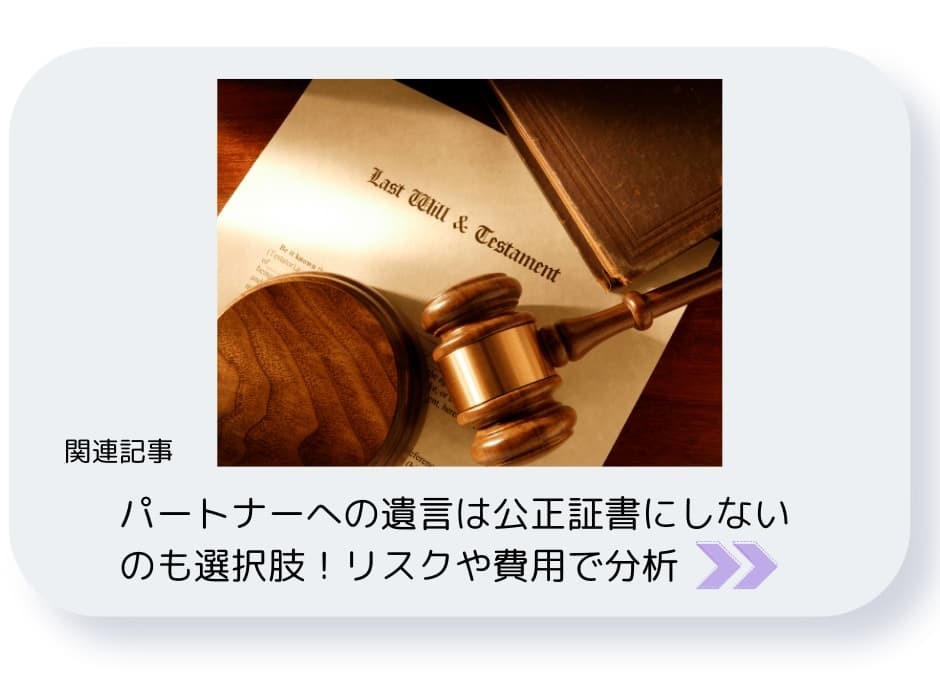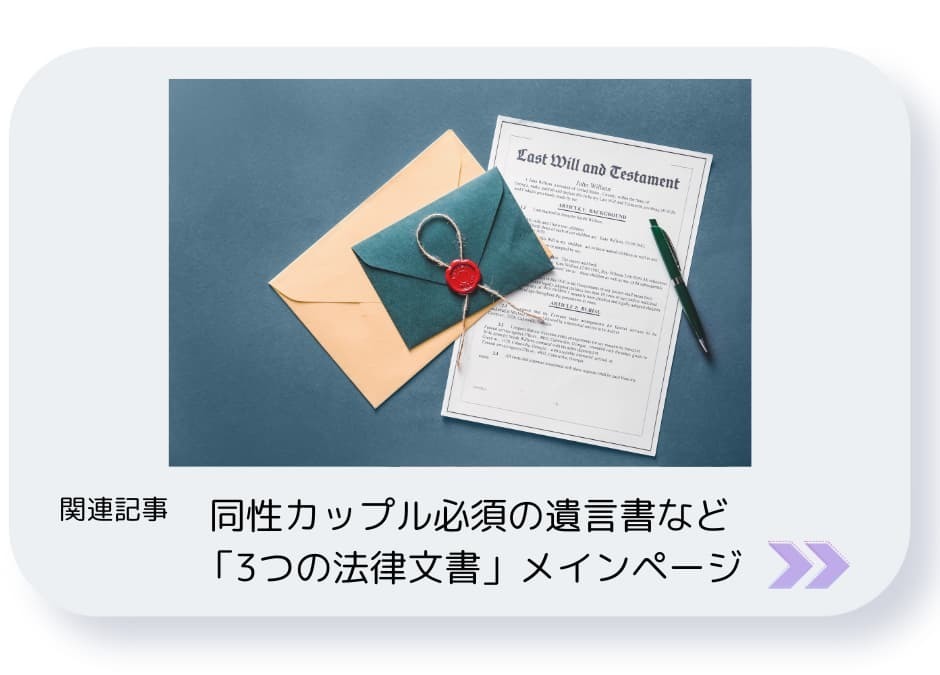相続・遺言に関する手続の総合案内(合同会社つなぐ(FP)×司法書士法人黒川事務所×行政書士黒川事務所の運営サイト)
同性カップルの相続対策:死因贈与と遺言はどちらが有利か徹底比較
最終更新日:2025年11月16日
「相続対策といえば遺言書はよく聞くけど、死因贈与という方法もあるらしい」
レズビアンやゲイなどLGBTの方にとって、相続対策はとても重要です。
現状の日本では同性婚が認められていませんし、パートナーシップ制度に登録しても相続権を発生させることはできません。
生涯をともに歩むことを誓った同性カップルの方は、比較的若いうちから相続対策を検討しておきましょう。
同性カップルの相続対策として有名なのは遺言や養子縁組ですが、マイナーな方法として死因贈与というものもあります。
死因贈与は遺言と同じような効力を発生させることができますし、特に財産をもらう側に遺言よりもメリットがあるとも言える方法です。
しかし、実際には遺言に比べてあまり利用されてはいません。
今回はこの死因贈与について、遺言との比較を中心に詳しく解説していきたいと思います。

死因贈与とは?
死因贈与というのは、贈与者が死亡した時に贈与の効力が発生するという合意をした契約のことです。
例えば、ある人が「私が死んだらこの建物をあげますね」と申込みをして、相手が「分かりました」と承諾をすれば成立します。
遺言もまた、遺言者が死亡した時に効力が発生する法律行為ですが、根本的な違いは、死因贈与が受贈者との合意によって成立する「契約」であるのに対して、遺言は合意の不要な「単独行為」であるという点です。
遺言は財産を譲り渡そうとする相手方に秘密のまま、一人で成立させることもできます。
とはいえ、どちらも贈与者死亡の時に効力が発生するという点で共通するため、民法は以下の規定を設けています。
民法554条(死因贈与)
贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。
死因贈与のメリット【遺言に勝る点】
贈与者の撤回を制限できる
これは受贈者側の大きなメリットになります。
遺言は、遺言者の最終意思尊重の制度であるため、いつでも遺贈を撤回することが可能です(民法1022条)。
これに対し死因贈与では、合意に基づくものであるため、撤回が法律上ないし事実上制限される場合があります。
この点は後で詳しく解説します。
同性カップルの一方が専業主婦(夫)であり、収入財産が少ない場合などには、受贈者としては財産取得の可能性を高めたいでしょうから、死因贈与も検討に値します。
ただし、撤回を必ず防げるかといえば、ケースバイケースになります。どのようなケースなら撤回が制限されるのか、判例の蓄積が少ないので、最終的には裁判で決着を付けざるをえなくなるリスクも高いといえます。
仮登記ができる
公正証書費用を節約できる
遺言の場合は、遺贈する財産の総額が1億円以下の場合には、公証人手数料が13,000円増額されます(これを「遺言加算」といいます)。
また、遺言書内で祭祀承継者(遺骨などを承継する人)を指定する場合には、追加で13,000円がかかります。
祭祀承継者について、詳しくは下記の記事をご覧ください。
死因贈与のデメリット【遺言に劣る点】
-この章の目次-
3-1.贈与者の撤回が制限される
3-2.受贈者は放棄できない
3-3.受贈者の承諾が必要
3-4.身分行為等はできない
3-5.私文書の場合は保管制度がない
3-6.税金が多くかかるケースがある
贈与者の撤回が制限される
受贈者は放棄できない
遺言の場合は、遺言者の死後に受贈者は遺産を承継するのか放棄するのかを選択することができます(民法986条以下)。
遺言が「全財産を遺贈する」又は「全財産の何分の一を遺贈する」という内容の場合(これを「包括遺贈」といいます)、プラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も承継されます(民法990条)。
そこで受遺者(遺贈を受けた人)は、死亡時の贈与者の財産状況(プラスとマイナスのどちらが大きいか等)に応じて、承継するのか放棄するのかを選択することができます。

これに対し、(書面による)死因贈与の場合には、死後に贈与財産の譲受けを拒絶することはできません。この点は判例通説で確立しています(最高裁昭和43年6月6日判決)。
そして、死亡時の全財産を贈与するという包括的死因贈与の場合、遺言と同様にマイナスの財産も受贈者に承継される可能性があります(学説で争われています)。
贈与者が死亡時に万一債務超過に陥っていた場合、受贈者は放棄できずに過酷な状況に追い込まれてしまう可能性があるのです。
なお、包括的死因贈与をしつつ、マイナスの財産だけは法定相続人に承継させるという旨を契約書内で定めることも可能ですが、そのような偏った処分は親族の反感を買い、遺留分請求を誘発させるものになるので、通常は避けた方がよいでしょう。
※死因贈与も遺贈と同じく、遺留分侵害額請求の対象になります。遺留分について、詳しくは下記の記事をご覧ください。
受贈者の承諾が必要
身分行為等はできない
遺言は、法律が定める限りにおいて様々な法律行為を行うことができます。
例えば、遺言であれば子どもの認知や未成年後見人の指定、生命保険の受取人の変更なども可能です。
私文書の場合は保管制度がない
税金が多くかかるケースがある
死因贈与で財産を受け取ったパートナーには、贈与税ではなく相続税が課されます。
そして、受取人が「親子や配偶者」以外の場合には、相続税が2割増額されてしまいます(「相続税額の2割加算」の制度)。
しかし、相続税についての以上の問題は遺贈でも同様ですので、手続選択に影響する要素にはなりません。

他方で、不動産取得税については、死因贈与と遺贈で大きく異なる場合があります。
対象財産に不動産が含まれるときは、相続税に追加して不動産取得税も課税されることがあります。
死因贈与と遺言で違いが生じるのは、包括的財産承継(全遺産を贈与する、ないし、全遺産の何分の一を贈与するという承継方法)の場合です。
包括的財産承継の場合、遺言であれば不動産取得税は課されませんが(地方税法73条の7)、死因贈与では課税されることを覚悟しなければなりません。
住宅等の不動産取得税の税率は不動産価格((固定資産税評価額)の3%ですので、納税は何十万円か、高額な物件なら100万円以上の差が出ることになります。
ミドル世代の同性カップルの遺産承継では包括的財産承継を選ぶケースが多く見受けられますから、死因贈与は遺贈と異なり不動産取得税で大きな違いが出ることを甘受した上で選択する必要があります。
死因贈与は撤回できる?
死因贈与も遺言のように、贈与者は自由に撤回ができるのでしょうか。
結論から言うと、ケースバイケースになりますが、遺言よりは撤回を制限される可能性が高まる、というところになります。
この論点はかなり専門的でやや難解な分野になりますが、遺言と死因贈与のどちらを選択するのか検討する際には理解しておく必要があります。
この論点で重要な遺言の規定は、以下の2つです。
1023条2項の補足解説
例えば、Aさんが「Bさんに甲不動産を遺贈する」と記載した遺言書を作成した後に、Aさんが同一不動産をCさんに売却した場合、この遺言書は撤回したものとみなされるということを意味しています。
不相当な場合は撤回が制限される
死因贈与の撤回を認めるかどうかについて、判例では大雑把に言えば事案ごとにその相当性を判断して決めています。
最近の裁判例でも、死因贈与の「契約に至る動機、目的、契約内容等の事情によっては撤回できない」と判示しているものがあります(名古屋地裁平成4年8月26日判決)。
詰まるところ、事例ごとの判断になってしまうので、判例の集積が乏しい現状では見通しを立てづらく、裁判で決着を付けざるを得ないというリスクが一定程度あるでしょう。
負担付き死因贈与なら撤回を防げる?
負担付き死因贈与というのは、死因贈与する条件として受贈者にも一定の義務履行を求めるものです。
負担付き死因贈与の典型例は、高齢の方が親交のある人に対して「私が死んだら貴方に全財産を遺贈するけど、そのかわりに私が死ぬまでは貴方に私の療養看護をしてほしい」と申し出るものです。
このように、贈与者の生前に受贈者が一定の義務を果たすことを内容とする死因贈与の場合、負担の全部に近い履行をした後は特段の事情がなければ撤回できないというのが確立した判例です(最高裁昭和57年4月30日判決)。
やるべきことをほとんどやった後になって、贈与者に自由に撤回されては受贈者にあまりに酷であり、相当ではないという判断ですね。

同性カップルの方の場合、結婚できない代わりにパートナーシップ契約(準婚姻契約)を締結することがあります。
そしてこの契約書の雛形の中には、カップル相互に全財産を死因贈与するものとしつつ、その条件として、パートナーシップ契約上の義務(扶助義務など)の履行を課しているものがあります。
そのような形で負担付きにしておけば、撤回は防げるのかというと、これもケースバイケースだと思います。
そもそもそのような義務を条件とすることが負担付き死因贈与と言えるのか、もしそのように言えたとしても、負担の全部に近い履行を終えていると言えるのかは、予断を許さないでしょう。
パートナーシップ契約について、詳しくは下記の記事をご覧ください。
撤回権の放棄
仮登記は撤回を事実上抑制する
仮登記に撤回権を奪うまでの法的効力はありません。
そのため、贈与者が死因贈与を撤回すれば、仮登記はその前提となる実体的権利関係を失い、抹消されるべきものになります。
しかし、抹消する手続が簡単ではないという点がポイントです。
仮登記を抹消するには、原則として受贈者の協力が必要で、協力を得られない場合は抹消を命じる判決が必要になります。
仮登記が残ったままでは通常は第三者に売却等を行うことは困難であり(紛争性のある不動産に誰も関わりたくないので)、また、仮登記を抹消しようにも最終的に裁判手続の手間暇がかかることになるので、贈与者が安易に死因贈与を撤回して売却等をすることができなくなります。
死因贈与は仮登記を備えることで、このように贈与者の撤回を事実上抑制する効力があるといえます。
仮登記は万能ではない
仮登記があれば、その後に贈与者が別人に譲渡(贈与、売却、遺贈など)をしても大丈夫と解説する記事がネット上では散見されますが、疑義があるように思います。
前述のとおり、仮登記に撤回権を奪う法的効力はありません。近時の裁判例でも、仮登記が撤回を妨げる要素になるとは判断していません(東京地裁平成7年10月25日判決)。
そして、死因贈与をした後に、贈与者がその贈与財産を別人に譲渡した場合には、過去の死因贈与は撤回したものとみなされます(民法1023条の準用)(最高裁昭和57年4月30日判決など)。
仮登記には順位保全効という法的効力がありますが、これはあくまで仮登記が記録する実体的権利関係(死因贈与による始期付き所有権移転)が有効であるという前提での話です。
撤回によりその実体的権利関係は覆ってしまうため、その仮登記は抹消されるべきものになります。
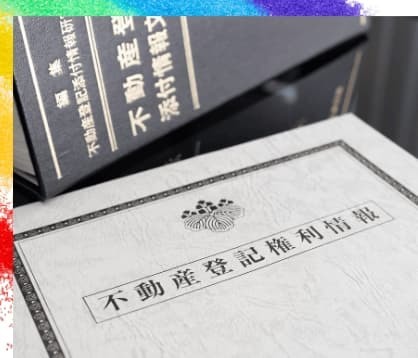
ただ、仮登記が「法的には」無効になっても、その抹消手続で受贈者の協力又は判決が必要になるため「事実上は」撤回しづらくなるということです。
仮登記があれば絶対に大丈夫…というわけではないことは把握しておいた方がよいでしょう。
仮登記の順位保全効は死後に活きる
仮登記が贈与者による撤回の事実上の制約になるという話を先程しましたが、法的効力の面でも有益な側面はあります。
死因贈与の場合、特に贈与者が死亡した後に仮登記の効力が活きてくるとも言えるでしょう。
前提として、上記の撤回権は贈与者本人のみの固有の権利とされているため、贈与者の死亡後にその相続人が撤回するということはできず、贈与者の相続人が第三者に譲渡をしても「みなし撤回」になるということもありません。
ただし、相続人が贈与不動産を第三者に譲渡した場合、その「相続人からの譲受人」と「死因贈与の受贈者」のどちらがその不動産を取得できるかは、登記を先に申請した方になります(民法177条)。
例えば、金欠の相続人が急いで贈与不動産を売却して登記を申請してしまうと、死因贈与の受贈者はその不動産を取得できなくなってしまうのです。

しかし、生前に仮登記をしておけば、死因贈与の受贈者は先に登記を備えたという地位を確保しておくことができるので(仮登記の順位保全効)、上記のようなリスクを払拭することができます。
仮登記には以上のように、受贈者の生前には受贈者の撤回を事実上抑制するという実益があり、受贈者の死後にも他人に登記の先を越されないという法的効力があるので、前向きに検討されることをお勧めします。
仮登記の登録免許税
撤回の可否のまとめ
死因贈与の契約書作成のポイント
撤回権を放棄しておく
受贈者が先に死んだ場合のことも書く
遺言の場合は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、遺贈は効力を生じないものとされています(民法994条1項)。
この規定も死因贈与に準用されるのでしょうか。例えば以下のような時系列で問題になります。
①AがBに甲不動産を死因贈与
②Bが死亡
③Aが死亡
死因贈与執行者を付ける
公正証書で作る
死因贈与は遺言のように方式が要求されていないため、理論的には口約束でも有効に成立します。
しかし、言った言わないの争いになることは目に見えていますし、書面によらない贈与は贈与者が撤回できることになっているほか(民法550条)、贈与者の相続人も撤回できるので(判例・通説)、選択肢にすべきではありません。
文書化する場合、費用節約のために公正証書にしないのも一応選択肢に上がります。
カップル双方が手書きで署名の上、実印で押印し、印鑑証明書を添付しておけば、一定程度の証拠力は備わります。
なお、死因贈与の場合は、遺言と異なり公正証書にしなくても検認は不要です。
しかし、やはり公正証書が強く推奨されます。公証人という公的機関により本人確認や意思確認がなされるので、より強い証拠力を備えることができます。
また、仮登記承諾文言付きで公正証書にしておくと、仮登記を受贈者が単独で申請できるようになります。
高額な財産を承継させるものですので、公正証書を第一に考えましょう。
まとめ
遺言と比較した場合の死因贈与の最大のメリットは、ミドル世代の同性カップルの場合、贈与者の撤回を制限できるところにあるということが多いでしょう。
カップルの一方の収入財産が低い場合には、低い側にとって遺言よりも贈与財産取得の安心感が得られると思います。
しかし、その撤回制限は確実なものではなく、後々に裁判沙汰に発展するリスクを伴うものになります。
また、贈与者にとっては、撤回制限はむしろ将来の財産処分の自由を奪うものとなりますので、デメリットに映ります。
また、受贈者も贈与者死後の承認放棄の自由がないため、贈与者が死亡時に万一債務超過に陥っていた場合、借金を承継するという悲劇を招きかねません。
贈与者も受贈者も将来の意思を拘束されないという面などで、基本的には遺言がお勧めになります。
本サービスの担当・執筆者

長野 正義(ながの まさよし)
保有資格
- 司法書士(東京司法書士会所属/登録番号:第8353号)
- 個人情報保護士
- 知的財産管理技能士(二級)
経歴等
昭和57年 東京都文京区 生まれ
平成16年 中央大学 法学部法律学科 卒業
平成22年 司法書士試験 合格
平成23年 簡易裁判所の訴訟代理権試験 合格
一般企業の法務部、大手の司法書士法人等を経て、現職。
メッセージ
裁判所への書類や企業間契約書など、法律文書の作成を専門として15年程の実務経験があります。定型文中心の行政申請業務が主流の司法書士業界では珍しい経歴かもしれません。
現在は特に、同性カップルの法的課題に対する支援に注力しており、遺言書や医療同意委任契約など、法的効力や実務上の実効性を重視したサポートを行っています。
「一人の人生の大事な局面に関わる責任」を重く受け止め、依頼者の思いに応える成果を提供できるよう、今後も研鑽を続けて参ります。
好きな言葉
・至誠一貫 ・第一義
趣味
・茶道(裏千家/許状:行之行台子)