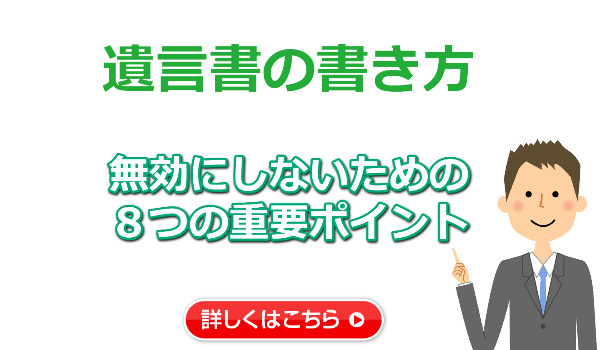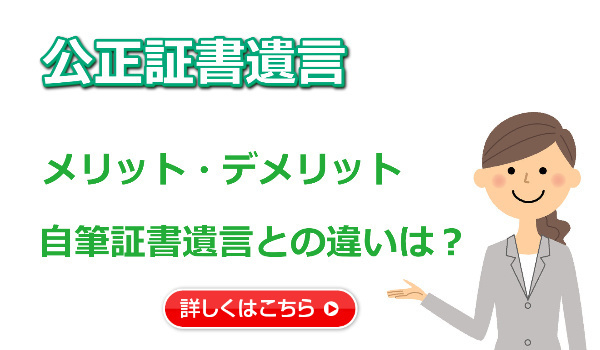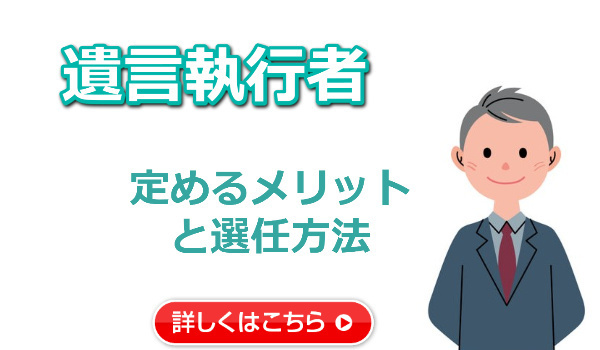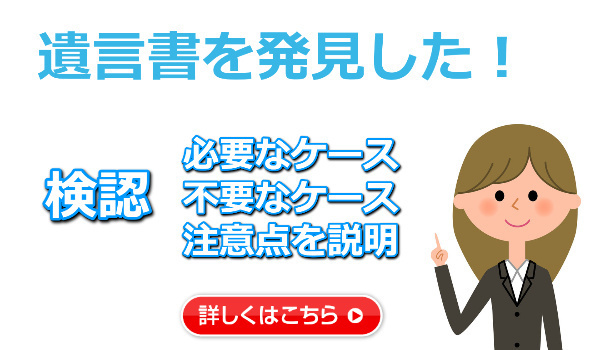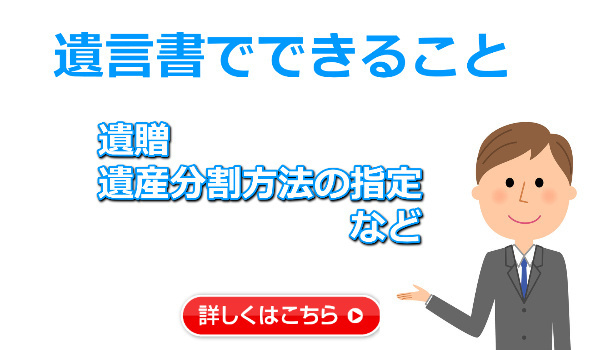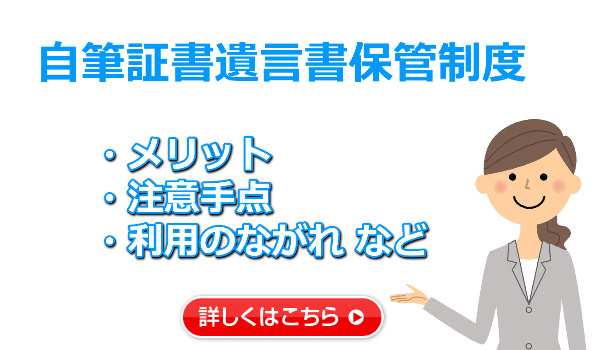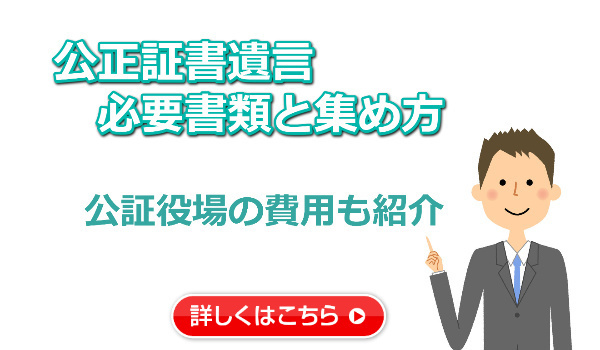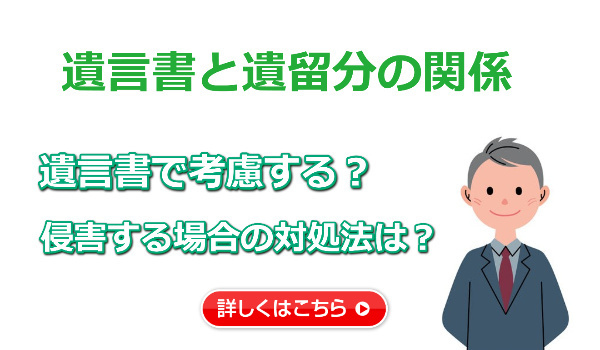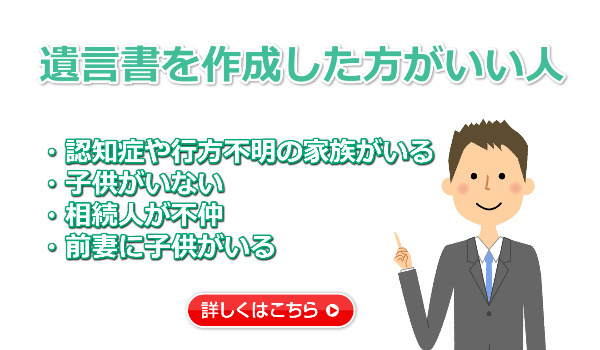相続・遺言に関する手続の総合案内(合同会社つなぐ(FP)×司法書士法人黒川事務所×行政書士黒川事務所の運営サイト)
妻に全財産を渡すための遺言書の書き方を解説
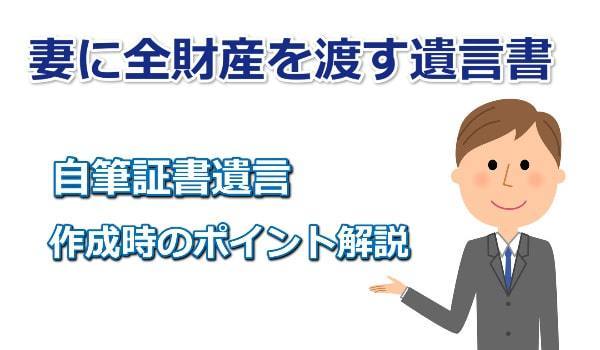
自分の財産を妻に相続させたい場合、遺言書を正しい方法で作成すれば、法定相続分を超えて妻に財産を渡すことが可能です。
例えば、夫婦に子供がいないため相続人が「配偶者(妻)と兄弟姉妹」になる場合、相続争いが起きないように「妻のみに財産を渡したい」というケースなどが考えられます。
本記事では、妻に財産を渡すための遺言書の書き方や、遺言書を作成するときの注意点をわかりやすく解説します。
妻に全財産を残すことは可能?
遺言書で全財産を相続させる
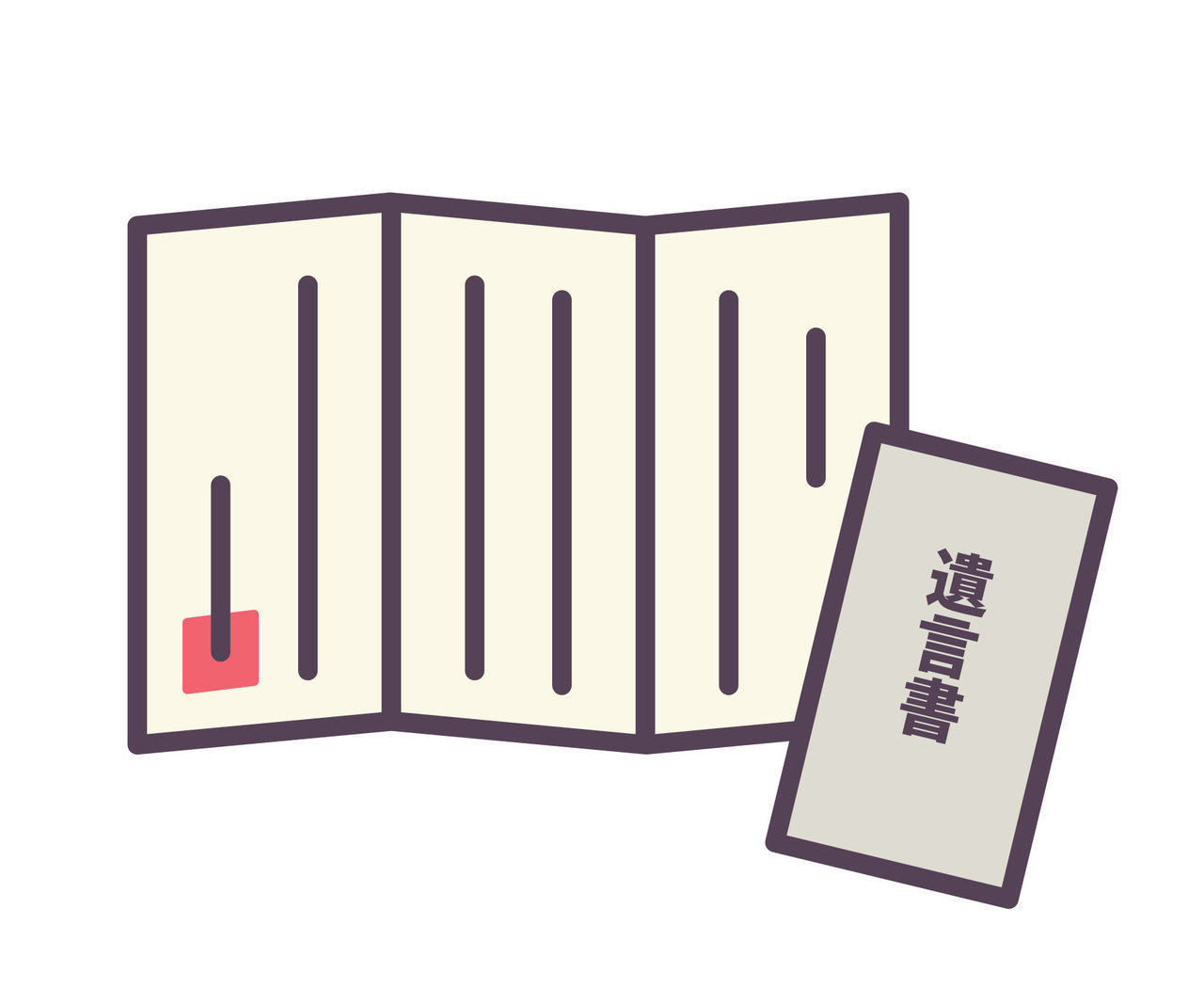
妻に財産を相続させたい場合は、遺言書を作成しましょう。
遺言書には、公証人の下で作成する公正証書遺言と、遺言書を自分で作成する自筆証書遺言の2種類があります。
遺言の作成には、それぞれ民法で定められた書き方のルールがあります。
遺言の作成方法が内容や書き方に民法上問題がなければ、妻に財産を相続させることが可能です。
自筆証書遺言は、公正証書遺言と違い証人が不要であるなどのメリットがあるため、証人の用意が難しい場合に利用することをお勧めいたします。
自筆証書遺言を手書きで作成した後の保管方法に対して不安があるかもしれませんが、法務局で行っている自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、遺言書の原本を安全に保管することも可能です。
ただし、遺言者が遺言書作成時に認知症になっているなど、意思能力がないと考えられる場合は、遺言そのものが無効となり、妻に財産を残すことができなくなる可能性があります。
遺言者が高齢の場合や相続争いが起きそうな場合は、自筆証書遺言より公正証書遺言をおすすめします。
妻に全財産を残したい!
自筆証書遺言書の書き方を4つのポイントで解説
遺言書の全文を自書し(手書き)記名押印をする
民法第968条では、自筆証書遺言を作成する場合、財産目録を除く全文を本人が自書し、記名押印しなければならないと定めています。
パソコンなどで作成した遺言書は無効となるため、必ず手書きで作成しましょう。
第968条
1 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
遺言の作成日付を正確に記載する
妻の氏名と生年月日の2点を必ず記載する
遺言書には、「妻」が具体的にどの人物を指すのかを明らかにするため、妻の氏名、生年月日の2点を必ず記載しましょう。
以下は遺言書の書き方の例です。
「妻に財産を相続させる」という内容を明文化する
妻に全財産を渡すときの注意点は?
法定相続分と遺留分の違い
妻に遺言で全財産を相続させるときの注意点は2つあります。
-
遺言の内容は法定相続分よりも優先される
-
遺留分を持っている相続人から請求を受ける可能性がある
民法では、遺産を相続することができる「法定相続人」を定めています。法定相続人は配偶者のほか、子や孫などの直系卑属(第一順位)、親や祖父母などの直系尊属(第二順位)、兄弟姉妹(第三順位)が該当します。
法定相続人には、民法で遺産を相続する割合(=法定相続分)が定められていますが、この法定相続分には法的拘束力がありません。そのため、法定相続分と異なる内容の遺言を残すことが可能です。
注意が必要なのは、遺産を「最低限」受け取れる割合を定めた遺留分の扱いです。
遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人に与えられており、遺言によって財産を受け取れなかった相続人は財産の一部を金銭で請求する権利を持ちます。
遺言によって相続人の遺留分を侵害すると、相続トラブルに発展する恐れがあるため、妻に全財産を相続させたい場合は、他の相続人(子供や親)がいる場合は生前によく話し合っておくことが大切です。
また、遺言に「付言事項」として「妻は高齢で、自立した暮らしが難しい」「子はすでに独立しており、安定した生活を営んでいる」といった事情を遺言書に記載しておけば、遺留分をめぐるトラブルを回避できる可能性があります。
-LGBTの遺言書-
レズビアンやゲイなど、同性カップルの方が妻(パートナー)に全財産を渡したい場合は、遺言書で祭祀承継など別の注意点もありますので、下記の記事もよければご覧ください。
(まとめ)妻に全財産を相続させる遺言書の書き方を知ろう
妻に全財産を相続させたい場合、自筆証書遺言を作成する方法がおすすめです。
ただし、民法で定められたルールを守らない場合、遺言書の内容が無効になる恐れがあります。遺言書の正しい書き方を知り、「妻に全財産を相続させる」という内容を明文化しましょう。
また、妻に全財産を相続させるときに注意したいのが、他の相続人の遺留分の扱いです。ほかの相続人の遺留分を侵害してしまうと、相続トラブルに発展する可能性があります。
なるべく早い段階から、遺産相続について家族で話し合っておくことも大切です。
監修者:黒川聡史

保有資格と所属団体
- 司法書士:東京司法書士会所属:登録番号4230号
- 行政書士:東京都行政書士会所属:登録番号第19082582号
- FP(FP技能士1級:日本FP協会CFP®)
経歴
昭和51年生まれ。平成13年司法書士と行政書士の資格取得後、都内司法書士事務所で勤務。平成19年に独立開業し、平成30年に法人化し司法書士法人黒川事務所となる。また、ファイナンシャルプランニング技能士1級及びCFP®を取得しFPとしても活動している(合同会社つなぐ)。