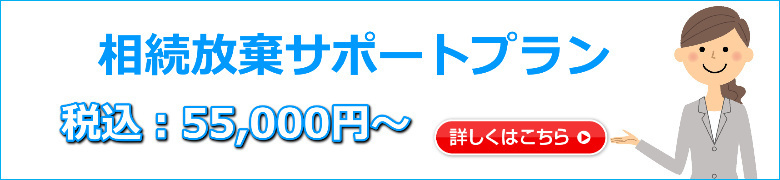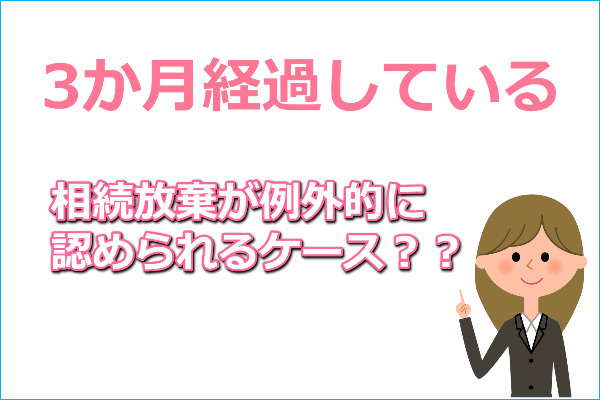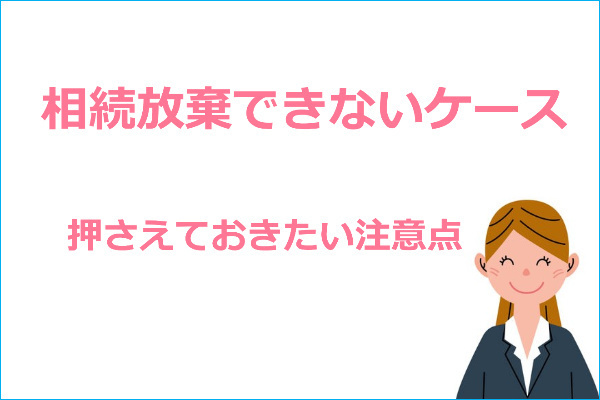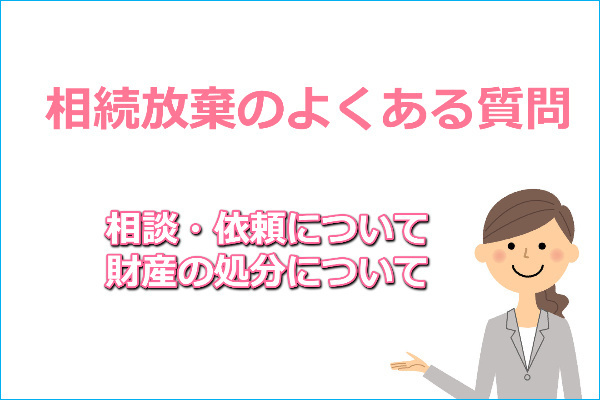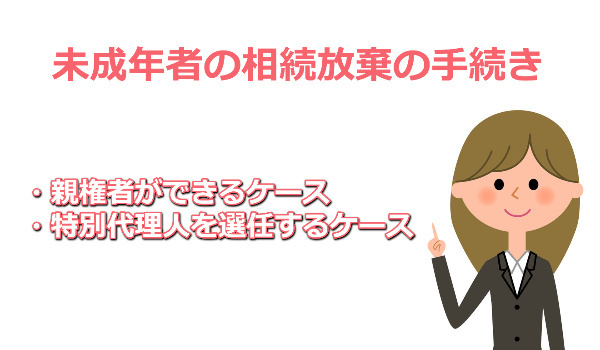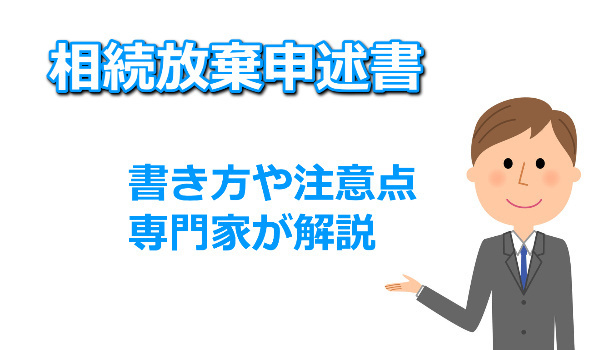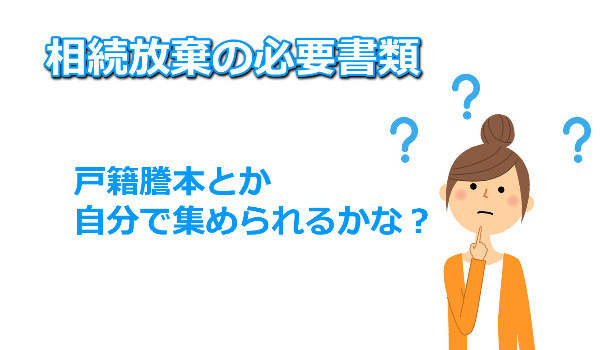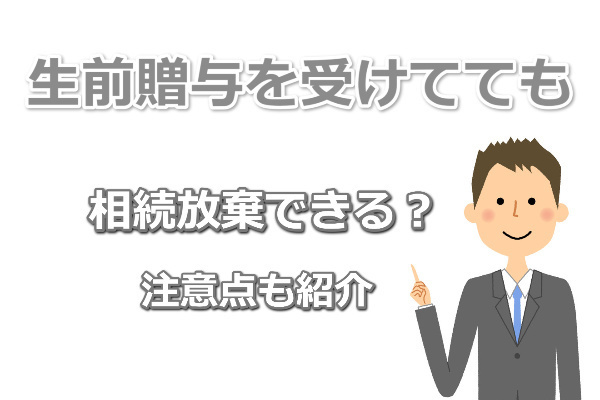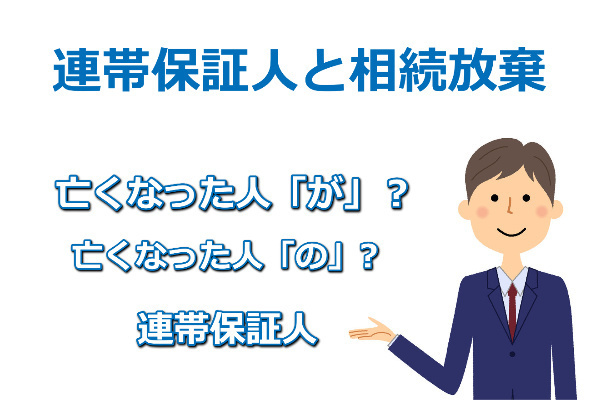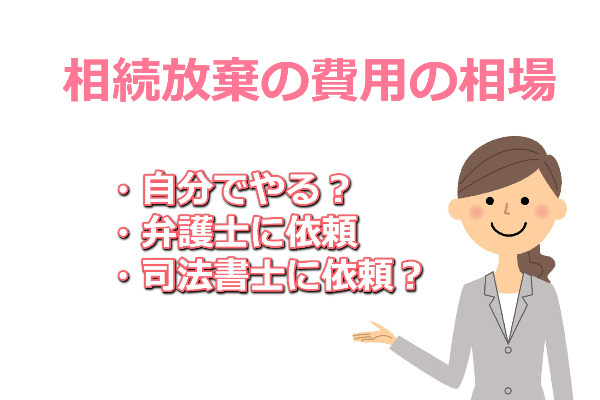相続・遺言に関する手続の総合案内(合同会社つなぐ(FP)×司法書士法人黒川事務所×行政書士黒川事務所の運営サイト)
相続放棄した後の管理義務はいつまで?管理を任せる方法も紹介
相続放棄を行っても、故人の財産を管理(保存)する義務が残る場合があります。この義務のことを「管理義務(保存義務)」と呼びます。
相続財産の管理義務は、いつまで継続されるのか。また、相続財産を自分で管理するのが難しい場合、他の人に代理してもらうことは可能なのか。
本記事では、相続放棄の管理義務の仕組みや期間、相続財産清算人(相続財産管理人)に管理を任せる方法について解説します。
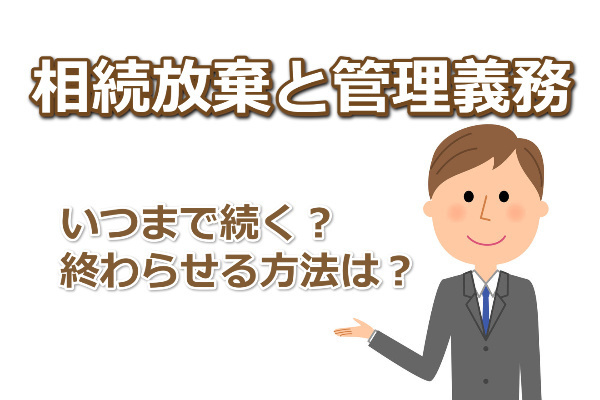
相続放棄しても管理義務は残る?
民法改正によって管理義務の対象者が明確化
相続財産の管理義務は、相続放棄をした人にとって大きな負担となります。
一部の自治体では、相続財産の管理義務を持ち出して、故人の家族に空き家などの管理を求めるケースもあります。
そうした背景をふまえて、2021年に民法の相続法に関する部分が改正されました。
これまでは管理義務の対象者が誰か明確化されていませんでしたが、改正民法が施行された2023年4月1日以降は、「放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有している」人が対象となります(民法第940条)。
また、相続財産の管理も含めた「管理義務」ではなく、状態を維持する「保存義務」に変更されました。
例えば、故人の家に同居していた場合は、相続放棄を行った後も空き家の状態を「保存」する義務を負います。
(自己の財産におけるのと同一の注意をもって保存しなければならいので、「管理義務」と「保存義務」の中身に実質的な違いはありません。)
一方、相続放棄を行った時点で故人の空き家、空き地、農地、山林などを占有していない場合、管理義務を負うことはありません。
改正民法の施行に伴って、相続放棄をした人の負担が大きく軽減されました。
相続放棄後の管理義務はいつまで?
管理義務が発生するのは相続人や清算人に財産を引き渡すまで
民法第九百四十条
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
故人の空き家、空き地、農地、山林などを他の相続人か、民法第952条第1項の清算人に引き渡した段階で、相続財産の管理義務は終了します。
民法第952条第1項の清算人とは、相続人がいなくなった場合(相続放棄も含む)に家庭裁判所が選任し、故人の財産を管理する人のことを指します。
いずれの場合も、相続放棄を他の人に引き渡せば、それ以降管理義務を負うことはありません。
管理義務がある人が亡くなっても管理義務は引き継がれない
相続放棄後の管理義務をなくす方法
相続放棄後の管理義務(保存義務)は、占有している財産を他の相続人に引き渡した段階でなくなります。
しかし、他に相続人がいない場合や、占有している財産を他の相続人が引き継がなかった場合、いつまでも管理義務が残りつづけることになります。
相続放棄後の管理義務をなくしたい場合は、相続財産清算人(相続財産管理人)を選任しましょう。相続財産清算人は、相続財産を管理する人に代わって債務の清算を行ったり、財産を処分したりする人です。
相続財産清算人を選任するには、故人の最後の住所地がある家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
相続財産清算人には、家庭裁判所が最も適任だと判断した人が選ばれ、弁護士や司法書士などの専門家が選任されるケースもあります。
ここでは、相続財産清算人の選任に必要な費用や書類を簡単に解説します。
相続財産清算人の選任に必要な費用
相続財産清算人の選任に必要な書類
相続財産清算人の選任の申し立てに必要な書類は以下のとおりです。
| 必要書類 |
|
戸籍謄本などの取得には時間がかかるため、余裕をもって必要書類を準備しておきましょう。