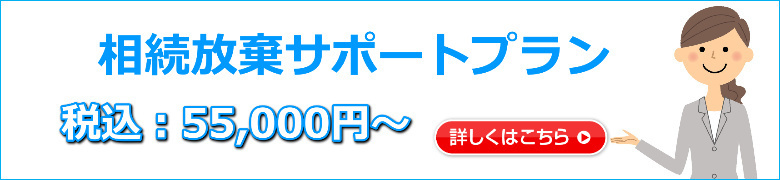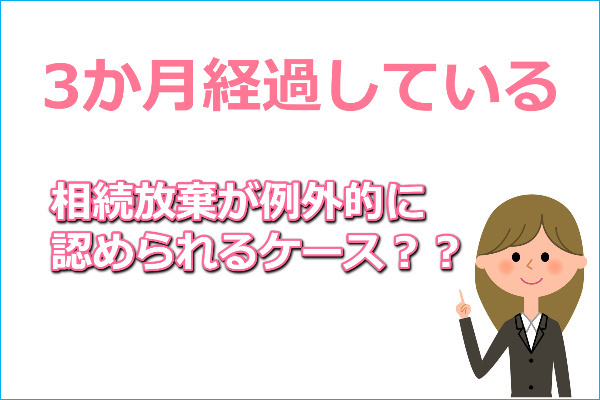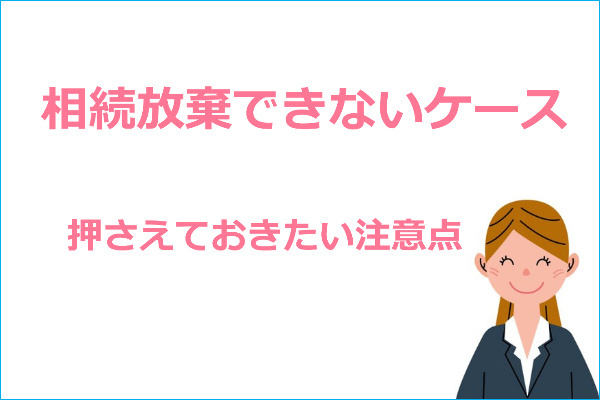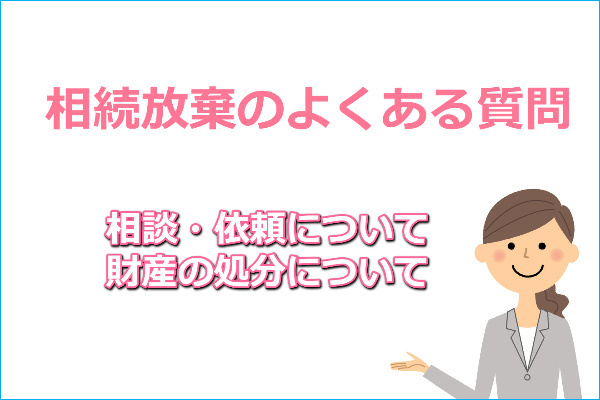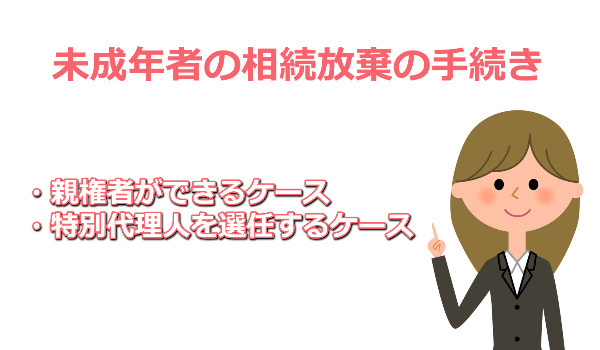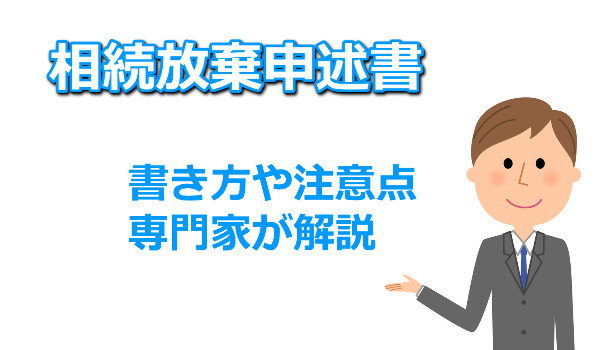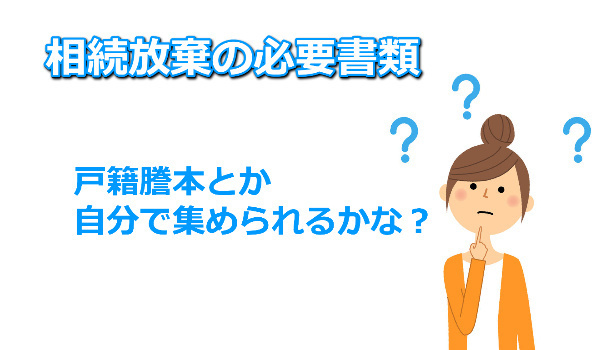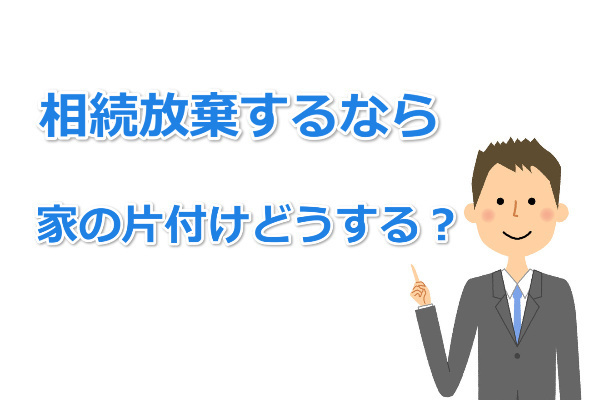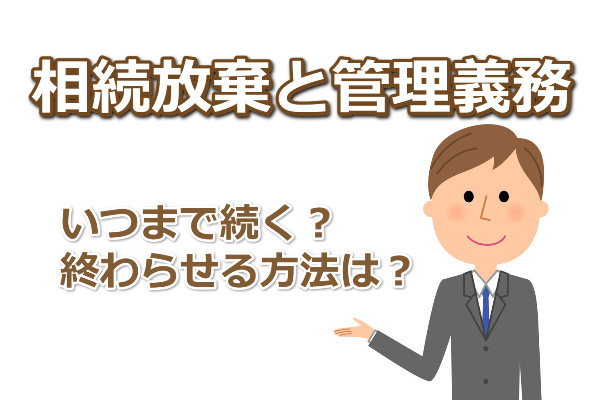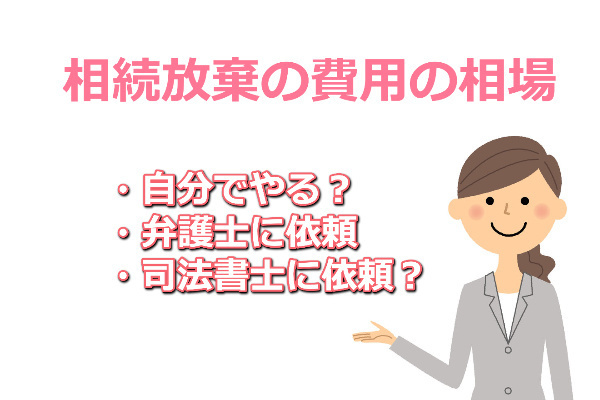相続・遺言に関する手続の総合案内(合同会社つなぐ(FP)×司法書士法人黒川事務所×行政書士黒川事務所の運営サイト)
生前贈与を受けても相続放棄できる?注意点を詳しく解説
故人から生前贈与を受けた後で、相続放棄をすることはできるのでしょうか。
仮に可能であれば、多額の生前贈与を受け取りつつ、亡くなって債務が残った場合に相続放棄をして借金の支払いから逃れられます。
結論からいうと、生前贈与を受けても相続放棄をすることは可能です。
ただし、債権者に詐害行為取消権を行使されたり、タイミングによっては相続税がかかったりすることを知っておきましょう。
本記事では、生前贈与後に相続放棄するときのポイントや注意点を解説します。
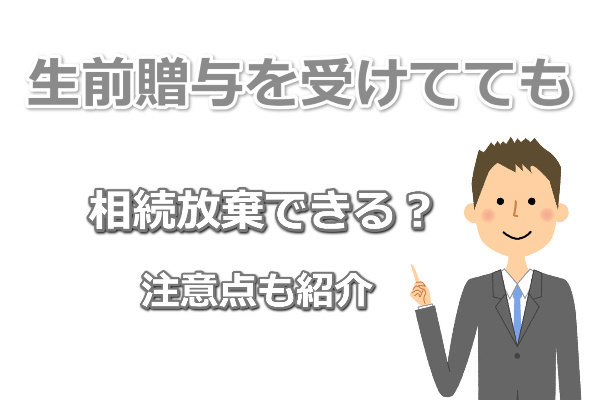
生前贈与後に相続放棄することは可能?
-
相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
-
相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
-
被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認
故人の債務も含めて、あらゆる権利や義務を引き継がない手続きが「相続放棄」です。相続放棄は、故人が多額の借金を抱えていた場合などに役立ちます。
しかし、故人から生前贈与を受けていた場合でも、借金を引き継ぎたくないという理由で、相続放棄を選ぶことはできるのでしょうか?
生前贈与を受けても相続放棄できる
相続時精算課税も利用できる
多額の贈与を行った場合、贈与税の課税対象となります。贈与税の課税方式は、暦年贈与(暦年課税)と相続時精算課税の2種類です。
| 課税方式 | 特徴 |
| 暦年贈与(暦年課税) | 1年間に贈与を受けた財産の合計額を基に贈与税額を計算するもの |
| 相続時精算課税 | 贈与を受けたときに、特別控除額及び一定の税率で贈与税を計算し、贈与者が亡くなったときに相続税で精算するもの |
暦年贈与の場合、1年間に110万円を超える生前贈与を行うと、贈与税が課税されます。
ただし、生前贈与の際は相続時精算課税を利用することもできます。
相続時精算課税を利用すると、2,500万円を限度として贈与税の控除が受けられるため、生前贈与を受けたときの贈与税の支払いを抑えられます(後日相続税で精算)。
この相続時精算課税も、相続放棄とは別個の関係にあるため、相続時精算課税を利用してから相続放棄を申し立てることが可能です。
なお、相続時精算課税にはデメリットもあるため、不明な点がある場合は税理士に相談してください。
生前贈与後に相続放棄するときの注意点
詐害行為取消権を行使される可能性がある
第四百二十四条
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
生前贈与が詐害行為に当たる場合は、債権者が詐害行為取消権を行使し、贈与の取消を求める可能性があります。
例えば、債務者が多額の借金を抱えているにもかかわらず、わざと生前贈与を行って無資力状態(債務超過状態)に陥り、債務を返済できなくなったケースです。
生前贈与のタイミングによっては相続税がかかる
相続放棄を行った場合、相続そのものが発生しないため、相続税は課税されません。
ただし、生前贈与を受けたタイミングによっては、相続放棄を行ったにもかかわらず、相続税がかかるケースがあります。
| 相続開始の3年以内(7年以内)に生前贈与を受けた場合 | 相続税の課税対象 |
| 相続開始の3年以上前(7年以上前)に生前贈与を受けた場合 | 相続税は非課税 |
※2024年1月1日以降は、生前贈与が課税対象財産に加算される期間が「相続開始前7年以内」に変更
相続税がかかるのは、相続開始の3年以内(7年以内)に生前贈与を受けた場合です。
相続税には、生前贈与加算という仕組みがあり、一定期間中に行われた生前贈与は、相続税の課税対象財産に含まれます。
例えば、故人が2023年10月1日に死亡し、2021年8月1日に生前贈与を受けていた場合、生前贈与加算によって相続税の支払いが発生します。
ただし、生前贈与加算が行われる場合、課税対象財産のうち100万円を限度として相続税の控除が認められます。
相続放棄をしたからといって、相続税の負担が完全になくなるわけではないことを知っておきましょう。
相続放棄をしても遺留分侵害額請求の対象になる場合がある
遺留分とは、民法で定められた法定相続人が、最低限受け取ることができる財産のことです。他の相続人によって遺留分が侵害された場合は、遺留分侵害額請求を起こすことができます。
通常、相続放棄を行うと相続そのものが発生しないため、遺留分侵害額請求を起こされることはありません。ただし、多額の生前贈与を受け取った場合、遺留分侵害額請求の対象になる可能性があります。
生前贈与は、民法における「特別受益」とみなされる場合があります。
特別受益は、遺留分を算定する基礎に含まれる金額のことです。特別受益の金額が多すぎると、他の相続人の権利が侵害され、遺留分侵害額請求を起こされる可能性があります。
生前贈与が特別受益とみなされるのは以下のケースです。
| 生前贈与の対象 | 特別受益とみなされるケース |
| 相続人 |
|
| 相続人以外 |
|
相続放棄を行った場合、すでに相続人ではないため、相続開始から1年以内の贈与が特別受益に該当します。
あまり多いケースではありませんが、生前贈与のタイミングによっては、遺留分侵害額請求を起こされる可能性があることを知っておきましょう。