相続・遺言に関する手続の総合案内(合同会社つなぐ(FP)×司法書士法人黒川事務所×行政書士黒川事務所の運営サイト)
前妻の子に相続させない方法は?ポイントを詳しく紹介
よくある相続トラブルの一つが、遺産を残した人が再婚しており、前妻との間に子がいたケースです。
前妻との間の子には遺産を相続する権利があります。
しかしながら、さまざまな事情から前妻の子に遺産を相続させたくない場合もあるかと思います。
本記事では、前妻の子の相続権についての考え方や、前妻の子に相続させない方法のポイント、相続トラブルを防止する方法を解説します。
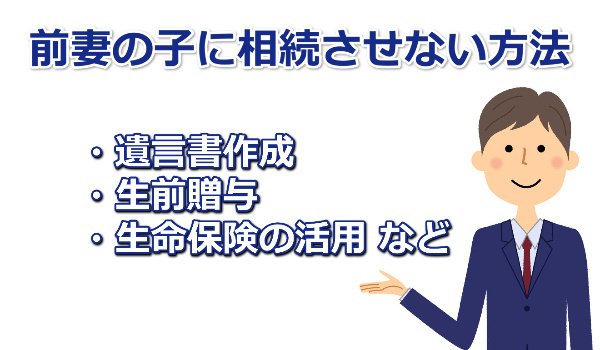
前妻の子にも相続権はある
前妻の子に相続させない方法
遺言書を作成する
まずは遺言書を作成し、遺産の相続分を指定しましょう。
相続人には、各自民法で定められた法定相続分がありますが、遺言で法定相続分と異なる取り決めをすることができます。
遺言書が存在する場合は、法定相続分よりも遺言書で指定した相続分が優先されるため、後妻や後妻の子により多くの財産を相続させることができます。
ただし、法定相続人には、法定相続分とは別に「遺留分」と呼ばれる民法で定められた「最低限の取り分」が認められています。
※遺留分とは、遺産を相続できる最低保証額のことです。
そのため、遺言書に「前妻の子は遺産を相続しない」という内容を記載したとしても、遺留分を請求された場合、財産の一部を相続させる必要があります。
前妻の子の場合、遺留分は法定相続分(本来の相続分)の2分の1です。たとえば、相続人が後妻、後妻の子、前妻の子の3人の場合、法定相続分と遺留分は以下の表のとおりです。
| 被相続人との関係 | 法定相続分 | 遺留分 |
|---|---|---|
| 後妻 | 2分の1 | 4分の1 |
| 後妻の子 | 4分の1 | 8分の1 |
| 前妻の子 | 4分の1 | 8分の1 |
生前贈与をする
生命保険を利用する
相続放棄をさせる?
相続人の廃除をする
前妻の子との相続トラブルを防止する方法
前妻の子との相続トラブルを防止するため、以下の3つを心掛けましょう。
-
まずは遺産分割協議についての通知をする
-
相続手続きに非協力的な場合は専門家に相談する
-
最低限の遺留分を保証する
相続手続きを進めるには、法定相続人が全員参加し、遺産分割協議を開く必要があります。前妻の子に遺産を相続させたくないからといって、遺産分割協議を避けて通ることはできません。
前妻の子に被相続人の死を伝えなかったり、遺産分割協議に参加させなかったりした場合、相続手続きそのものが無効になる可能性があります。被相続人が亡くなったら、すみやかに遺産分割協議について通知しましょう。
前妻の子の居場所がわからない場合は、戸籍の附票か住民票を取得し、現住所を調べましょう。もし相手方が相続手続きに非協力的な場合は、司法書士や税理士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
前妻の子をめぐる相続は、大きなトラブルに発展しやすいため、自力で解決しようとせず、専門家の意見を聞くことが大切です。
相続トラブルを避けたい場合は、遺言書で前妻の子の相続分を指定し、最低限の遺留分を保証しておく方法も効果的です。
財産の一部を相続させる必要はありますが、先手を打って遺留分を保証しておけば、後で相続分の請求(遺留分侵害額請求)を起こされる心配がありません。
遺留分は現金で精算する必要があるため、遺産分割協議を開く際にある程度の現金を用意しておくとスムーズです。
【まとめ】前妻の子も相続人になる!遺留分を少しでも減らそう
民法上は、前妻の子も法定相続人に含まれます。
遺言書を作成すれば、被相続人が自由に相続分を決めることができますが、法定相続人には遺留分(遺産の最低保証額)が認められる点に注意が必要です。
前妻の子の場合、遺留分は法定相続分のさらに2分の1となります。生前贈与や生命保険の仕組みを利用し、少しでも相続財産を少なくすることで、前妻の子が相談する財産を減らせます。
ただし、相続手続きの開始から10年以内に贈与した財産は、遺留分の計算の基礎(=特別受益)となるため、早い段階から手続きを行っておく必要があります。
監修者:黒川聡史

保有資格と所属団体
- 司法書士:東京司法書士会所属:登録番号4230号
- 行政書士:東京都行政書士会所属:登録番号第19082582号
- FP(FP技能士1級:日本FP協会CFP®)
経歴
昭和51年生まれ。平成13年司法書士と行政書士の資格取得後、都内司法書士事務所で勤務。平成19年に独立開業し、平成30年に法人化し司法書士法人黒川事務所となる。また、ファイナンシャルプランニング技能士1級及びCFP®を取得しFPとしても活動している(合同会社つなぐ)。


