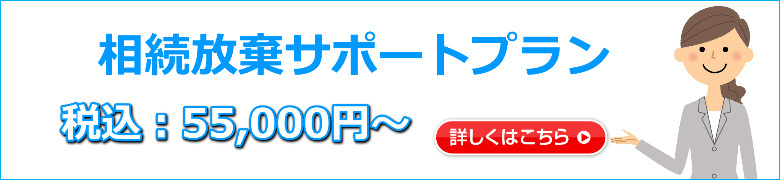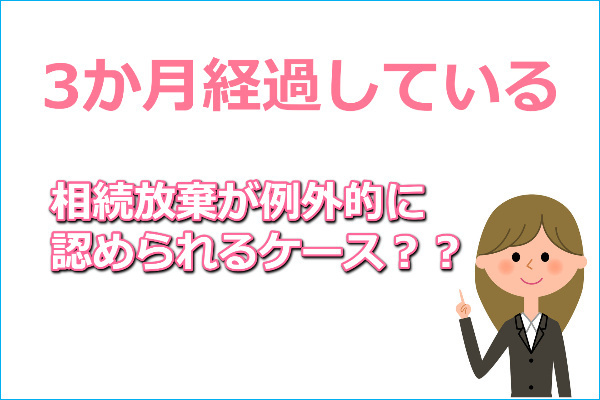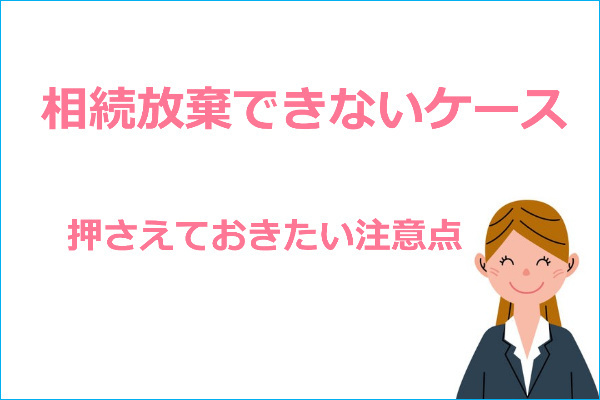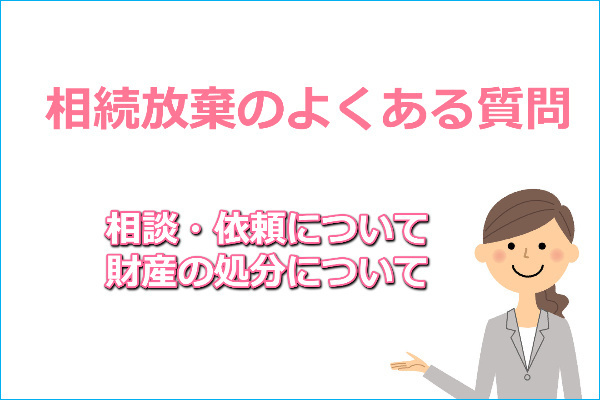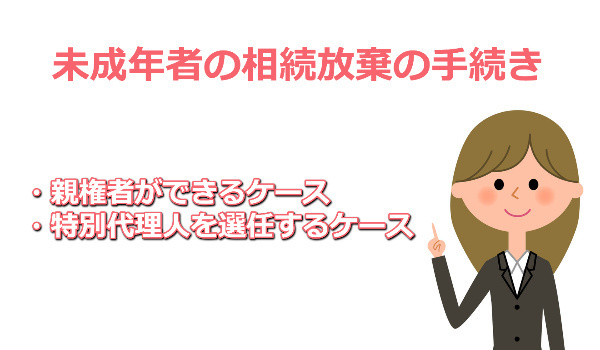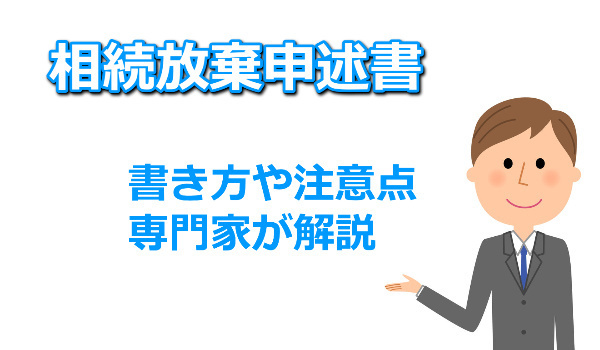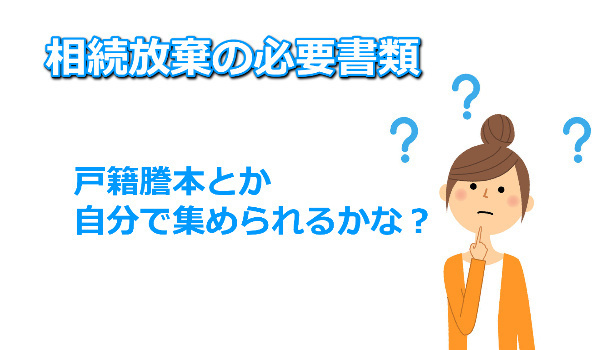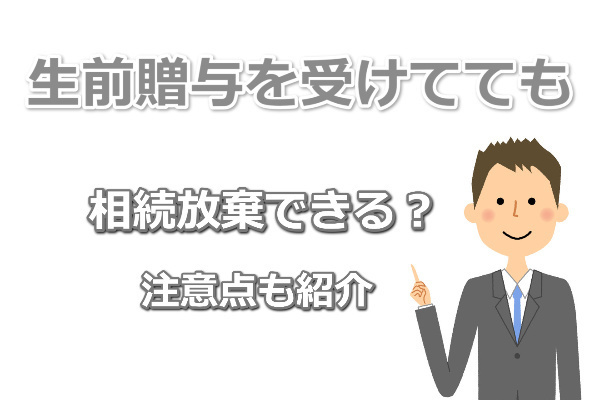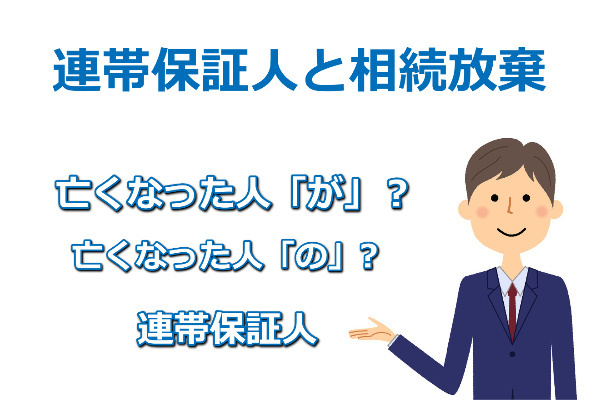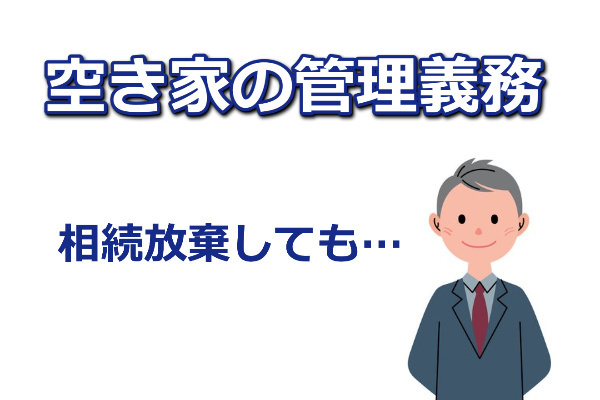相続・遺言に関する手続の総合案内(合同会社つなぐ(FP)×司法書士法人黒川事務所×行政書士黒川事務所の運営サイト)
相続放棄の取り消し・撤回は可能?
相続放棄を行うと、相続人としての地位を失い、故人の負債も含めて一切の財産を相続できなくなります。
故人が多額の債務を抱えていた場合は、相続による債務の負担も免除されるため、相続放棄をすることがおすすめです。
相続放棄が一度受理されると、自己都合での撤回はできません(後から財産が見つかったなど)。ただし、一定の事由がある場合には取り消しが可能なケースも(極稀に)あります。
相続放棄は1回しかできないと思い慎重に判断して行う必要があります。
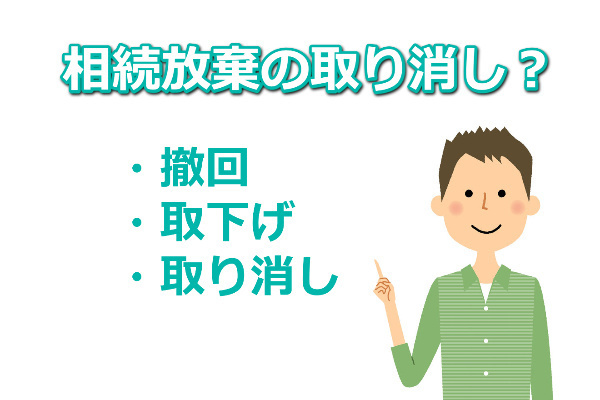
相続放棄は撤回や取り消しはできる?

相続放棄は撤回できません。簡単に相続放棄を撤回できてしまうと、他の相続人の不利益につながるからです。
民法第919条では、相続放棄の申し立てが可能な期間(相続開始から3カ月以内)であっても、相続放棄の撤回は認められないと明言しています。
ただし、民法第919条第2項によって、相続放棄の取り消しは例外的に認められています。相続放棄における撤回と取り消しの違いは以下のとおりです。
| 撤回 | 相続放棄を行った後で発生した問題を理由として、相続放棄の効力を将来に渡って失わせること |
| 取り消し | 相続放棄を行った時点で問題があったため、相続放棄の効力を遡って失わせること |
つまり、相続放棄を行った時点で何らかの問題が発生しており、「本来は相続放棄が受理されるべきではなかった」と証明できる場合、後で相続放棄を取り消すことができます。
「相続放棄をした後で気が変わった」「相続放棄をした後で新たな遺産が見つかった」といったケースは撤回に当たるため、相続放棄を取り消す(撤回する)ことはできません。
相続放棄の撤回と取り消しの違いを正確に把握しておきましょう。
第九百十九条 相続の承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、撤回することができない。
2 前項の規定は、第一編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。
3 前項の取消権は、追認をすることができる時から六箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。相続の承認又は放棄の時から十年を経過したときも、同様とする。
4 第二項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
例外的に相続放棄の取り消しが可能なケース
相続放棄の申し立てがまだ受理されていない場合
第八十二条 家事審判の申立ては、特別の定めがある場合を除き、審判があるまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
判断能力に問題がある人が相続放棄を行った場合
判断能力に問題がある人(制限行為能力者)が相続放棄を行った場合も、後で取り消すことが可能です。制限行為能力者に当てはまる人は以下のとおりです。
-
未成年者(民法第5条)
-
成年被後見人(民法第9条)
-
被保佐人(民法第13条)
-
被補助人(民法第13条)
例えば、民法第5条では、未成年者の法律行為を禁じています。
相続放棄も法律行為に含まれるため、保護者などの法定代理人の同意を得ずに相続放棄を行った場合、後で取り消すことができます。
また、成年被後見人は、重度の認知症や精神障害を理由として、一人で判断するのが難しくなった人のことを指します。成年被後見人が単独で相続放棄を行った場合は、民法第9条の規定により、後見人が後で取り消すことが可能です。
第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
第九条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
本人の「錯誤」によって相続放棄を行った場合
「詐欺」や「脅迫」によって相続放棄を行った場合
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
相続放棄を取り消すときの流れ

相続放棄を取り消す場合は、家庭裁判所で取り消し手続きを行う必要があります。
相続放棄を取り消す流れは以下のとおりです。
-
家庭裁判所に相続放棄を取り消したい旨を伝える
-
取り消しに必要な書類が郵送されてくる
-
相続放棄取消申述書と必要書類一式を家庭裁判所に提出する
-
家庭裁判所による審理を受ける
-
取り消しが認められた場合、相続放棄取消申述受理通知書を受け取る
相続放棄の取り消しは、民法919条3項によって期限が設けられています。
-
相続放棄の取り消しが可能な事実を知ったとき(追認できるとき)から6カ月以内
-
相続の放棄を行ったときから10年以内
期限を過ぎると相続放棄の取り消しができなくなるため、早めに手続きを進めましょう。