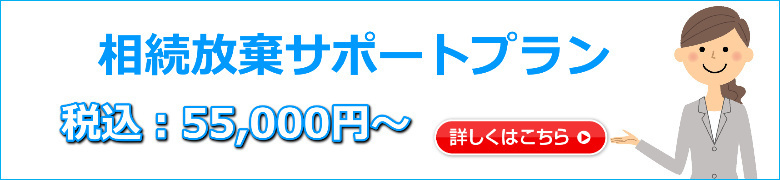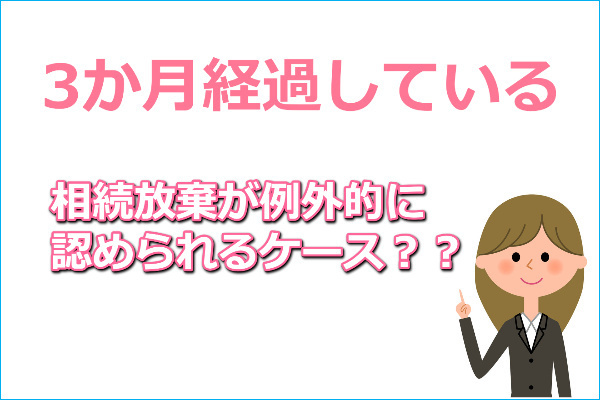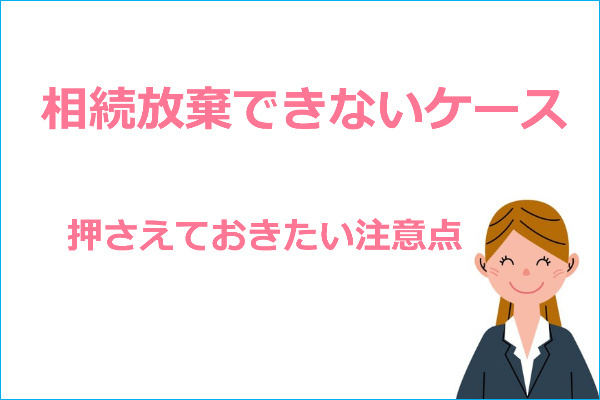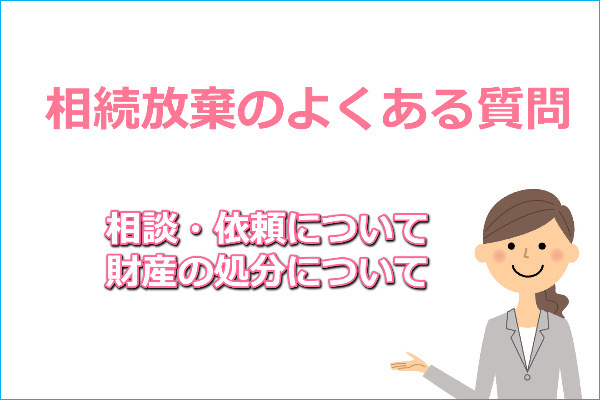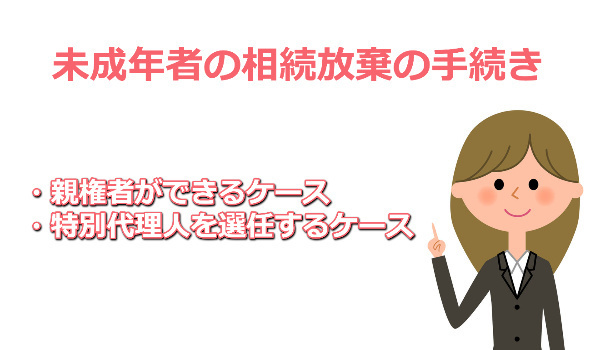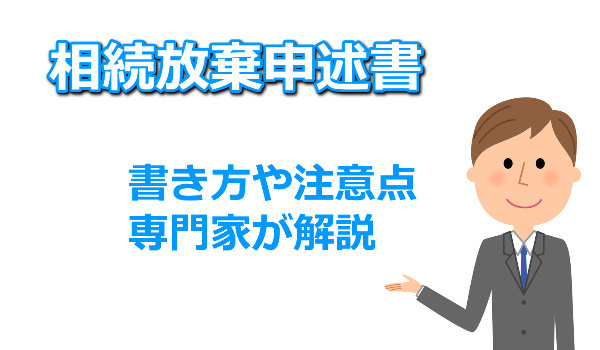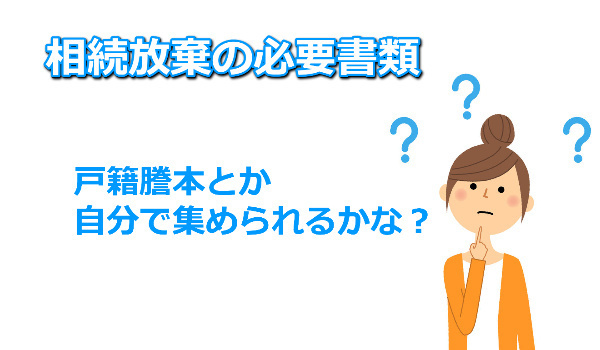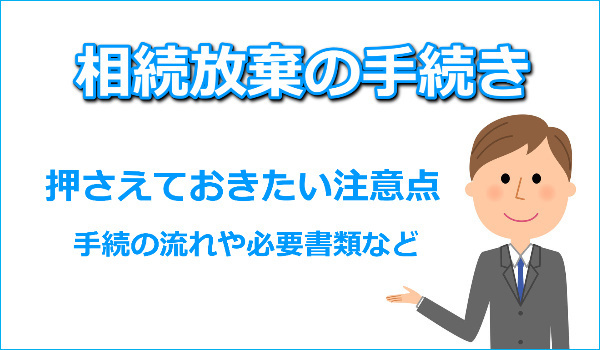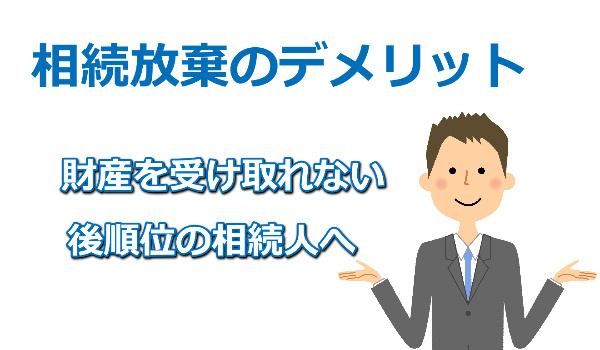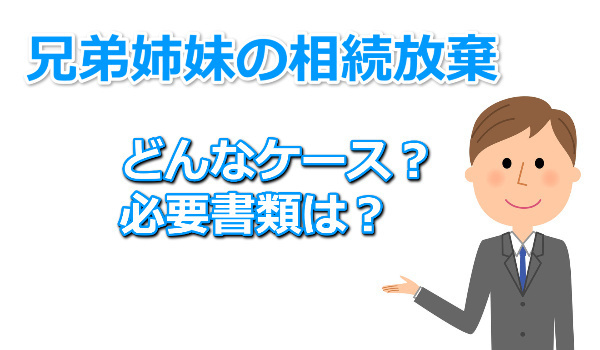相続・遺言に関する手続の総合案内(合同会社つなぐ(FP)×司法書士法人黒川事務所×行政書士黒川事務所の運営サイト)
相続放棄申述受理証明書とは?取得方法や注意点を解説
故人が多額の借金を抱えている場合は、相続放棄の申し立てによって、借金などの債務を一切受け継がない選択をすることができます。
相続放棄を行ったことを第三者に証明するための書類が、家庭裁判所で取得できる「相続放棄申述受理証明書」です。
本記事では、相続放棄申述受理証明書と相続放棄受理通知書の違いや、相続放棄申述受理証明申請の流れ、相続放棄申述受理証明書を発行するときの注意点を分かりやすく解説します。

相続放棄申述受理証明書とは?
相続放棄受理通知書との違い
相続放棄申述受理証明書が必要なケース
相続放棄申述受理証明書が必要なケースは2つあります。
-
故人の債権者に借金の支払いを請求された場合(相続放棄申述受理通知書でも代用可能なケースは多いです)
-
相続した不動産の相続登記をする場合
生前、故人が金融機関やカード会社などから借金をしていた場合、相続人に支払い請求が送られてくることがあります。
相続放棄をしている場合は、相続放棄受理通知書の写しか、相続放棄申述受理証明書のいずれかを提示すれば、借金の支払い義務が免除されます。
また、自分以外の相続人(相続放棄しなかった人)が、不動産の相続登記をする場合、相続放棄申述受理証明書が必要です。
相続放棄受理通知書の写しではなく、公文書である相続放棄申述受理証明書の提出を求められるため、忘れずに相続放棄申述受理証明申請を行いましょう。
相続放棄申述受理証明書の取得方法
相続放棄した本人が取得する方法
相続放棄していない他の相続人が申請するときの必要書類
債権者が申請するときの必要書類
相続放棄申述受理証明書に関する注意点

相続放棄申述受理証明書は再発行できる
相続放棄申述受理証明書は請求期限がある
相続放棄をしたか分からない場合は照会申請が必要
相続放棄申述受理証明申請は弁護士に委任できる
相続放棄申述受理証明申請は、弁護士に委任することもできます。必要書類を用意したり、家庭裁判所の窓口を訪問したりする時間がない人は、専門家に依頼しましょう。
相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会も弁護士に限り、代理で行うことができます。
【まとめ】必要に応じて相続放棄申述受理証明書を取得しよう
相続放棄申述受理証明書は、相続放棄が行われたことを第三者に証明するための文書です。よく似た文書に相続放棄受理通知書がありますが、相続放棄申述受理証明書は不動産の相続登記など、行政手続きの際に必要になります。
相続放棄の申し立てを行っただけでは、相続放棄申述受理証明書は発行されません。家庭裁判所で相続放棄申述受理証明申請を行い、相続放棄申述受理証明書を請求しましょう。
また、相続放棄をした人以外の相続人や債権者などの利害関係人も、相続放棄した人の相続放棄申述受理証明書を取得することが可能です。
相続放棄に関するおすすめ記事
3ヶ月経過している場合の相続放棄
相続放棄ができないケースの紹介
相続放棄に関するよくある質問
未成年者の相続放棄
相続放棄申述書
相続放棄の必要書類
相続放棄の手続き
相続放棄のデメリット
兄弟が相続放棄する
監修者:黒川聡史

保有資格と所属団体
- 司法書士:東京司法書士会所属:登録番号4230号
- 行政書士:東京都行政書士会所属:登録番号第19082582号
- FP(FP技能士1級:日本FP協会CFP®)
経歴
昭和51年生まれ。平成13年司法書士と行政書士の資格取得後、都内司法書士事務所で勤務。平成19年に独立開業し、平成30年に法人化し司法書士法人黒川事務所となる。また、ファイナンシャルプランニング技能士1級及びCFP®を取得しFPとしても活動している(合同会社つなぐ)。