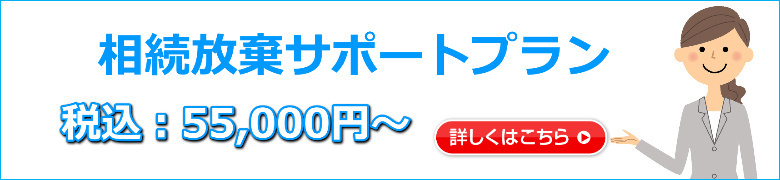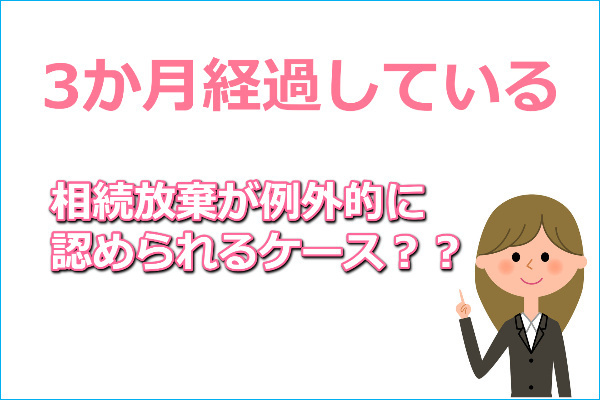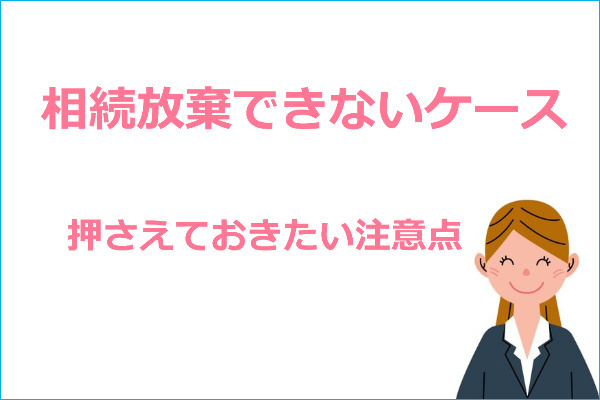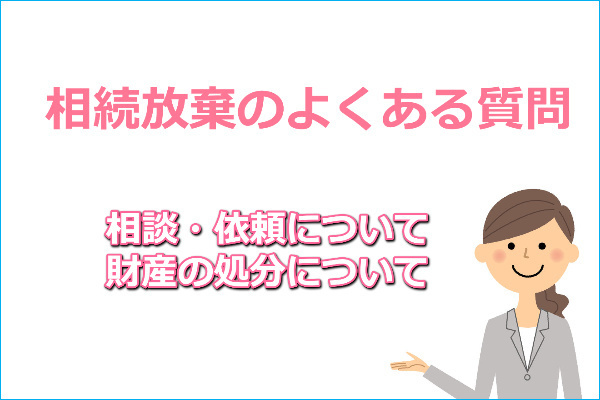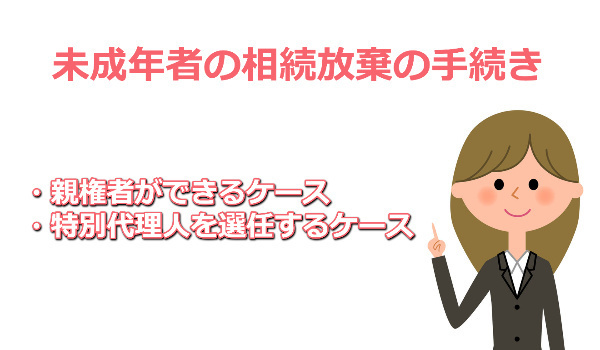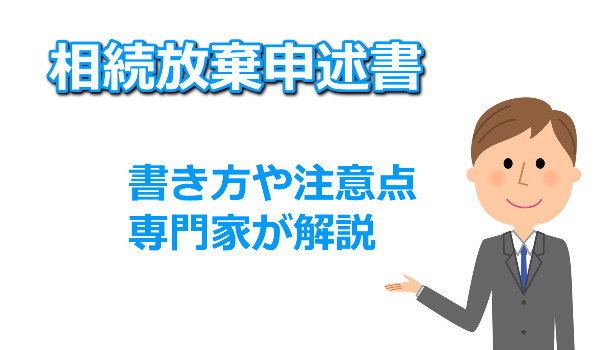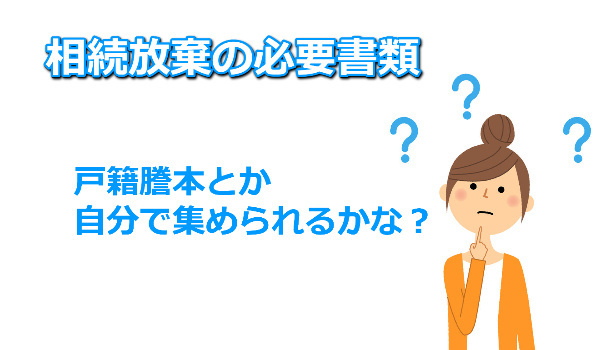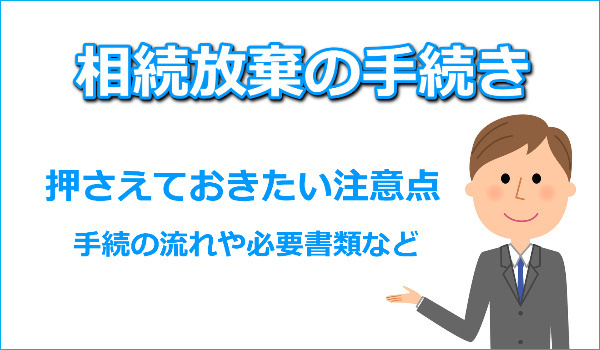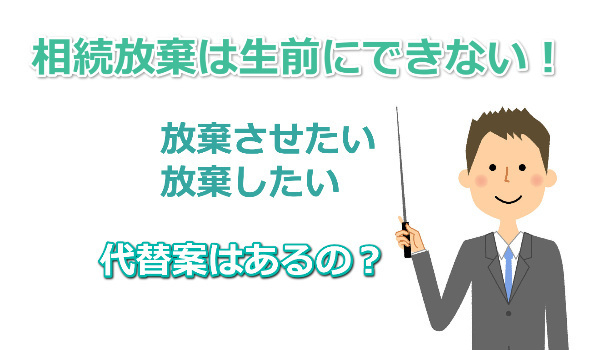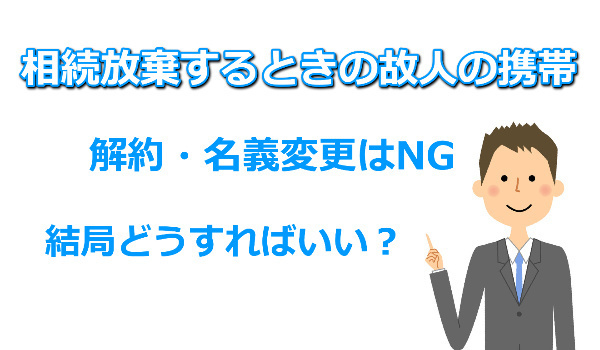相続・遺言に関する手続の総合案内(合同会社つなぐ(FP)×司法書士法人黒川事務所×行政書士黒川事務所の運営サイト)
相続放棄すると代襲相続は発生しない!次の相続人は誰?
相続には、本来相続人になるはずだった人が亡くなっている場合、その相続人の子が相続権を受け継ぐ「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」という仕組みがあります。
被相続人の借金などを理由に相続放棄を行った場合も、代襲相続によって自分の子に相続権が移るのではと不安に思う方もいるでしょう。
実際には、相続放棄と代襲相続は関係がありません。
本記事では、勘違いしやすい代襲相続の定義や、相続放棄と代襲相続の正しい関係を具体例付きで解説します。
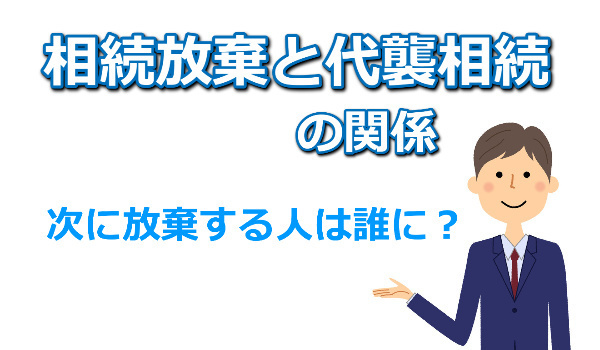
代襲相続とは?
代襲相続とは、本来の相続人がなんらかの理由で財産を相続できないとき、相続人の子(例:被相続人からみて孫など)が相続権を引き継ぐ制度です。
代襲相続は、「相続人の死亡」「相続欠格や推定相続人の廃除」のいずれかを原因として発生します。
代襲相続が発生した場合、代襲相続人は元の相続人(被代襲者)の相続分を引き継ぎます。
そのため、被相続人に借金などの負債があった場合は、代襲相続人が負債の返済義務を負うことになります。
代襲相続人が複数いる場合は、「被代襲者の相続分」を代襲相続人の人数で割って計算します。
代襲相続の範囲は、被相続人の子の代襲相続と、兄弟姉妹の代襲相続で異なります。
被相続人の子の代襲相続
被相続人の子が亡くなっている場合、相続人の子(被相続人から見た孫)に相続権が移ります。
ただし、相続人の子も亡くなっている場合は、その孫(被相続人から見たひ孫)が代襲相続することになります(再代襲相続)。
被相続人の兄弟姉妹の代襲相続
相続放棄すると代襲相続は発生しない
相続放棄とは、相続人としての権利を放棄し、被相続人の財産を一切受け継がないことを指します。相続放棄を行っても、代襲相続は発生しません。
その理由は、代襲相続の発生原因を規定した民法第887条第3項にあります。
相続放棄は、民法第887条で挙げられた代襲相続の発生原因に含まれていません。
そのため、被相続人が残した負債を相続放棄しても、代襲相続によって自分の子へ引き継がれることはありません。
相続放棄と代襲相続の関係!次の相続人は誰になる?
民法では、配偶者以外の相続人の順位について、子(第一順位)、親(第二順位)、兄弟姉妹(第三順位)の順に定めています。
| 相続順位 | 相続人の範囲 |
|---|---|
| 第一順位 | 亡くなった人の子供 |
| 第二順位 | 亡くなった人の直系尊属(父母や祖父母など) |
| 第三順位 | 亡くなった人の兄弟姉妹 |
被相続人の子と親が両名とも相続放棄したケース
被相続人の子・親・兄弟姉妹が全員相続放棄したケース
被相続人の子が相続放棄し、その後祖父が死亡したケース
被相続人の子(A氏)が相続放棄し、その後A氏の祖父(被相続人から見た父)が死亡した場合、誰が相続人となるのでしょうか。
まず、被相続人の財産については相続放棄の申し立てが完了しているため、A氏が引き継ぐことはありません。
ただし、A氏の祖父の財産については、被相続人(A氏の父)がすでに亡くなっており、直系の子孫がA氏しかいないことから、A氏が代襲相続によって引き継ぐことになります。
A氏はすでに父の財産の相続放棄を行っていますが、父が本来の相続人となるはずだった祖父の財産とは関係がありません。
そのため、祖父が多額の借金を抱えているなど、負債を引き継ぎたくない場合は、改めて祖父の分について相続放棄の申し立てをしなければなりません。
被相続人の子と親が両名とも相続放棄し、兄弟姉妹が死亡しているケース
被相続人の子と親が両名とも相続放棄し、兄弟姉妹が死亡しているケースを考えてみましょう。
被相続人の子と親が相続放棄したことで、相続権は第三順位の兄弟姉妹に移りますが、兄弟姉妹は全員死亡しています。
そのため、兄弟姉妹の相続権は、それぞれの子(被相続人から見た甥や姪)に代襲相続されます。
相続人のいずれかが相続放棄を行った場合、誰が財産を相続するのかが複雑になりがちです。
相続放棄と代襲相続の関係を理解し、遺産を正しく分配しましょう。
相続放棄と代襲相続の関係を知り、相続順位を正しく理解しよう
代襲相続の発生原因は、「相続人の死亡」「相続欠格や推定相続人の廃除」のいずれかです。
そのため、相続放棄を行っても、被相続人の借金などが自分の子に引き継がれることはありません。
相続放棄と代襲相続の関係を正しく理解することが大切です。次の相続人が誰か迷ったら、本記事で取り上げた具体例を参考にしてください。
相続放棄に関するおすすめ記事
3ヶ月経過している場合の相続放棄
相続放棄ができないケースの紹介
相続放棄に関するよくある質問
未成年者の相続放棄
相続放棄申述書
相続放棄の必要書類
相続放棄の手続き
生前の相続放棄に?
携帯解約と相続放棄
監修者:黒川聡史

保有資格と所属団体
- 司法書士:東京司法書士会所属:登録番号4230号
- 行政書士:東京都行政書士会所属:登録番号第19082582号
- FP(FP技能士1級:日本FP協会CFP®)
経歴
昭和51年生まれ。平成13年司法書士と行政書士の資格取得後、都内司法書士事務所で勤務。平成19年に独立開業し、平成30年に法人化し司法書士法人黒川事務所となる。また、ファイナンシャルプランニング技能士1級及びCFP®を取得しFPとしても活動している(合同会社つなぐ)。