相続・遺言に関する手続の総合案内(合同会社つなぐ(FP)×司法書士法人黒川事務所×行政書士黒川事務所の運営サイト)
認知症になると家族信託は利用できない?基準を解説
家族信託とは、自分の財産(不動産・預貯金・有価証券等)を、信頼できる家族や相手に託し、特定の人のために、あらかじめ定めた信託目的に従って、管理・処分・承継する財産管理手法です。
家族信託は認知症になった後の財産管理の方法として、成年後見制度とともに注目されていますが、注意しなければならない点もあります。
本記事では、認知症になったときに家族信託が利用できるかどうかや、認知症が進行した後の代替手段を紹介します。
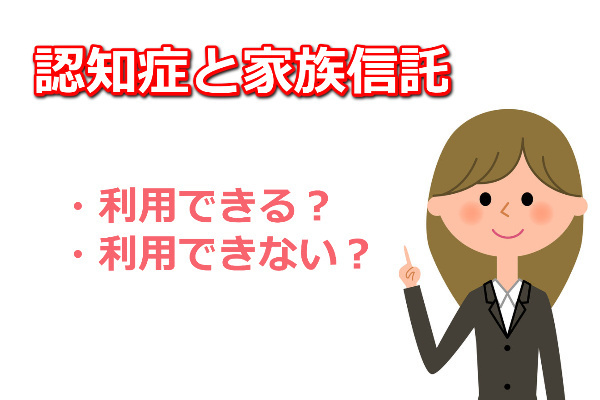
認知症になると家族信託は利用できない?
認知症になっても家族信託を利用できるケース
初期や軽度の認知症の場合
要介護認定を受けたが、判断能力は十分にある場合
認知症になって家族信託を利用できないときはどうする?
認知症が進んで家族信託を利用できない場合、代替手段はあるのでしょうか。
本人が重い認知症や精神障害を発症している場合は、法定後見制度(成年後見制度)を利用することが一般的です。
家族信託の他にも、本人が任意に後見人を選ぶ「任意後見制度」や、家族信託とよく似た効力を持つ「財産管理委任契約」などの財産管理手法があります。
ただし、任意後見制度や財産管理委任契約は、本人の認知症が進むと利用できなくなるため、家族信託の代替手段にはなりません。
法定後見制度は、本人の症状の度合いによって、後見・保佐・補助の3つがあります。
| 種類 | 対象となる方 | 成年後見人等が同意又は取り消すことができる行為 | 成年後見人等が代理することができる行為 |
| 後見 | 多くの手続・契約などを、ひとりで決めることがむずかしい方 | 原則としてすべての法律行為 | 原則としてすべての法律行為 |
| 保佐 | 重要な手続・契約などを、ひとりで決めることが心配な方 | 借金、相続の承認など、民法13条1項記載の行為のほか、申立てにより裁判所が定める行為” | 申立てにより裁判所が定める行為 |
| 補助 | 重要な手続・契約の中で、ひとりで決めることに心配がある方 | 申立てにより裁判所が定める行為 | 申立てにより裁判所が定める行為 |
以下では、後見・保佐・補助のそれぞれの特徴やメリット、家族信託との違いを簡単に解説します。
後見(重い認知症や精神障害を発症した場合)
保佐(中程度の認知症にかかっている場合)
監修者:黒川聡史

保有資格と所属団体
- 司法書士:東京司法書士会所属:登録番号4230号
- 行政書士:東京都行政書士会所属:登録番号第19082582号
- FP(FP技能士1級:日本FP協会CFP®)
経歴
昭和51年生まれ。平成13年司法書士と行政書士の資格取得後、都内司法書士事務所で勤務。平成19年に独立開業し、平成30年に法人化し司法書士法人黒川事務所となる。また、ファイナンシャルプランニング技能士1級及びCFP®を取得しFPとしても活動している(合同会社つなぐ)。



